江戸時代初期、人びとの暮らしに寄り添い、静かで深い祈りを込めて数々の仏像を彫った仏師・円空(えんくう)。
一目見て「円空仏」だとわかる独特の表情とスタイルは、見る者の心に深く響きます。
ノミ1つで、時に荒々しく、時に繊細に、30年以上にわたって彫りつづけた仏像の数は、12万体におよぶと言われています。
その円空はどのような生涯をたどったのでしょうか?
また、円空仏の特徴や魅力はどのようなところにあるのでしょうか?
わかりやすく解説していきます^^
円空って誰?円空の生涯を一覧にした円空年表つき
円空は、江戸時代前期の1632年に美濃国(現在の岐阜県)で生まれました。
江戸幕府3代将軍・徳川家光の治世のときですね。
生まれ育った村は木曽川と長良川にはさまれ、洪水が多く、その洪水のために円空は母親を失います。
そして円空は、尾張の寺に預けられますが、そこでナタとノミを使って彫り始めたのが仏像でした。
その後、円空は、北は北海道から南は九州にいたるまで、日本全国を遊行僧(ゆぎょうそう)としてめぐり、32歳で仏像を彫り始めてから亡くなる64歳までの32年のうちに12万体(!)もの神仏を彫ったと言われています。
これは、飛騨高山の桂峯寺(けいほうじ)に安置されている今上皇帝立像(1690年)の背面に「当国万仏十マ仏作己」(全国で10万体を造り終えた)と墨書されているのが根拠です。
そうだとすると、単純計算でも、円空は年間3750体ものペースで仏像を彫りつづけたということになります。
なんというバイタリティ!
いったい、この原動力は何なのでしょうか?
円空は全国を遊行するなかで各地の寺院の住職や民衆と交流し、悩み苦しむ人のためには菩薩像を、病に苦しむ人のためには薬師像を、災害に苦しむ人のためには不動明王像を、干ばつに苦しむ人のためには龍王像を、生命の危機に瀕した人のためには阿弥陀像を彫ったと言われています。
これは、民衆を救いたいという強い意志と使命感にもとづいていなければ、なかなかできないはずです。
では、なぜそれほどまでに民衆を救いたかったのかと推測すれば、幼いころに洪水で母親を失ったときの自分と同じような苦しみを和らげてあげたいという衝動があったからではないでしょうか。
つまり、民衆の救いの底に、自分自身の救いがあり、それが円空仏制作の原動力になっていたと私には思えます。
晩年の円空は、長良川にほど近い弥勒寺(現・岐阜県関市)を再興し、そこを拠点に仏像制作を続けましたが、1695年、死期を悟ると、母親を失った長良川のほとりで、みずから即身仏となって入定し、64年の生涯を閉じたのでした。
円空年表
| 1632年 | 1歳 | 美濃国(岐阜県)に生まれる |
| 1650年 | 19歳 | 長良川の洪水で母親を失う |
| 1654年 | 23歳 | 某寺を遁出(『近世畸人伝』) |
| 1663年 | 32歳 | 11月6日、岐阜県郡上市・神明神社の神像など3体(天照大神・阿賀田大権現・八幡大菩薩)を造像 |
| 1664年 | 33歳 | 9月、郡上市・白山神社の阿弥陀像を造像 12月、郡上市・子安神社の諸像を造像 |
| 1666年 | 35歳 | 津軽藩弘前城下を追われ、青森を経て松前へ渡る(『津軽藩日記』) 北海道をめぐり、多数の仏像を彫る |
| 1669年 | 38歳 | 名古屋市千種区・鉈薬師寺堂の十二神将等の諸像を造像 10月18日、岐阜県関市・白山神社で白山三尊を造像 |
| 1670年 | 39歳 | 11月、郡上市・黒地神明社の天照皇大神像を造像 |
| 1671年 | 40歳 | 岐阜県美濃加茂市で馬頭観音像を造像 7月15日、法隆寺の巡尭春塘から「法相中宗血脈」を受ける(円空自筆同血脈写) 関市洞戸菅谷の不動明王像を造像 |
| 1672年 | 41歳 | 5月、郡上市・長瀧寺別当寺阿名院に十一面観音像を残す(『白鳥町史』資料編) 6月、郡上市・八坂神社の牛頭天王像を造像 |
| 1673年 | 42歳 | 奈良県天川村・栃尾観音堂の諸像を造像 |
| 1674年 | 43歳 | 3月、三重県志摩市・三蔵寺の『大般若経』600巻を修復し、その扉に添絵54枚を描く(同寺旧蔵『大般若経』奥書) 6月上旬から8月中旬に志摩市・立神薬師堂の『大般若経』を修復。130枚の添絵を描き、62巻末尾に和歌を墨書(同堂蔵『大般若経付属文書』) |
| 1675年 | 44歳 | 9月、奈良県吉野郡の大峯山で役行者像を刻む(背銘) |
| 1676年 | 45歳 | 名古屋市守山区・龍泉寺で馬頭観音像や千体仏を造像(馬頭観音像背銘) 名古屋市中川区・荒子観音寺で仁王像一対、余材で千体仏等を造像(『浄海雑記』) 12月25日、『両頭愛染法』を書写し、荒子観音寺に残す(『浄海雑記』) |
| 1679年 | 48歳 | 7月5日、滋賀県大津市・園城寺の尊栄から「仏性常住金剛宝戒相承血脈」を受ける(円空自筆同血脈写) 岐阜県羽島市・中観音堂蔵の護法神を造像(背銘) |
| 1680年 | 49歳 | 茨城県笠間市・月崇寺の「御木地土作大明神」像を造像(背銘) |
| 1681年 | 50歳 | 4月14日、群馬県富岡市・貫前神社で大般若経を見終り、奥書に墨書を残す |
| 1682年 | 51歳 | 9月9日、栃木県日光・円観坊で十一面千手観音像を造像(背銘) 日光の高岳法師から「サラサラ童子法」「勤行祭礼之縁日」「七仏薬師一切秘法」等を受ける(円空自筆書写文書) |
| 1684年 | 53歳 | 岐阜県関市・高賀神社に滞在し、漢詩を詠む(同神社蔵『詩歌集』) 荒子観音寺住職・円盛法印から「天台円頓菩薩戒師資相承血脈」を受ける(円空愛用経本) 12月25日、名古屋市熱田区・熱田神宮で「読経口伝明鏡集」を書写 |
| 1685年 | 54歳 | 岐阜県高山市・千光寺蔵の円空作弁財天像3体を納めた厨子の扉内側に「貞享二年五月吉祥日」とあることから(貞享2年=1685年)、飛騨滞在が確か |
| 1686年 | 55歳 | 1月17日、羽島市・稲荷神社の御神体を造像 3月、高山市で不動像等を造像 6月、8月に長野県南木曽町・等覚寺で天神像、弁財天并十五童子等を造像 |
| 1689年 | 58歳 | 3月7日、滋賀県米原市・太平寺で十一面観音像を造像(背銘) 6月、日光・明覚院で観音像を造像 8月9日、滋賀県大津市・園城寺の尊栄大僧正から「授決集最秘師資相承血脈」と「被召加末寺之事」の書面を受け、自坊の関市・弥勒寺が天台宗寺門派総本山園城寺内霊鷲院兼日光院末寺に召し加えられる(「被召加末寺之事」文書) |
| 1690年 | 59歳 | 高山市で十一面観音など三体を造像。そのうちの今上皇帝像の背面に10万体造像達成を記す |
| 1691年 | 60歳 | 1月、歌集「熱田太神宮金淵龍王春遊に」を詠む(円空歌集) 4月20日、岐阜県下呂市・薬師堂で青面金剛神像を造像 5月8日、高山市・八幡神社で八幡大菩薩像を造像 |
| 1692年 | 61歳 | 4月11日、関市・高賀神社で十一面観音像等を造像 5月、「円空歌集」の一紙に「元禄五年壬申暦五月吉日」と書きのこす |
| 1695年 | 64歳 | 7月13日、弟子の円長に「授決集最秘師資相承血脈」を与える 7月15日、かねてからの願いどおり、長良川畔で入定(墓碑銘) |
円空の仏像(円空仏)の特徴と魅力とは?代表作は?
円空がつくった仏像=円空仏は、約300年前に造像された作品なのに、まるで古さを感じさせません。
その最大の理由は、円空の仏像の彫りかたにあると言えます。
ふつう仏像をつくるときは、経典に記されているように持ち物や姿を表現するのですが、円空はそれを意に介せず、抽象的で自由に彫っています。
木のなかに宿る仏をナタやノミで荒くシンプルに削り出すような彫りかたです。
そのような彫りかたをした仏師は、後にも先にも円空だけです。
そのため、円空の仏像はひと目見て「円空仏だ!」とわかる独自性をそなえていて、古びて見えることがないのです。
また、円空仏の多くは、口元に微笑みをたたえた表情をしています。
それは、如来像や菩薩像だけでなく、ふつうは忿怒(ふんぬ)の表情をしている明王像や仁王像でも例外ではありません。
〝怒っているのに笑っている〟という、なんともユーモラスな表情。
だから、円空仏はいつも生き生きとして見えるのでしょう。
これらが円空仏の特徴であり、また、魅力になっているように思われます。
こうした円空の仏像の彫りかたは、仏像を寺や有力者のためではなく、悩み苦しむ名もなき民衆のためにつくったことと関連しているようです。
円空はよく、道ばたに転がっているような木の端から仏を彫り出しました。
ふぞろいな木の破片に目、鼻、口だけを表現したような荒削りでシンプルな小像で、「木っ端仏」(こっぱぶつ)と呼ばれています。
遊行で滞在した村の人びとのために、限られた時間のなかで仏像を彫るには、そんなに形状や細部に凝ることはできません。
ササッとシンプルにインスタントに彫る必要があります。
そうした状況が独特の円空仏を生み出したと私には思えますし、だからこそ生涯で12万体もの仏像を彫ることができたのだと思います。
しかし、彫りかたはシンプルでインスタントでも、そこに込められた円空の思いや願いは強かったのではないでしょうか。
なぜなら、「木っ端仏」の多くが、捨てられることなく、今も大切に受け継がれているからです。
さて、そうやって受け継がれてきた円空仏は約5000体が現存していますが、1番の代表作と言われているのが飛騨高山の千光寺にある「両面宿儺坐像」(りょうめんすくなざぞう)です。
三井記念美術館開催の円空展である「特別展 魂を込めた円空仏――飛騨・千光寺を中心にして」では、もっとも注目されました。
▼「特別展 魂を込めた円空仏――飛騨・千光寺を中心にして」の紹介記事あり↓↓↓
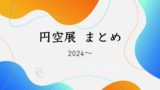
〝円空といえば「両面宿儺坐像」〟というくらい、円空仏の象徴となっています。
この他、荒子観音寺の住職に頼まれてつくった一対の仁王像の余材でつくった「聖観音菩薩」や、岐阜県・高賀神社でつくられた最後の作品の1つである「十一面観音菩薩立像」が円空の代表作として挙げられます。
▼両面宿儺坐像の魅力を語っています♪↓↓↓

〝円空仏のメッカ〟岐阜・千光寺
円空が生まれ没した美濃国=岐阜県。
この岐阜県には、1000体を超える円空仏が確認されています。
現存する円空仏は約5000体と言われていますから、5分の1以上が岐阜県に存在する計算になります。
なかでも、貴重な円空仏が安置されているのが、高山市の千光寺です。
円空は1685年、54歳のときに千光寺を訪ね、住職と意気投合したのをきっかけに、約1年間、千光寺を拠点にして飛騨各地をめぐり、数多くの仏像を彫り、また「袈裟百首」という歌集も残したそうです。
その縁で、海抜約900メートルの山中に位置する千光寺には「円空仏寺宝館」があり、現在64体の円空仏が所蔵され、「立木仁王像」「両面宿儺坐像」「三十三観音像」などの作品を拝観することができます。
まさに千光寺は〝円空仏のメッカ〟なのです。
まとめ
- 円空は日本全国を遊行僧としてめぐり、64年の生涯のうちに12万体もの神仏を彫った、江戸時代を代表する仏師である
- 円空仏は木のなかに宿る仏をナタやノミで荒くシンプルに削り出すようにして彫られた
- 円空仏の多くは、口元に微笑みをたたえた表情をしている
- 円空は仏像を寺や有力者のためではなく、悩み苦しむ名もなき民衆のためにつくった
- 円空のいちばんの代表作は「両面宿儺坐像」(飛騨高山・千光寺)である
- 千光寺には「円空仏寺宝館」があり、現在64体の円空仏が所蔵され、「立木仁王像」「両面宿儺坐像」「三十三観音像」などの作品を拝観することができる
▼2024年以降の円空展をまとめています↓↓↓
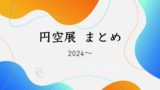
▼円空仏と木喰仏の違いについて知りたい方は、こちら↓↓↓



