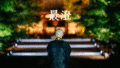【この記事でわかること】
- 空海が唐で何を学んだか
- 最澄とどのような関係だったのか
- 日本でどのようなことを行なったのか
空海の年表
| 774年 | 讃岐国多度郡屏風浦(現在の香川県善通寺市)に生まれる |
| 788年 | 桓武天皇の皇子伊予親王の侍講(家庭教師)を務めていた叔父・阿刀大足のもとで儒教を学ぶ |
| 789年 | 平城京へ上京 |
| 791年 | 大学(明経道専攻)へ入学 「虚空蔵求聞持法」を知る |
| 792年 | 大学を中退。名を「空海」と改める |
| 797年 | 『三教指帰』を著す |
| 804年 | 4月9日、東大寺戒壇院で具足戒を受けて得度する 留学生として遣唐使船で唐へ渡る |
| 805年 | 青龍寺の恵果から胎蔵界と金剛界の灌頂を授かる |
| 806年 | 10月に帰国。太宰府(現・福岡県)に留め置かれる 『御請来目録』を献上 |
| 809年 | 平安京へ入京 高雄山寺へ入山 最澄から密教経典借用の申し出 |
| 812年 | 高雄山寺で最澄とその弟子に灌頂を授ける |
| 813年 | 11月、最澄からの『理趣釈経』借用の申し出を断る |
| 816年 | 最澄と決別。嵯峨天皇から高野山を下賜される |
| 821年 | 満濃池の修繕工事 |
| 823年 | 嵯峨天皇から東寺(教王護国寺)を下賜される |
| 827年 | 大僧都(だいそうず)に任じられる |
| 828年 | 庶民向けの私立学校「綜藝種智院」を設立 |
| 832年 | 高野山へ移り住む |
| 835年 | 3月21日、高野山で〝入定〟 |
| 921年 | 醍醐天皇から「弘法大師」の諡(おくりな)が授けられる |
▼空海についてさらに広く知りたい方は、こちら↓↓↓

空海の生涯
空海は超エリート!
空海(くうかい)は、774年から835年までの平安時代初期を生きた僧侶で、真言宗(しんごんしゅう)の開祖です。
生まれは讃岐(さぬき)国多度郡(現在の香川県善通寺市)で、同じ平安時代を生き、天台宗(てんだいしゅう)を開いた最澄より7歳年下です。
空海の幼名は「真魚」(まお)。
真魚は、12歳で地方役人を養成する学校へ入学し、15歳のころに誘いを受け、平城京へ上京。
桓武天皇の皇子・伊予親王の侍講(家庭教師)を務めていた叔父・阿刀大足(あとのおおたり)のもとで儒教を学び、18歳(791年)のときに大学(官吏になるための教育機関)へ入学します。
空海は超エリートだったんですね!
大学では歴史、詩文、算術、法律などを幅広く学びました。
そのなかで密教(インドで興った大乗仏教の一派で、秘密仏教とも呼ばれる)の「虚空蔵求聞持法」(こくうぞうぐもんじほう:密教の修行法で、記憶力の増進が目的)を知ったことをきっかけに、仏教に興味を抱きます。
世俗の出世の道を捨てた空海は、792年に大学を中退。
19歳で出家し、修行のために四国各県や奈良県の吉野山をめぐりました。
▼空海についてさらに広く知りたい方は、こちら↓↓↓

空海、密教を受け継ぐ
空海は、20歳で僧侶になるために受戒すると、22歳で名を「空海」と改めました。
このころの空海の考え方は、儒教、道教、仏教の3人の師が放蕩息子を改心させようとする自著『三教指帰』(さんごうしいき)で知ることができます。

その空海は、修行のなかで密教経典の『大日経』と出会い、唐で密教を修得したいという思いを強くします。
そしてついに、空海が31歳のとき、遣唐使に選ばれ、「留学生」(るがくしょう)として唐へ渡ります。
遣唐使の船は暴風雨や漂流に見舞われ、空海が乗った船は予定よりもだいぶ南の福州に漂着しました。
中国へ渡るというのは、当時としては命がけだったんですね。
唐の都・長安へ向かった空海は、密教の修得に必要なサンスクリット語(古代インド語)や最先端の学問を修得したのち、密教の高僧・恵果(けいか:746〜805)を青龍寺に訪ねました。
密教は当時の中国で最先端の仏教で、中国や朝鮮半島から1000人を超える弟子が集まっていました。
これだけの数の弟子がいながら、恵果は空海をひと目見たときから、ただ者ではないと見抜き、すべてを伝授するにふさわしい僧だと即断したようです。
真言密教の後継者にする儀式である「灌頂」(かんじょう)を行い、空海のために弟子たちに経典を書写させたり、「曼荼羅」(まんだら:仏教の世界観をわかりやすく表現した絵図)や仏具をつくらせたりしました。
その間、わずか3ヵ月!
恵果は、空海に密教のすべてを伝授したのです。
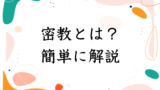
ちなみに、灌頂のとき、目隠しをして曼荼羅に花を投げ、その花が落ちたところに描かれている仏と縁を結ぶ「投華得仏」(とうげとくぶつ)を行いますが、空海が投げた花は2回とも、密教最高の仏である大日如来(だいにちにょらい)のところに落ちたと伝えられています。
空海を正式な後継者とすると、恵果は自身の使命を終えたと感じたのか、この世を去ります。
そして空海は、「一日も早く日本へ戻り、密教を広めよ」という恵果の遺言どおり、20年の留学予定を2年で切り上げ、806年に帰国します。
空海が2年で帰国するなんて、みんなさぞかし驚いたことでしょう。
▼空海についてさらに広く知りたい方は、こちら↓↓↓

最澄が空海の弟子に
2年で帰国したことが問題視されたのか、空海は約3年、平安京へ入ることができず、太宰府に留め置かれました。
その間、空海は、自分が唐で学んだ教えや持ち帰った経典、法具などを一覧にした『御請来目録』(ごしょうらいもくろく)を朝廷へ提出しています。
その目録を見た最澄は、なんと空海が都へ戻ると灌頂を受け、弟子となりました。
朝廷に注目されはじめていた当時の最新仏教である密教を最澄も唐で学びましたが、その学びは不完全かつ部分的なもので、そのことを最澄自身がよくわかっていたのです。
そこで最澄は、完全な密教を学んで帰ってきた空海の弟子となることで、不足を補おうとしたのだと思われます。
きっと最澄は、仏教の第一人者というプライドをかなぐり捨ててまで、みずからが開いた天台宗を発展させようとしたのではないでしょうか。
空海と最澄の関係は、文献や経典の貸し借りをするなど最初は良好でした。
しかし、密教経典の注釈書である『理趣釈経』(りしゅしゃくきょう)を借用したいという最澄の申し出を空海が断ったことを境に、最澄との関係は冷え込んでいきます。
そして、最澄が密教を学ばせるために空海のもとに預けていた弟子の泰範(たいはん)が比叡山へ戻ることを空海が拒否したことで、空海と最澄は決別しました(異説あり)。
空海には空海なりの思いがあって、最澄の要望を冷たくあしらったわけでは決してありませんが、最澄はさぞや無念だったと思います。
▼空海と最澄の関係についてさらにくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

密教の布教と社会事業に力を注いだ空海
この出来事は816年のことですが、同じ年、空海は真言密教を広めるための拠点として、高野山(こうやさん)を下賜(かし)され、ここに金剛峯寺(こんごうぶじ)を創建し、修行の場とします。
高野山は山全体が境内となっており、今では100以上の寺院が密集しています。
さらに、823年には、嵯峨天皇から京都の東寺(とうじ)を託されました。
この東寺の名前を空海は「教王護国寺」(きょうおうごこくじ)と改め、密教布教の拠点としました。
ちなみに、私は東寺へ何度も行っていますが、講堂の「立体曼荼羅」は必見です!
密教の世界観を21体の巨大な仏像によって表現しており、見る者を圧倒する迫力に満ちています^^
一方で、空海は民衆のために、さまざまな社会事業を行なっています。
その代表が、満濃池(まんのういけ:香川県仲多度郡)の修繕工事と「綜芸種智院」(しゅげいしゅちいん)の設立です。
満濃池はダムによるため池で、よく決壊を繰り返していて、空海が唐から持ち帰った当時の最新土木技術を用いてダムを修繕しました。
わずか3ヵ月で工事を完了したというから驚きです。
一方、「綜芸種智院」とは、庶民の教育のために設立した私立学校で、当時、教育を受けられるのは貴族や官僚の子弟に限られていたのに対し、身分に関わりなく入学できる点が画期的でした。
仏教、儒教、道教などの思想や学芸を教えていたようです。
空海の死後は廃校になりましたが、現在、種智院大学(京都市)や高野山大学が、その精神を継承しています。
832年、空海は59歳になると高野山に移り住み、真言宗の基盤を強化する活動に身を献げました。
そして、835年、弟子たちが読経するなか入定(にゅうじょう)した(亡くなった)のです。
享年62歳。
現代人の感覚からすれば、まだまだこれからという年齢で亡くなったという印象ですね。
なお、空海は「弘法大師」(こうぼうだいし)とも呼ばれますが、その名が贈られたのは、入定から86年が経った921年で、醍醐天皇からでした。
▼空海についてさらに広く知りたい方は、こちら↓↓↓

まとめ
- 空海は、774年から835年までの平安時代初期を生きた僧侶で、真言宗の開祖
- 空海は31歳のとき、遣唐使に選ばれ、「留学生」として唐へ渡る
- 空海は最澄に灌頂を授け、弟子としたが、その後決別してしまった
- 816年、空海は高野山を下賜され、金剛峯寺を創建
- 満濃池の修繕工事や綜芸種智院の設立など、社会事業に力を尽くした
- 晩年は高野山に移り住み、835年に入定(死去)
▼空海についてさらに広く知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海の数々の著作についてざっと知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海が遺した言葉について知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海の映画(2018年)について知りたい方は、こちら↓↓↓