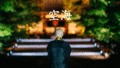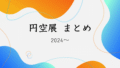【この記事でわかること】
- なぜ空海は満濃池の修復に関わることになったのか?
- 空海の修復事業が持つ意味とは?
満濃池と空海①讃岐の地に刻まれた民衆救済への願い
あなたは満濃池(まんのういけ)をご存じでしょうか?
満濃池は、香川県仲多度郡まんのう町にあります。
地元の方ならもちろんのこと、行ったことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
満濃池は、農業用水を確保するために人工的に作られた〝ため池〟です。
しかし、池といっても周囲は約20キロメートル。
長野県の諏訪湖よりひとまわり大きい巨大池です。
というより、もう湖ですね^^;
その膨大な水量は、周辺の田畑を潤し、讃岐平野の豊かな実りを支え続けています。
そして、この満濃池の歴史を語るうえで決して欠かすことのできない人物が、弘法大師・空海なのです。
空海は、宗教家として活躍しただけではなく、土木技術、教育、芸術など多岐にわたる分野で才能を発揮した〝超マルチタレント〟で、その功績は現代にまで伝えられています。
なかでも、空海の出身地にほど近い満濃池の改修事業は、民衆の生活を豊かにするために尽力した空海の人間的な魅力と、その卓越した実行力を如実に示しました。
空海はいかにして満濃池の修復に携わることになったのか?
その修復事業は当時の社会にどのような影響を与えたのか?
讃岐の地に刻まれた空海の足跡をたどり、彼の民衆救済への熱い願いに迫ってみます^^
満濃池と空海②たび重なる決壊と修復
満濃池は、日本を代表する歴史あるため池の1つです。
その築造は奈良時代初期にまでさかのぼります。
満濃池自体は知っていましたが、そんなに古いため池だったとは驚きです。
聖武天皇の時代、701年から704年にかけて、讃岐国の国守(くにのかみ)の道守朝臣(みちもりあそん)が中心となり、干ばつに苦しむ讃岐平野の農民を救うために、満濃池は築かれました。
当時の土木工事としては驚異的な規模であり、その完成は地域の人びとにとって、まさに「命の水」をもたらす存在でした。
当時の人びとの喜ぶ顔が眼に浮かぶようです^^
しかし、その後の満濃池は何度も自然災害に襲われました。
とりわけ、大規模な洪水や地震によって堤防が頻繁に決壊し、そのたびに周辺の田畑は水没し、多くの農民が生活基盤を失うという悲劇に見舞われました。
犠牲者も少なからずいたのだろうと推測します。
決壊と復旧が繰り返されるなかで、平安時代初期には大規模な決壊が起こり、その修復は困難を極め、一時は機能不全の状態になったとも伝えられています。
水利の確保は、当時の農業社会においてもっとも重要な課題であり、満濃池の機能不全は讃岐国の民衆にとって死活問題でした。
農業関係者にとって、水に対する意識は今よりもっと鋭敏だったのでしょうね。
満濃池と空海③最新の土木技術を駆使し、驚異の短期間で大事業を完成!
空海は806年に唐から帰国し、真言密教の布教に尽力していましたが、同時に故郷・讃岐の窮状にも心を痛めていました。
818年、讃岐国は大洪水に見舞われ、満濃池はまたしても決壊しました。
堤防が崩れ、池の底には泥が堆積し、ため池としてほとんど機能しなくなってしまいました。
これを受けて、朝廷の築池使・路真人浜継(ちくちし・みちのまひとはまつぐ)が修復に乗り出します。
しかし、技術的な困難と人手不足によって、1年経っても修復のメドが立ちませんでした。
そこで、国守・清原夏野の発議により、嵯峨天皇から責任者に任命されたのが空海でした。
821年のことです。
現地入りした空海は、地元から熱烈な歓迎を受けました。
そして、空海を慕って多くの人びとが集まり、修復作業の人手不足は解消されました。
人手不足が一気に解消されてしまうなんて、すごい人気だったのでしょうね。
空海は、唐で学んだ最新の土木技術を次々と採用しました。
そして、水圧を考慮した「アーチ型堤防」や、洪水時にあふれた水を流す「余水吐」(よすいばき)と呼ばれる水路などをつくりました。
一方で、空海は満濃池の堤防が見える高台に護摩壇(ごまだん)をつくり、工事の成功を祈願したようです。
その高台は現在も残っていて、「護摩壇岩」と呼ばれています。
その祈りの効果もあってか、満濃池の修復はわずか2ヵ月で完了!
空海はこの功績によって賜った報奨金によって、満濃池の北西岸に神野寺(かんのじ)を建立しています。
なお、生涯にわたっていかに超人的な活躍をした空海といえども、満濃池の工事の規模から考えて、着工から竣工まで2ヵ月というのは、あまりに短すぎます。
おそらく、前任の築池使・路真人浜継が、ある程度の工事を進めていて、後任の空海が残りを完成させたのではないでしょうか。
もっとも、空海が持つ知識と技術、そして人望が大いに貢献したことはまちがいありません。
空海による満濃池の修復は、平安時代末期に成立した『今昔物語』に記されました。
それほどの大事業だったんですね。
ちなみに、満濃池は、現在でも日本最大級の農業用ため池となっています。
満濃池と空海④空海の「利他」の精神と現代へのメッセージ
空海による満濃池の修復は、たんなる土木事業の成功にとどまりません。
そこには、〝自分のことよりも他人の幸福を願う〟という慈悲に満ちた「利他」(りた)の精神が見て取れます。
空海は、仏教の教えを広めることを使命としていましたが、座学や儀式で事足りるという考えはまるで持ち合わせていませんでした。
空海は、民衆の苦しみ、とりわけ当時の農民にとって死活問題だった水の問題に正面から向き合いました。
そして、その解決のために、自身が持つ知識、技術、そして労力を惜しみなく捧げました。
満濃池の修復は「現世利益」(げんぜりやく)、つまり、この世での幸福や利益を求める人びとの願いに応えるという真言密教の考え方を実践したものでもあったはずです。
その結果、讃岐の人びとはふたたび豊かな収穫を得られるようになり、生活が安定しました。
空海の功績は民衆の心に深く刻まれ、「お大師さま」として、現在にいたるまで慕われ続けています。
空海は、ほんとうに多くの人びとを救ったのです。
現代社会において、私たちはさまざまな問題に直面しています。
自然災害、貧困、社会の分断など、解決すべき課題は山積しています。
このような時代だからこそ、空海が満濃池の修復事業を通じて示した「利他」の精神と、困難に立ち向かう実践的な行動力は、私たちに大きなメッセージを投げかけているのではないでしょうか。
私たちは、各自が置かれた立場や分野で他者=社会のために何ができるかを考え、行動を起こすことの重要性を、空海の満濃池の修復から学ぶことができるのだと思います。
まとめ
- 決壊と修復を繰り返していた満濃池だったが、818年の深刻な決壊をきっかけに、空海は嵯峨天皇から修復の責任者に任命された
- 空海は唐で学んだ最新の土木技術を用いて、2ヵ月で修復を完成させた
- 修復作業は「利他」の精神にもとづき、人びとへ「現世利益」をもたらす実践だった
▼空海の生涯についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海について広く知りたい方は、こちら↓↓↓