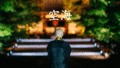【この記事でわかること】
- 空海の十大弟子は2つのグループに分けられる
- 空海の十大弟子の10人はそれぞれどんな僧侶だったか
- 空海が十大弟子に期待したこと
空海の十大弟子は「生え抜き」と「移籍組」に分けられる
平安時代の高僧・空海は生前、たくさんの弟子を育てました。
なぜ空海のもとに数多くの弟子が集まったのかというと、嵯峨天皇が空海に帰依し、鎮護国家の修法(しゅほう:ある目的のために行う密教の作法)を行なったことと、最澄に灌頂を授けた=最澄が空海の弟子になったことの2つが大きな理由です。
この理由により、空海の名は日本全国に広まり、密教を修得しようとする若者や、すでに僧侶である者が空海のもとに集まりました。
天皇が帰依したり、日本一の高僧を弟子にしたりすれば、「すごい人だ! 自分も教えを請いたい!!」と思う人が大勢出てきて当然ですよね。
そうして集まった空海の弟子たちのなかでも、特に優秀な10人の弟子のことを「空海の十大弟子」といいます。
この呼び名は、後世の人たちが、釈迦(シャカ)の十大弟子になぞらえてつけられました。
当時の人びとからすれば、それほど偉大な高僧だったということでしょう。
彼ら十大弟子は、2つのグループに分けることができます。
1つは、空海のもとで得度(とくど:出家して受戒すること)した僧侶です。
いわゆる「生え抜き」のグループですね。
このグループには、智泉(ちせん)、真雅(しんが)、真済(しんぜい)、真如(しんにょ)がいます。
智泉以外は、名前(法名)に「真」がついているのが特徴です。
もう1つのグループは、空海の弟子になる前に別の師のもとで得度した僧侶です。
いわゆる「移籍組」ですね。
このグループには、実恵(じちえ)、道雄(どうゆう)、杲隣(ごうりん)、円明(えんみょう)、泰範(たいはん)、忠延(ちゅうえん)がいます。
生え抜きよりも移籍組のほうが多いんですね。
空海の十大弟子①智泉
読み方は「ちせん」。
生年は789年で、没年は825年です。
智泉の母親は空海の姉です。
つまり、智泉は空海の甥に当たります。
幼いときから空海にかわいがられ、空海が遣唐使になったときは、いっしょに唐へ渡りました。
高野山を継ぐはずでしたが、30代後半にして病気で亡くなりました。
空海はかなり嘆き悲しんだにちがいありません。
空海の十大弟子②真雅
読み方は「しんが」。
生年は801年で、没年は879年です。
78歳まで生きたのは、当時としては長生きですね。
真雅は、空海の実の弟です。
ただし、実の弟といっても、774年生まれの空海とは27歳も歳が離れています。
兄弟というよりも親子に近いですね。
ひょっとしたら異母兄弟かもしれません。
真雅は、清和天皇や有力貴族であった藤原氏からとても信頼されていました。
東大寺の別当職(長官)を務めたことがあります。
空海の十大弟子③真済
読み方は「しんぜい」。
生年は800年で、没年は860年です。
空海に才能を見込まれ、25歳で灌頂を受け、阿闍梨(あじゃり:弟子を導く師匠)となっています。
真済は、よほど優秀だったのだと思います。
後述する実恵のあとに、教王護国寺(東寺)の長者(長官)になりました。
15歳のときに空海のもとで出家し、才能を見込まれ、25歳のときに伝法灌頂(でんぽうかんじょう:修行を終えた者に阿闍梨の位を授ける儀式)を受けています。
空海から京都の神護寺(じんごじ)を託されたり、空海が著した漢詩集『性霊集』(しょうりょうしゅう)を編集したりしています。
空海の十大弟子④真如
読み方は「しんにょ」。
平城天皇(へいぜいてんのう)の3番目の皇子です。
生年は799年で、没年は865年です。
嵯峨天皇の討伐を計画した藤原薬子(ふじわらのくすこ)による「薬子の変」に加担した疑いにより、真如は皇太子の位を剥奪されます。
その後、親王の位は回復したものの、そこにとどまることはなく、出家して空海の弟子となり、高野山で修行に専念しました。
実際に薬子の変に加担したのかどうかはわかりませんが、政治の世界にほとほと嫌気がさして一から出直したかったから出家したのかもしれません。
晩年は唐を経てインドをめざしましたが、その道中に消息を絶ちました。
マレー半島の南端あたりで亡くなったと言われています。
空海の十大弟子⑤実恵
読み方は「じちえ」。
生年は不明ですが、没年は847年です。
空海のあとを継いで教王護国寺(東寺)の長者(長官)になりました。
空海の第1の高弟と言われています。
第1の高弟と言われるからには、よほど優秀だったんだと思います。
実は、実恵は、空海と同じ讃岐国の佐伯氏の出身です。
東大寺で得度し、高雄山寺の空海を訪ね、弟子となりました。
空海の十大弟子⑥道雄
読み方は「どうゆう」。
生年は不明で、没年は851年です。
実恵と同じ佐伯氏の出身です。
もともと東大寺の僧侶でした。
一説には、華厳宗の正統を受け継ぎ、第7祖になったとも言われています。
その後、空海の弟子となりました。
空海の十大弟子⑦杲隣
読み方は「ごうりん」。
元の名は、高隣でした。
生年は767年で、没年は不明です。
空海よりも7歳年上ですね。
杲隣は道雄と同じく、東大寺の僧侶でした。
密教布教のため、空海は杲隣を東国へ遣わしました。
その成果として、杲隣は、寳金剛寺(神奈川県)や修禅寺(静岡県)を開創しています。
空海の十大弟子⑧円明
読み方は「えんみょう」。
生年は不明で、没年は851年です。
道雄、杲隣と同じく、東大寺の僧侶でした。
空海の弟子となってからは、神護寺定額僧(寺院の維持や法事などを担当する僧侶)21人のうちのひとりになりました(824年)。
834年3月には、空海に随伴し、比叡山西塔釈迦堂の落慶供養に列席しています。
空海の十大弟子⑨泰範
読み方は「たいはん」。
生年は778年で、没年は不明です。
泰範はもともと最澄の弟子でした。
最澄とともに空海から高雄山寺で結縁灌頂を受け、最澄の代わりに空海のもとにいましたが、そのまま空海の弟子となりました。
最澄と空海が決別した際のキーパーソンです。
泰範としては、最澄と空海が決別したのは自分のせいだと思い、自責の念に駆られたのではないでしょうか。
空海が高野山を開く際に、大いに活躍しました。
▼最澄と空海の決別について知りたい方は、こちら↓↓↓

空海の十大弟子⑩忠延
読み方は「ちゅうえん」。
生年も没年も不明です。
東大寺で具足戒を受けたのち、空海の弟子となりました。
円明と同じく、神護寺定額僧のひとりになったとも伝えられています。
忠延は、10人の弟子のなかでもっとも情報が少なく、謎が多い弟子ですね。
空海の十大弟子に多い血縁者と地縁者
空海の十大弟子をひとりひとり見てくると、親戚筋や生まれ故郷の佐伯氏出身者が複数人いることに気づきます。
これにはワケがあります。
空海が高野山を開いた当時、日本で仏教といえば奈良仏教=「南都六宗」のことでした。
つまり、力を持っていたのは南都六宗で、空海が開いた真言宗は、まだ未熟な新興勢力でした。
そのため、空海は仲間を集めるのに苦労しました。
そこで空海が頼ったのが、血縁と地縁だったのです。
空海自身の偉大さが真言宗発展の大きな原動力であったことは間違いありませんが、一方で空海は血縁者や地縁者の力を期待し、彼らはみごと真言宗の発展に大きく貢献したと言えるのでしょうね。
まとめ
- 空海の十大弟子は、生え抜きと移籍組に大別される
- 空海の十大弟子とは、智泉、真雅、真済、真如、実恵、道雄、杲隣、円明、泰範、忠延の10人
- 真言宗の勢力拡大のために空海は血縁者と地縁者に頼った
▼空海の生涯について知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海について広く知りたい方は、こちら↓↓↓