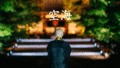【この記事でわかること】
- 空海が最澄に宛てて書いた「風信帖」の概要
- 「風信帖」の全文、訓読文、現代語訳
風信帖は空海から最澄への手紙
「風信帖」の読み方は「ふうしんじょう」です。
唐から帰国後、空海と最澄は何通もの手紙をやりとりしましたが、そのうち、空海が最澄へ宛てた3通の漢文の手紙=尺牘(せきとく)を1つの巻物にしたのが「風信帖」です。
「弘法大師筆尺牘三通」(こうぼうだいしひつせきとくさんつう)というのが正式名称です。
巻末の文章によると、もともとは5通あったが、1通は盗難のために失われ、さらに1通は関白の豊臣秀次(とよとみひでつぐ)から望まれて献上されたとのこと。
そのために3通になったそうです。
残り2通も見てみたかったですね。
なお、風信帖は東寺(教王護国寺)に保管されていて、国宝に指定されています。
さて、最澄が空海に宛てた手紙は23通残っています。
最初の手紙は、都へ戻った空海が高雄山寺(たかおさんじ)へ入ってまもなくの809年のものです。
12部53巻の書物の貸し出しを願う内容でした。
これを契機に、最澄と空海は交流するようになり、お互いに書物の貸し借りをしています。
風信帖としてまとめられた手紙が空海から最澄へ送られたのは、ちょうどこのころのようです。
最澄と空海の親密な関係が窺われる内容となっています。
ところで、風信帖がなぜ「風信帖」と呼ばれるのかというと、手紙の書き出しが「風信雲書」(ふうしんうんしょ)と、「風信」の2文字で始まっているからです。
また、3通ひとまとめで風信帖と呼ばれる一方で、2通目は「忽披帖」(こっぴじょう)、3通目は「忽恵帖」(こっけいじょう)と呼ばれることもあります。
これは、それぞれの手紙の書き出しが「忽披」「忽恵」という2文字で始まっていることから名づけられました。
以下に、風信帖(風信帖、忽披帖、忽恵帖)の全文、訓読、現代語訳を順にご紹介していきます。
なお、各手紙の末尾に日付が記されていますが、それぞれ何年の日付なのかはわかっていません。
▼最澄と空海の交流についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

風信帖の全文
風信帖(1通目)
風信雲書自天翔臨
披之閲之如掲雲霧兼
恵止観妙門頂戴供養
不知攸厝已冷伏惟
法體何如空推常擬
隨命躋攀彼嶺限以少
願不能東西今思与我金蘭
及室山集會一處量商仏
法大事因縁共建法幢報
仏恩徳望不憚煩勞蹔
降赴此院此所々望々忩々
不具 釋空状上九月十一日
東嶺金蘭 法前
謹空
忽披帖(2通目)
忽披枉書已銷陶尓
御香兩裹及左衛士
督尊書状並謹領
訖迫以法縁暫闕談
披過此法期披雲
因還信奉此不具
釋遍照状上九月十三日
忽恵帖(3通目)
忽恵書札深以慰情香
等以三日來也從三日起
首至九日一期可終
十日拂晨將參入願
留意相待是所望
山城石川兩大徳深
渇仰望申意也
仁王經等備講師將
去未還後日親將去
奉呈莫々責々也因
還人不具沙門遍照状上九月五日
止観座主 法前
謹空
風信帖の訓読
風信帖(1通目)
風信雲書、天より翔臨(しやうりん)す。
之を披(ひら)き之を閲(けみ)するに、雲霧を掲(かか)ぐるが如し。
兼ねて止観の妙門を恵まる。
頂戴供養す、厝(お)く攸(ところ)を知らず。
已(すで)に冷(ひや)やかなり。
伏して惟(おもん)みれば、法體(ほつたい)何如(いか)に。
空推(うつ)ること常なり。
命(めい)に隨(したが)ひ彼(か)の嶺(みね)に躋攀(せいはん)せんと擬(こら)すといえども、限るに少願を以てし、東西すること能(あた)はず。
今、我が金蘭及び室山と一處に集會(しふゑ)し、仏法の大事因縁を商量し、共に法幢(ほふどう)を建てて仏の恩徳に報(むく)いんと思ふ。
望むらくは、煩勞(はんろう)を憚(はばか)らず、蹔(しばら)く此の院に降赴(かうふ)せよ。
此れ望む所なり、望む所なり。
忩々(そうそう)不具 釋空状(しる)して上(たてまつ)る。
九月十一日
東嶺金蘭 法前
謹空
忽披帖(2通目)
忽ちに枉書(わうしよ)を披(ひら)き、已(はなは)だ陶尓(うれひ)を銷(け)す。
御香兩裹(りやうくわ)及び左衛士(さゑじ)の督(かみ)の尊(みこと)書状、並びに謹んで領し訖(をは)る。
迫(せま)るに法縁を以てし、暫く談披(だんぴ)を闕(か)く。
此の法(ほふ)、期を過ぐれば披雲(ひうん)せん。
還信(くわんしん)に因(よ)つて此(これ)を奉ず。
不具 釋遍照 状(しる)して上(たてまつ)る。
九月十三日
忽恵帖(3通目)
忽ちに書札(しよさつ)を恵まれ、深く以て情(こころ)を慰む。
香等は三日を以て來(きた)る也。
三日より起首(はじめ)て、九日に至りて一期終るべし。
十日の拂晨(ふつしん)に參入せんとす。
願はくは留意して相(あひ)待たれんことを。
是れ望む所なり。
山城・石川の兩大徳、深く渇仰(かつがう)して意(こころ)を申(の)べんことを望む也。
仁王經等は備講師(びかうし)將(も)ち去(ゆ)きて未だ還らず。
後日、親(みづか)ら將(も)ち去(ゆ)きて奉呈せん。
責むること莫(なか)れ、責むること莫(なか)れ。
還人(くわんじん)に因(よ)る。
不具 沙門遍照 状(しる)して上(たてまつ)る。
九月五日
止観座主 法前
謹空
風信帖の現代語訳
風信帖(1通目)
お手紙、頂戴いたしました。
拝見したところ、近況を知ることができ、雲や霧が去ったように心が晴れ晴れといたしました。
また、お手紙とともに、(天台宗の書物である)『摩訶止観』(まかしかん)をお贈りくださいましたこと、ありがたく頂戴し、供養いたします。
大変うれしく存じます。
すでに寒くなっておりますが、お体はいかがでしょうか。
わたくし空海は、あなたのお言葉に従い、比叡山に登ってお目にかかりたく存じますが、用事に追われ、お伺いすることができません。
いま思うことは、あなたと、(私の弟子である)室生寺(むろうじ)の堅慧(けんえ)と3人で集まり、仏法の重要な教義や因縁について語り合い、いっしょに寺を建立し、仏の恩徳に報いたい。
そのためにも、わずらわしいと思われることなく、私のいる高雄山寺へお越しください。
これこそ、まさしく私が望むことなのです。
9月11日
忽披帖(2通目)
ご返信いただいたお手紙を早速に拝見し、すっかり安心いたしました。
届けてくださったお香2包、そして、左衛士(さえじ)の督(かみ)でいらっしゃる藤原冬嗣様の手紙をたしかに拝受いたしました。
しかしながら、このところ、法要が迫っており、お手紙を拝見したり使いの方とお話したりする時間がありません。
この法要が済みましたら、すぐに拝見し、必ずやお返事いたします。
使者の方に託し、とり急ぎこの手紙を差し上げました。
9月13日
忽恵帖(3通目)
さっそくお手紙を頂戴し、とても安心いたしました。
お香をはじめとしたいただきものは3日にこちらへ届きました。
3日から始まった法要は9日には終わります。
つきましては、10日の早朝にこちらを出発し、あなたさまの所へお伺いいたしますので、お待ちください。
山城と石川のどちらの高僧も、あなたのことをとても慕(した)っており、お会いしてお話したいと望んでいます。
ところで、『仁王経』(にんのうぎょう)などの貸し出しをご希望されましたが、国分寺の講師が持っていったままで、まだ返ってまいりません。
後日、必ずやお貸ししたいと存じます。
どうかご容赦を。
お許しくださいませ。
帰りの使いの方にこの手紙を持たせます。
9月5日
風信帖は臨書によく使われる
空海は、嵯峨天皇、橘逸勢(たちばなのはやなり)と並び、書の達人3人という意味で、「三筆」と呼ばれています。
風信帖は、そんな空海の直筆の書なので、臨書(手本を見て書くこと)の際によく使われます。
風信帖は、空海と最澄の交流の様子を窺い知るための資料としてのみならず、書道の練習をする際のメジャーなお手本でもあるのですね。
まとめ
風信帖は、空海から最澄へ宛てた手紙のうちの3通(風信帖、忽披帖、忽恵帖)を1つの巻物にしたもの
風信帖は、空海と最澄の交流の様子を窺い知るための貴重な資料である
書道の世界において、臨書の際によく使われる
▼最澄と空海の交流についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海の数々の著作についてざっと知りたい方は、こちら↓↓↓

▼最澄と空海について広く知りたい方は、こちら↓↓↓