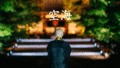【この記事でわかること】
- 『山家学生式』はいつ何のために書かれたのか
- 『山家学生式』はどのような状況のもとで書かれたのか
- 『山家学生式』と『顕戒論』の違い
- 『山家学生式』はどのような内容か
『山家学生式』はいつ何のために書かれた?
唐へ渡り、法華経を中心とする天台の教えを学んで帰国した最澄は、翌年の806年に桓武天皇から天台宗を開く許しを与えられました。
その最澄の悲願は、比叡山で大乗仏教にもとづく学問僧を養成し、独自の戒壇(かいだん:僧侶になる者に戒律を授ける儀式を行う場所)を設けることでした。
そのため最澄は、朝廷へ戒壇設立の勅許を願い出ます。
具体的には、818年5月に『天台法華宗年分学生式一首(六条式)』(てんだいほっけしゅうねんぶんがくしょうしきいっしゅ)、同年8月に『勧奨(かんしょう)天台宗年分学生式(八条式)』、翌819年3月には『天台法華宗年分度者回小向大式(四条式)』(てんだいほっけしゅうねんぶんどしゃえしょうこうだいえ)を奏上したのです。
これらを総称したのが、『山家学生式』(さんげがくしょうしき)です。
つまり、最澄は、818年〜819年にかけて、比叡山に大乗戒壇を設ける目的で『山家学生式』を書いたのです。
ちなみに、「山家」とは天台宗のこと。
「式」というのは、律令の施行細則。
「年分」「年分度者」というのは朝廷が認める官費支給の僧侶のことです。
『山家学生式』が書かれた時代背景とは?
最澄が天台宗を開いたころ、戒壇があるのは「日本三戒壇」、すなわち、奈良の東大寺、下野(しもつけ:現在の栃木県)の薬師寺、筑紫(つくし:現在の福岡県)の観世音寺(かんぜおんじ)の3箇所のみで、それらの戒壇で授戒されるのは上座部仏教の戒律でした。
これに対して最澄が構想したのは、〝すべての人が必ず仏になれる〟という法華経の一乗思想にもとづき、『梵網経』(ぼんもうきょう)に書かれた「十重四十八軽戒」という、従来の戒律よりも簡潔な戒を授ける戒壇を比叡山に設けることでした。
なぜ最澄は、独自の戒壇の設立にこだわったのでしょうか?
従来のやり方だと、自分の弟子をとろうとしても必ず、朝廷が定めた3つの戒壇のどこかで授戒しなければなりませんでした。
しかし、これらの戒壇は、奈良仏教の1つで、〝仏になる道は3つある〟とする三乗思想を説く法相宗(ほっそうしゅう)が仕切っていました。
つまり、受戒するには、天台宗が説く一乗思想ではなく三乗思想を学ばなければならなかったのです。
これは、たとえが適切ではないかもしれませんが、自由主義思想家を育てるのに、いったん社会主義思想を身につけさせなければならないようなものでしょうか。
そうなると、自由主義思想家になるつもりが、社会主義思想家になってしまうリスクがあります。
実際、最澄が期待していた弟子のなかには、奈良仏教にすっかり傾倒し、最澄の元に戻ってこなかった者がいたようです。
自分が手塩にかけて育てた弟子が、他のところへ去ってしまうなんてやりきれないですよね。
こうしたことから最澄は、独自の大乗戒壇を設立する必要性を痛感し、『山家学生式』を上奏したのです。
『山家学生式』と『顕戒論』の違い
『山家学生式』による最澄の戒壇設立の願いに対し、奈良仏教側は猛反対しました。
そして、最澄の願いが実現しないよう、朝廷に圧力をかけてきました。
これに対して、最澄は『顕戒論』(けんかいろん)を著し、大乗戒壇を設立する正当性を訴えました。
『山家学生式』と『顕戒論』の違いに関する問いをネットで見かけますが、両著は明らかに違います。
『山家学生式』は天台宗の僧侶育成のための規則をまとめたもので、一方の「顕戒論」は比叡山に大乗戒壇を設置することに反対する奈良仏教への反論の書です。
ちなみに、比叡山に大乗戒壇を設立する許可が朝廷から下りたのは、最澄の死の直後です。
ひょっとしたら、最澄は死の直前、設立許可の件を密かに知らされ、悲願が達せられたと安心したために息を引き取ったのかもしれませんね。
▼最澄の生涯について知りたい方は、こちら↓↓↓

『山家学生式』の内容
『山家学生式』には、次のような有名なくだりがあります——
国宝とは何物ぞ。
宝とは道心なり。
道心あるの人を名づけて国宝となす。
故に古人いわく、
「径寸十枚、これ国宝に非ず。照千一隅、これ則ち国宝なり」と。
| 【現代語訳】 国の宝とは何か。 宝とは、仏の道を求める心である。 仏の道を求める心を持つ人のことを国の宝というのである。 だから、昔の人はこう言っている、 「直径が1寸(約3cm)ある宝石が10個あっても、それは国の宝ではない。 国のなかの一隅を照らすこと、それこそが国の宝なのだ」と。 |
要は、国の宝とは金銀財宝などのことではなく、世の中の一隅(自分のいる場所や環境)でまじめに努力し、周囲をよくする人のことなのだ、ということです。
当たり前のようなことですが、とても大切な意識ですね^^
『山家学生式』は大乗戒壇の開設を願い出る、いわば申請書のような書物ですが、この一節を読んだだけでも、お役所に提出するような申請書のレベルを超え、国を救う人材を養成しようという最澄の熱意をじかに感じられます。
また、ここに記されている「照千一隅」は、「一隅を照らす運動」として、今も天台宗の主要な活動でありつづけています。
まとめ
- 最澄は、818年〜819年にかけて、比叡山に大乗戒壇を設けるために『山家学生式』を書いた
- 当時の戒壇は三乗思想を説く法相宗(奈良仏教)が仕切っていたため、最澄は大乗戒壇の開設が必要だと考えた
- 『山家学生式』は天台宗の僧侶育成のための規則集で、「顕戒論」は大乗戒壇に反対する奈良仏教への反論の書
- 『山家学生式』には、国を救う人材を養成しようという最澄の熱意が込められている
▼最澄の生涯をくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

▼最澄について広く知りたい方は、こちら↓↓↓