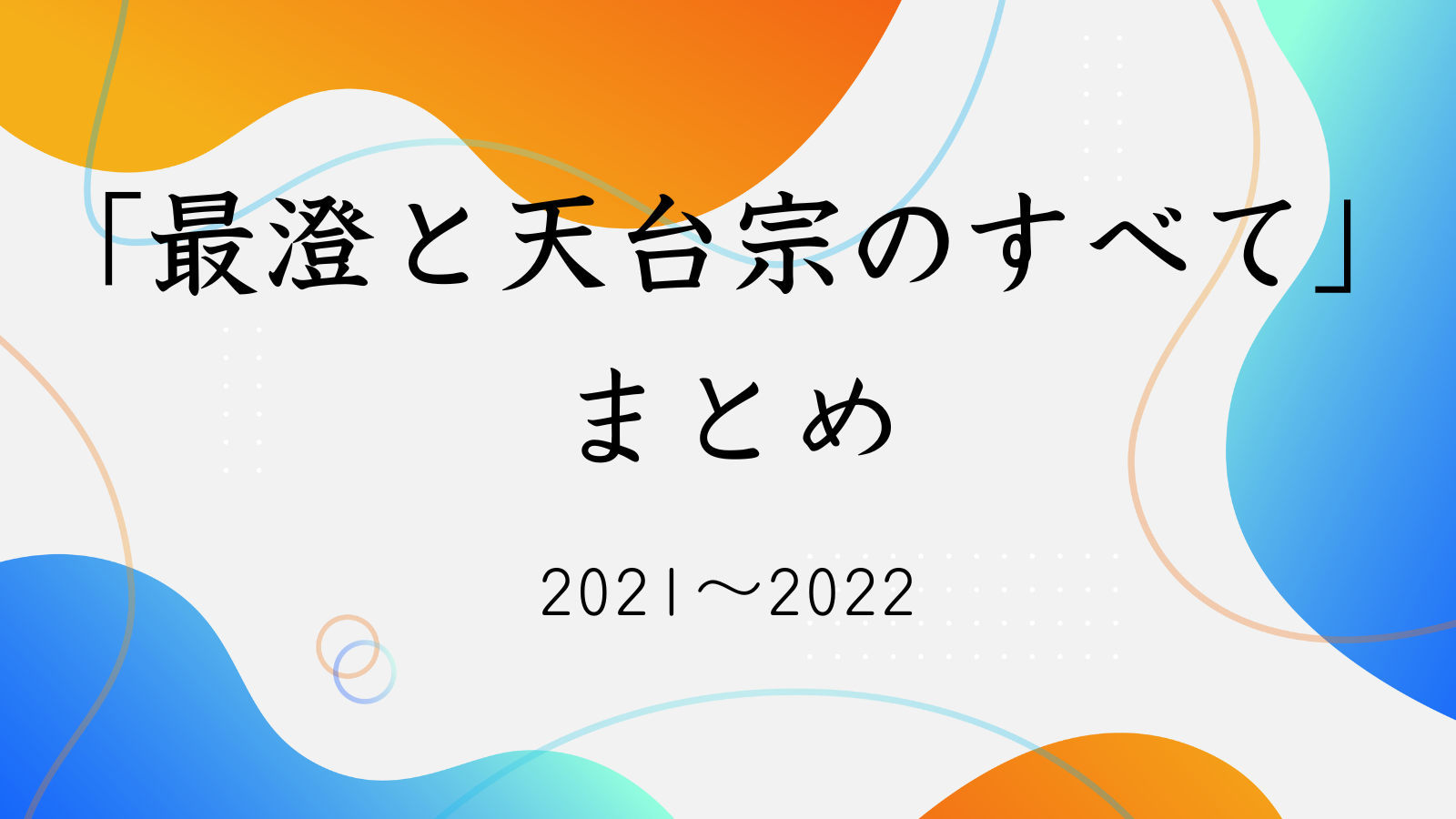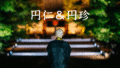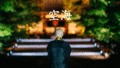【この記事でわかること】
「最澄と天台宗のすべて」展とは?
2021年は、日本天台宗を開いた最澄が821年に亡くなってから、ちょうど1200年目でした。
これを記念して、2021年から2022年にかけ、「伝教大師1200年大遠忌記念 特別展『最澄と天台宗のすべて』」が開催されました。
私は、行きたかったけれども行けませんでした~(涙)
開催場所は、東京国立博物館、九州国立博物館、京都国立博物館の3館(巡回開催)。
開催期間は、東京国立博物館が2021年10月12日(火) ~ 2021年11月21日(日)、九州国立博物館が2022年2月8日(火)~3月21日(月・祝)、京都国立博物館が2022年4月12日(火)~5月22日(日)でした。
展示は6章構成で、比叡山延暦寺における日本天台宗の開宗から、「東の比叡山」と呼ばれた東京・上野の寛永寺が創建された江戸時代へいたる、天台宗の歴史が紹介されました。
具体的には、延暦寺をはじめ、天台宗の諸寺院等が所蔵する国宝と重要文化財を含む貴重な寺宝が展示されました。
会場ごとに一部展示品の入れ替えがありましたが、ここでは東京国立博物館の展示に即して、その内容をご紹介します。
ちなみに、東京国立博物館では、「最澄と天台宗のすべて」展開催に合わせ、「浅草寺のみほとけ」展が開かれ、天台宗の古刹として知られた浅草寺に伝わる仏像17体が展示されました。
見たかった~(涙)
最澄と天台宗のすべて:第1章 最澄と天台宗の始まり――祖師ゆかりの名宝
最澄は、鑑真が日本へもたらした経典から中国天台宗・智顗(ちぎ:538~597)の教えを学びます。
智顗の教えは、法華経を根本経典としていました。
最澄は、遣唐使として唐へ渡り、天台の教えを修得して帰国します。
そして、比叡山を日本天台宗の拠点とし、従来の南都六宗とは異なる大乗仏教としての活動を行います。
第1章では、こうした最澄の歩みが紹介されました。
主な展示品は――
薬師如来立像
平安時代に造像された法界寺(京都市)に安置される薬師如来立像です。
秘仏で、寺外初公開です。
比叡山延暦寺の根本中堂には最澄作の薬師如来立像があり、やはり秘仏とされていますが、その像を模したと考えられています。
秘仏が見られるなんて、めったにないことなので、貴重な展示だったはずです。
聖徳太子及び天台高僧像
「聖徳太子及び天台高僧像」は、インド、中国、日本の天台宗にゆかりがある高僧たちを描いた肖像画です。
国宝です。
期間によって展示品の入れ替えがありましたが、全期間展示されたのは慧文(えもん)、灌頂(かんじょう)、10月12日(火)~11月7日(日)の期間で展示されたのは最澄、円仁(えんにん)、龍樹(りゅうじゅ)、善無畏(ぜんむい)、11月2日(火)~11月21日(日)の期間展示されたのは智顗、慧思(えし)、湛然(たんねん)、聖徳太子でした。
10人分すべてが展示されたのは、11月2日から7日にかけての6日間。
さぞや壮観だったことでしょう。
なお、最澄の肖像画は、最澄を描いた絵画としては現存最古です。
光定戒牒
「光定戒牒」(こうじょうかいちょう)とは、最澄の弟子・光定に交付された、受戒を示す証明書(戒牒)です。
国宝です。
最澄の死後7日目、比叡山が独自に大乗菩薩戒を授けることが朝廷から許可されました。
その設立に力を尽くしたのが光定で、当該展示品は最初の授戒が行われたときの戒牒です。
書いたのは「三筆」の1人・嵯峨天皇。
気品と力強さを併せ持つ字が連なっているとの評価です。
▼最澄の生涯について知りたい方は、こちら↓↓↓

最澄と天台宗のすべて:第2章 教えのつらなり――最澄の弟子たち
最澄亡きあと、後継者たちが天台宗の基盤を築いていきました。
最澄が望んだ天台宗における密教の本格化を果たすべく唐へ渡った円仁と円珍。
それを受けて、台密を完成させた安然。
比叡山の山中を駆けめぐる回峰行(かいほうぎょう)を創始した相応(そうおう:831~918)。
こうした後継者たちによって、天台宗は発展していきました。
第2章では、その発展の歴史が紹介されました。
主な展示品は――
木造 不動明王坐像
平安時代中期の作品で、回峰行の創始者・相応が建立したと言われる伊崎寺(滋賀県)の本尊です。
相応が滝行中に不動明王を感得したと思い、抱きつくと、それは葛(かつら)の木でした。
不動明王に抱きつこうなんて、いい度胸してます(笑)
相応は、葛の木を3つに分け、3体の不動明王を造像。
葛川明王院、比叡山無動寺、伊崎寺で祀りました。
2006年に国の重要文化財の指定を受け、現在は比叡山延暦寺の國寳殿に収蔵されています。
▼円仁と円珍について知りたい方は、こちら↓↓↓

最澄と天台宗のすべて:第3章 全国への広まり――各地に伝わる天台の至宝
「誰もが仏になれる」という天台の教えは、天台宗が日本全国へ広まる大きな原動力となりました。
そして、広まった先で土着の信仰に取り込まれ、現在へいたっています。
第3章では、その様子が紹介されました。
主な展示品は――
薬師如来坐像
岐阜県可児郡御嵩町にある願興寺(蟹薬師)の本尊で、重要文化財です。
子年(ねずみどし)の4月の第1日曜日にだけ開扉される秘仏です。
寺外初公開です。
秘仏で寺外初公開とは、とても貴重な展示ですね。
この薬師如来坐像は、最澄が東国布教へ向かう際、疫病に苦しむ人びとが多いことを憐み、施薬院として建立し、そこに安置したのが始まりです。
最澄と天台宗のすべて:第4章 信仰の高まり――天台美術の精華
比叡山は10世紀に入ると、数度の火災によって多くの堂が焼失し、荒廃していきました。
これに対し、55歳で18代天台座主(てんだいざす:延暦寺のトップ)になった良源(りょうげん:912~985)は、藤原氏の財力を背景に、荒れていた比叡山の伽藍を整備し、天台宗に最盛期をもたらしました。
その後、弟子の源信(げんしん:942~1017)は、末法思想の流行で不安に駆られた人びとに向けて『往生要集』を著します。
この著作によって、源信は貴族社会にも大きな影響を与え、その名が広く知られるところとなります。
また、念仏運動を展開して、下級貴族や庶民にいたるまで、幅広い層に広がっていきました。
第4章では、貴族の浄土信仰と結びついた寺宝が紹介されました。
主な展示品は――
阿弥陀如来立像
京都市左京区の真正極楽寺(真如堂)の本尊で、重要文化財です。
毎年11月15日にだけ開扉される秘仏です。
平安初期に円仁が彫ったと伝えられ、女人を救う仏で、「うなずきの弥陀」という別称で庶民に親しまれています。
3体めの秘仏ですね。
こんなこと、めったにないと思います。
最澄と天台宗のすべて:第5章 教学の深まり――天台思想が生んだ多様な文化
発展した天台宗は、さまざまな宗教者や信仰を生みました。
まず、比叡山延暦寺で学んだ僧から、法然(ほうねん:1133~1212)、親鸞(しんらん:1173~1263)、道元(どうげん:1200~1253)、日蓮(にちれん:1222~1282)など、鎌倉新仏教の祖師たちが誕生しました。
また、比叡山延暦寺で20年以上学んだ真盛(しんせい:1443~1495)は、源信の『往生要集』による称名念仏と戒律の一致を唱え、天台真盛宗の祖となりました。
一方、平安時代後期、神道における神々は、実は仏や菩薩が姿を変えて現れた=「垂迹」(すいじゃく)したものだという神仏習合思想が起こりました。
この思想は鎌倉時代になると、天台宗において、比叡山の鎮守社である日吉神社=「山王」(さんのう)の神は釈迦如来が垂迹したものだとして、日吉神社への信仰が高まり、「山王神道」、別名「天台神道」として成立しました。
第5章では、このような中世天台宗の多様性の紹介として、日吉山王曼荼羅や山王霊験記絵巻などが展示されました。
最澄と天台宗のすべて:第6章 現代へのつながり――江戸時代の天台宗
1571年、織田信長は比叡山を焼き討ちにします。
浅井氏と朝倉氏をかくまったことへの報復でした。
その結果、僧侶をはじめ数千人もの人びとが犠牲となりました。
その後、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗の援助を受け、比叡山は復興していきます。
この復興にあたって重要な役割を果たしたのが慈眼(じげん)大師こと天海(てんかい:1536~1643)です。
1642年、徳川家光のころには、根本中堂が再建されています。
一方で、天海は、徳川家康に仕え、江戸に寛永寺(かんえいじ)を創建しました。
比叡山延暦寺が京都御所の鬼門に位置し、朝廷の平和を祈る役割を果たしていたように、寛永寺は江戸城の鬼門にあたる上野に建てられ、江戸幕府の安泰を祈る役割を期待されました。
そのため、寛永寺は「東の比叡山」と呼ばれました。
第6章では、こうした江戸時代の天台宗を物語る品が展示されました。
主な展示品は――
慈眼大師縁起絵巻(中巻)
寛永寺を建立した天海の生涯を描いた絵巻物です。
比叡山中興の祖とされる良源(りょうげん)=元三大師(がんざんだいし)の生涯を描いた元三大師縁起絵巻とともに、両大師縁起として、住吉具慶(すみよしぐけい:1631~1705)によって描かれました。
公刊は、1680年ごろです。
なお、絵巻のなかに記されている詞書は、天海の弟子・胤海(いんかい)によるものです。
この絵巻は、当時の寛永寺や上野の山の様子を知るうえで、とても貴重な資料です。
なお、展示期間は、10月26日(火)~11月7日(日)に限定されていました。
慈眼大師(天海)坐像
近年の修理で、像内から墨書が見つかり、七条大仏師(慶派)の康音(こうおん)が1640年、天海の生前に造像したことがわかりました。
表情には気迫があり、存在感がある造形だと評されています。
2009年7月10日に重要文化財に指定されました。
▼最澄について広く知りたい方は、こちら↓↓↓