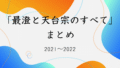【この記事でわかること】
- 最澄が開いた天台宗の草創期に活躍した円仁と円珍がそれぞれどのような僧侶だったのかということ
- 試験に臨むにあたって、円仁と円珍について覚えておくべきこと
- 円仁が開いた山門派と円珍が開いた寺門派の対立のワケ
円仁とは?
円仁(えんにん:794〜864)は、最澄のあとを継いで、経済的に逼迫(ひっぱく)していた比叡山(天台宗)をV字回復させた第一人者です。
この人がいなかったら、今の天台宗はなかったかもしれないとも言える重要人物です。
その円仁は、23歳で東大寺で具足戒を受け、最澄とともに東国を巡行しています。
また、最澄は天台宗の中心的な修行法である止観(しかん)を10人の弟子に学ばせていますが、最澄に代わって止観の指導を任せられたのは円仁ひとりでした。
つまり、円仁は最澄の一番弟子だったわけです。
かなり信頼されていたのだと思います。
さて、最澄は、当時の朝廷や貴族の人気が高かった密教の導入において、すっかり空海に遅れをとり、みずからが開いた天台宗に密教を本格的に導入することを悲願としながら、それを果たせず亡くなりました。
さぞや無念だったことでしょう。

円仁は838年、42歳のとき、その最澄の遺志を受け継ぎ、9年半という長期間にわたって唐へ留学し、天台教学と密教を体系的に学びます。
密教に関しては、空海以後の最新の密教も学んでいます。
そして、847年、円仁は経書559巻や金剛界曼荼羅など、空海をしのぐほどの文物を携えて帰国します。
この円仁の成果により、比叡山は密教の導入において、空海が開いた真言宗をしのぐ力をつけ、皇族や貴族からの人気が一気に高まりました。
それに伴い、比叡山は経済的なピンチを乗り越え、繁栄することになったのです。
円仁にしてみれば、「お師匠さん、やったよー!」と歓喜したい心境だったことでしょう。
一方で、円仁は、帰国した翌年、常行三昧堂(じょうぎょうざんまいどう)を建立し、弟子たちに伝授しました。
常行三昧とは、天台智顗(てんだいちぎ)がまとめた行法「四種三昧」(ししゅざんまい)の一種です。
一定の期間、不眠不休で飲食せず、口では阿弥陀如来の名を唱え、心には阿弥陀如来の姿を思い描きながら阿弥陀如来像の周囲を右回りで回りつづけていると、ついには阿弥陀如来が目の前に現れると言われています。
聞くだけでめまいがしそうな過酷な修行です。
その常行三昧をもっぱら専修するのが常行三昧堂で、比叡山では今でも行われています。
こうして円仁は、日本浄土教発展の基礎を築いたのでした。
その功績により、円仁は死後、慈覚大師(じかくだいし)の名を贈られています。
なお、円仁が唐へ留学中に書いた『入唐求法巡礼行記』(にっとうぐほうじゅんれいこうき)は、当時の唐の様子を知るうえで貴重な史料となっています。
円珍とは?
円仁が唐から比叡山へ戻ってきたころに名声を高めていたのが円珍(えんちん:814〜891)です。
最澄の弟子・義真(ぎしん)の弟子にあたります。
円珍は、空海と同じ讃岐国の出身で、空海の甥(おい)もしくは姪(めい)の息子に当たるとも言われています。
親戚なら、顔も空海に似ているところがあったのでしょうか?
円珍も円仁と同じく唐へ渡りました。
853年のことです。
そして、天台山の数々の寺院や、空海が学んだ青龍寺という密教寺院を訪れ、約1000巻もの経典を携え、5年後の858年に帰国します。
翌年の859年には朝廷から賜った三井(みい:現・滋賀県大津市)の園城寺(おんじょうじ)へ入り、延暦寺の別院としました。
円珍がもっとも注力したのは、円仁が進めた天台宗の密教化をさらに推し進め、従来の天台宗の教義と密教を理論的に統合することでした。
円珍は藤原氏や清和天皇などから重用され、のちに智証大師(ちしょうだいし)という名を贈られています。
円仁も円珍もともに「○○大師」という諡(おくりな)を贈られるとは、よほど朝廷に貢献したのでしょうね。
円仁と円珍の覚え方
試験で問われることが多いのは、最澄が開いた天台宗において、円仁と円珍がそれぞれ何という門派を開き、何という寺院を拠点としたかについてです。
| 円仁 | 山門派 | 延暦寺 |
| 円珍 | 寺門派 | 園城寺(三井寺) |
ちなみに、延暦寺は比叡山の上にあるので山門派と呼ばれ、園城寺(三井寺)は比叡山の南麓に位置しています。
また、園城寺の正式名称は「長等山(ながらさん)園城寺」で、一般には「三井寺」(みいでら)と呼ばれています。
延暦寺の山門は2円です
実際に、延暦寺の山門が2円で買えるわけではありません。
〝延暦寺を拠点に山門派を開いたのは円仁〟という意味です。
「2円」(にえん)は円仁(えんにん)を倒置しています。
覚えるべきは、円仁/円珍、山門派/寺門派、延暦寺/園城寺(三井寺)なので、あとは消去法で、円珍—寺門派—園城寺(三井寺)という組み合わせだとわかります。
園児のme(ミイ)はエッチ自慢
「園児」は園城寺の園と寺(じ)=児(じ)、「me」(ミイ)は三井寺(みいでら)のミイ、「エッチ」は円珍(えんちん)のエとチ、「自慢」(じまん)は寺門派(じもんは)の〝じ〟と〝ん〟に、それぞれもとづいています。
この文章の意味するところは、各自創作してください(笑)
山門派(円仁派)と寺門派(円珍派)の対立
円仁と円珍亡きあと、天台宗は円仁派=山門派と円珍派=寺門派に分かれ、ついには対立するようになります。
その対立点は、密教に対する考え方の違いでした。
すでに述べたように、最澄が不充分にしか学べなかった密教を充分な形で天台宗に取り入れるため、円仁も円珍も唐へ渡り、密教を学びました。
そして、円仁も円珍も、「円密一致」(えんみついっち:法華経を中心とする中国天台宗の教え=円教と密教を融合させる考え)の立場から、密教を天台宗のなかへ組み込み、円仁の弟子・安然(あんねん:841~?)のときに「台密」が完成しました。
しかし、平安時代後期になると、その密教の位置づけが、山門派と寺門派では異なっていきました。
最澄が開いた天台宗においてもっとも重視されたのは、法華経です。
山門派は、この法華経の教え(誰もがみな仏になれる)と密教の教えは同じ価値があると考えました。
一方の寺門派は、法華経と密教は同じ教えを説いてはいるが、密教のほうが優位であると考えました。
この考え方の違いの他に、天台宗内の権力争いが加わり、山門派と寺門派の対立は激化していきます。
そしてついには、お互いの僧兵がぶつかり合うという流血の事態に発展したのでした。
天台宗は悲惨な状況を経験しているのですね。
まとめ
- 円仁は最澄の一番弟子で、唐で最新の密教を学ぶ
- 円珍も唐で密教を学び、天台宗の教義と密教の理論的な統合に努めた
- 円仁と円珍の覚え方としては、「延暦寺の山門は2円です」「園児のme(ミイ)はエッチ自慢」がある
- 平安時代後期には円仁の系統の山門派と円珍の系統の寺門派が激しく対立・衝突した
▼最澄について広く知りたい方は、こちら↓↓↓