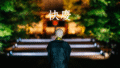湛慶は、運慶や快慶ほどに有名ではありません。
だから、湛慶のことはよく知らないという人は多いでしょう。
たとえば、「湛慶の父親は?」と訊かれて、すぐに答えられる人は、そう多くはないかもしれません。
そこで、ここでは他にも、湛慶の代表作や、三十三間堂の千手観音像についても、わかりやすく解説していきます^^
湛慶の父は誰?
鎌倉時代初期に活躍した仏師である運慶と快慶の名前が挙がるとき、よくいっしょに見かける名前が湛慶(たんけい:1173-1256)です。
湛慶も、運慶や快慶と同じ仏師のグループ=「慶派」に属していました。
すでに他の記事でご紹介しているように、運慶と快慶のあいだには血のつながりはいっさいないので、2人は親子や家族、親戚ではなく、兄弟弟子という間柄でした。
それでは、湛慶の場合はどうでしょうか?
運慶や湛慶とどのような関係なのでしょうか?
実は、湛慶の父親は、運慶なのです。
運慶には6人の子どもがいます。
湛慶、康運(こううん)、康弁(こうべん)、康勝(こうしょう)、運賀(うんが)、運助(うんじょ)です。
この6人が6人とも仏師になりました!
今の時代、6人もの子どもがいれば、そのうちの何人かは父親とは別の職業につくことが多いものです。
しかし、運慶の子どもたちはみな父親と同じ職業に就きました。
そういう時代だったのかもしれませんが、湛慶はじめ6人の子どもたちにとって、父・運慶はスーパーマンのような憧れの存在だったとも言えるのではないでしょうか。
結果、湛慶は、運慶、快慶と並び称されるほどの仏師になっています。
なお、湛慶の仏像の作風は、父・運慶の仏像に見られる豪快さはないものの、運慶の完成された作風にもとづく洗練された温和な表現が特徴となっています。
▼湛慶の父・運慶について知りたい方は、こちら↓↓↓

▼湛慶が属した慶派について知りたい方は、こちら↓↓↓

湛慶の代表作は?
湛慶は、約60年にもわたり、仏像をつくりつづけました。
その長きにわたる期間は、およそ3つの時期に分けられます。
第1期は、1223年に父・運慶が亡くなるころまでで、東大寺がある奈良で活躍し、その後の自身の作風を培いました。
第1期の代表作としては、快慶とともに制作した醍醐寺閻魔堂の司命・司録像や、地蔵十輪院の増長天像が挙げられます。
次の第2期は、1248年ころまでで、湛慶は奈良を離れ、独自の作風を築き上げました。
第2期の代表作としては、雪蹊寺の善膩師童子像や、高山寺の狛犬像、仔犬像が挙げられます。
最後の第3期は、湛慶が生涯を閉じる1256年までです。
湛慶は、東大寺講堂の千手観音像を制作している途中で亡くなりました。
この時期の代表作は、京都の蓮華王院本堂、いわゆる「三十三間堂」の復興のときに制作した、三十三間堂の中央に坐す像高355cmの「千手観音坐像」(1251年)、そして、この坐像の左右に安置された千手観音立像1000体のうちの9体になります。
そのどれもが国宝に指定されています。
国宝に指定されるだけでもすごいことなのに、10体もの仏像が国宝に指定されるなんて〝超〟すごいですね!
湛慶がつくった三十三間堂の千手観音はどんな仏像?
湛慶の代表作中の代表作といえば、京都・三十三間堂の千手観音像10体、なかでも千手観音坐像でしょう。
まず三十三間堂ですが、長さが約120mもある細長い建築物で、正面の東側の柱が34本あり、その柱と柱の間の間隔が33あることから、「三十三間堂」と呼ばれています。
そして、その堂内には、1001体の千手観音像が整然と並ぶように安置されています。
千手観音とは、正しくは「千手千眼観自在菩薩」といい、千の手と千の目を持つ菩薩(ぼさつ)です。
仏教における「千」は「無限」を意味していて、千手観音は無限の功徳と術をもって衆生を救うという仏の姿を表しているのです。
さて、1001体もの千手観音像が並んでいるありさまは、世界に1つしかない特別な光景です!
120mの細長い堂内のど真ん中に、台座と光背を含めると7mもの高さになる千手観音坐像が鎮座し、その左右両脇には500体ずつ合計1000体の千手観音立像が立ち並んでいます。
しかも、それらの仏像はみな金色に輝いていて、その壮観な光景は見る者を完全に圧倒します。
私も三十三間堂を何度か拝観したことがありますが、その美しさに言葉を失った経験があります。
また、1001体の千手観音像の周囲には、観音たちを守るように、仏法の守護神である「二十八部衆」等が31体まつられています。
つまり、三十三間堂のなかには、1032体の仏像があるのです。
そのなかでもっとも存在感を放っているのが、湛慶が制作した巨大な千手観音坐像なのです。
この千手観音坐像は、父・運慶のような力強さはないものの、写実的で洗練された湛慶の非凡な手腕が如実に表現されていると評価されています。
なお、湛慶は、この中央に鎮座する千手観音坐像と、千手観音立像9体を制作するにあたり、自身がリーダーを務めていた「慶派」一門だけでなく、京都の「院派」(いんぱ)「円派」(えんぱ)といった他の仏師のグループにも援助を求めました。
なぜ湛慶は、他の仏師のグループに助けを求めてまで、千手観音像の制作に心血を注いだのでしょうか?
慶派は、その源流にあたる、平安時代後期を生きた仏師・康助のときから蓮華王院の大仏師を努めていましたが、推測するに、そのリーダーとしてのプライドと責任感が、湛慶にそこまでさせたのかもしれませんね。
まとめ
- 湛慶の父親は運慶
- 湛慶のいちばんの代表作は京都・三十三間堂の千手観音坐像
- 千手観音(千手千眼観自在菩薩)は衆生救済のために千の手と千の目を持つ