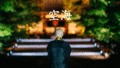平安時代に真言宗を開き、日本仏教の礎(いしずえ)を築いた弘法大師・空海。
約1200年前の人物でありながら、空海の言葉は色褪せることなく、現代を生きる私たちの心にも深く響きます。
生き方や悩み、将来への不安……
私たちが抱えるどんな問題にも、空海は明確な答えを与えてくれます。
この記事では、あなたの人生の指針となるような空海の名言を11個選んでみました。
さあ、あなたの心を揺さぶる言葉に出逢いにいきましょう!
空海の名言①すべてに感謝せよ
一切の男子(なんし)はこれわが父なり、
一切の女人(にょにん)はこれわが母なり。
一切の衆生(しゅじょう)は皆これわが二親(にしん)、師君(しくん)なり
『教王経開題』(きょうおうきょうかいだい)より
| 【現代語訳】 すべての男性は私の父であり、 すべての女性は私の母である。 生きとし生けるものはみな 私の両親、そして先生なのだ。 |
〝人は自分ひとりでは生きられない〟というニュアンスが伝わってきますね。
だから、〝自分を支えてくれているものすべてに感謝しなさい〟というメッセージが込められた言葉なのだと思います。
仏教には「四恩」(しおん)という考え方があります。
人がこの世において受ける4つの恩のことです。
父母の恩、衆生の恩、国王の恩、三宝(さんぽう:仏、法、僧)の恩です。
父母の恩とは〝自分を生み育ててくれた恩〟です。
両親がいなければ自分はここにいなかったのであり、自分を育てるために多大な労力と時間を費やしてくれたことに思いをいたせ、ということでしょうね。
衆生の恩とは〝他者からの恩〟です。
自分を助け、支え、励ましてくれる周囲の人びとのことを常に思え、ということだと思います。
国王の恩とは〝為政者への恩〟です。
衣食住や社会的安定の提供など、人びとが安心して暮らせる環境を保ってくれている為政者へ感謝せよ、という意味だと思います。
空海は天皇のことをイメージしていたのでしょうか。
ひるがえって現代は、自分たちの利益や保身ばかりを考える為政者がいて、空海の言葉のようには感謝できないのが現状ではないでしょうか。
三宝の恩とは〝仏・法・僧〟への恩です。
仏そのもの、仏の教え、教えを伝える僧に感謝することが大切だという意味のようです。
また、それだけにとどまらず、仏の道を実践しなさいというメッセージも込められていると思います。
空海の名言②前向きで明るい心が大切
心暗きときは、
すなわち遭(あ)うところことごとく禍(わざわい)なり
眼(まなこ)明らかなれば
途(みち)に触れて皆宝なり
『性霊集』(しょうりょうしゅう)より
| 【現代語訳】 自分の心が暗く曇っているときは、 よくない不幸なことばかりに遭遇してしまうものだ。 でも、心が明るくなれば、 どんなことにでも幸せを見出すことができるだろう。 |
私たちは、自分にとって都合が悪いことや悲しいできごとなどがあると、心が暗くなり曇ってしまいます。
そして、その状態が積み重なれば、電車に1本乗り遅れただけで、〈ツイてないな〉と毒づいてしまい、ますます心は暗く曇るばかりです。
一方、よいことがあれば心は晴れ、急ぎのときに赤信号で足止めされても、〈ちょっと小休止〉と前向きに受け止められます。
であれば、心が暗く曇っているときは、その心のレンズの曇りを拭いてあげればいい。
そうすれば物事がよく見え、心も前向きに明るくなってきます。
わかっちゃいるけど、なかなかできないことですが、それでもやっぱり大切なことだと思います。
私も毎日、心がけていきたい言葉ですね^^
空海の名言③行動による自己変革
春の種を下(くだ)さずんば、
秋の実(みのり)いかに獲(え)ん
『秘蔵宝鑰』(ひぞうほうやく)より
| 【現代語訳】 春に種をまかずして、 どうやって秋に実りを収穫することができるだろうか。 |
仏教では、「因果応報」(いんがおうほう)を説きます。
「因果応報」とは、〝原因は結果を生み、その報い(応報)は必ずもたらされる〟という考え方です。
あなたは善い結果が得られないとき、どう思いますか?
〝運がない〟〝才能がない〟と思うでしょうか?
でも、空海は、どんな人でも善い努力という「種」をまけば、善い縁に恵まれると言っているのです。
たしかに、運や才能のせいにするのは、〝自分は何も努力したくありません〟と公言しているようなものですよね。
そうではなく、正しい努力=「精進」(しょうじん)を積み重ねていけば、おのずと善い縁に恵まれ、善い結果(実り)を得られるようになるのです。
一見、この空海の言葉は凡庸に聞こえますが、基本的なことだからこそ、とても意味が重いのだと思います。
空海の名言④大事なのは行動
言って行わずんば、
何ぞ猩猩(しょうじょう)に異ならん
『秘蔵宝鑰』より
| 【現代語訳】 口先ばかりで何も行わないのは、 猩猩とどこも違わない。 |
「猩猩」(しょうじょう)というのは、中国の古典に記された想像上の動物のことで、赤い毛並みと赤い顔の猿に似た生きものです。
批判的な言葉だとすぐにわかりますね。
なぜ空海は、こんな言葉を遺したのでしょうか。
それは、あるとき儒教者に「僧侶は出家して働かない。国のために役立ってもいない」とけなされたからでした。
これに対して、空海は、「儒教者こそ、道徳心は説くものの何もせず、口先ばかりじゃないか」と反論しました。
実際に空海は、真言宗の布教に精力を傾けていただけでなく、満濃池(まんのういけ)というため池の修復や、綜藝種智院という庶民のための学校をつくるなど、いろいろな事業を行なっていました。
それなのに、役立たずと言われた空海はよほど悔しかったのか、上記のような言葉を遺したのでした。
ちょっと人間くさい感じがするように私には思えました。
▼空海の生涯について知りたい方は、こちら↓↓↓

空海の名言⑤学びの大切さ
物の興廃(こうはい)は必ず人に由る。
人の昇沈(しょうちん)は定(さだ)んで道に在(あ)り
『続性霊集』(ぞくしょうりょうしゅう)より
| 【現代語訳】 ものごとが盛んになるか滅びるかは、 必ずそれに関わっている人に影響される。 また、人が社会で成功したり失敗したりするのは、 決まってその人が何を学び、 どう生きてきたかに関係している。 |
行動を重視する空海の考え方がはっきりと表れていますね。
空海は綜藝種智院(しゅげいしゅちいん)を開いたとき、ある人物から「貴族でもない人間のための学校など長続きしない」と言われました。
上記の言葉は、その批判に対する空海の応答です。
空海の真言密教では、誰でも仏になることができると考えられており、それに貴族や庶民などの身分は関係ありません。
つまり、才能があれば、どんな身分の人間であっても、努力すれば、それを開花させることができるわけです。
しかし、そのためには、誰もが平等に学べる環境が必要になります。
また、空海は、仏教だけでなく儒教や道教など他のさまざまな学問を総合的に学ぶことが大切だと考えていました。
そうした環境を提供するのが、綜藝種智院だったのです。
空海って先進的な人だったんだなあって私は思いました。
ちなみに、綜藝種智院(の精神)は、現在は種智院大学へ引き継がれています。
空海の名言⑥ものごとの本質を見極める
医王の目には途(みち)に触れて皆薬なり
解宝(げほう)の人は鉱石(こうしゃく)を宝と見る。
知ると知らざると何誰(だれ)か罪過(ざいか)ぞ
『般若心経秘鍵』(はんにゃしんぎょうひけん)より
| 【現代語訳】 名医が見れば、道端の雑草さえもすべて薬になる。 宝石の専門家が見れば、鉱石のなかに宝石を見出す。 それがわかるかわからないかは本人次第である。 |
〝ものごとの本質を見極める〟には、分別の心を持たずに観察することが重要だと空海が説いている言葉です。
空海は、すぐれた医師が道端に生える草を薬草と見るように、宝石の専門家が鉱石のなかに宝石を見出すように、仏は私たちの本質的な価値を見抜くのだといいます。
私たちは、ものごとを〝好き/嫌い〟〝良い/悪い〟という基準で分別しがちです。
でも、分けへだてない仏の智慧によって観察すれば、すべてのものが優れた価値を持っていることに気づけます。
たとえば、雑草と見なされがちな「セイタカアワダチソウ」が、知っている人から見れば、貴重な蜜源植物(みつげんしょくぶつ:ミツバチが蜜を採取する花が咲く植物)や薬効のある植物だとわかるのと同じです。
現代社会は情報過多で、ものごとの本質を見失いがちです。
でも、仏の教えという智慧の光をともすことで、私たちは正しい視点でものごとを捉え、本来の価値を見極められるようになるのです。
私も分別の心を持たずにものごとを観察し、本質を見極められる人間になりたいものです^^
空海の名言⑦生と死の真実を直視せよ
生れ生れ生れ生れて生の始めに暗く、
死に死に死に死んで死の終りに冥(くら)し
『秘蔵宝鑰』より
| 【現代語訳】 自分はどこから何のために生まれてきたのか、 また死んだらどこへ行くのか、 何度生まれ変わろうとも誰にもわからない。 わかっているのは、 人はみな暗闇から生まれ、 死んだらまた暗闇に戻っていくということだ。 |
空海の言葉のなかでいちばん有名な言葉だと思います。
あなたも聞いたことがあるのではないでしょうか。
自分が生まれたときのことを覚えている人はおらず、死んだらどうなるかも本当のところは誰にもわかりません。
生まれる前にも、死んだ後にも暗闇が広がっています。
死が怖いのは、その先が暗闇だから。
でも、まるで死の恐怖から逃れるかのように、人は快楽や利益を貪欲に求めて生きています。
私も同じ(汗)
そして、生や死についてろくに考えることなく死んでいくのです。
空海はきっと、そんな人生を無為だと思っているのでしょう。
〈この世に生を受けた者は、いつか必ず死ぬ。ならば、その生と死から目をそらさず、その真実を直視しなさい! いつまで目をそらしているつもりだ〉
そんな空海のナマの声が聞こえてきそうな言葉だと思います。
空海の名言⑧仏と私たちは何が違うか?
仏身(ぶっしん)即(すなわ)ち是(こ)れ衆生身(しゅじょうしん)、
衆生身即ち是れ仏身なり
不同にして同なり、
不異にして異なり
『即身成仏義』より
| 【現代語訳】 仏とは私たち自身であり、 私たちは仏自身である。 仏と私たちは同じではないけれども同じであり、 異ならないけれども異なっている。 |
〈なんのこっちゃ?〉ですよね?(笑)
私も最初は〈???〉でした。
この言葉の意味は――
私たちはみな仏の心を持っているという点で仏と同じだが、ものごとを分別する心を持っている点で仏とは異なる
ということらしいです。
「分別する心」とは、〝好き嫌い〟や〝損得〟など、ものごとを勝手に2つに分けて考える心のことです。
仏には、そんな分別心などありません。
だから、仏になろう(即身成仏しよう)と思うならば、分別心を捨てないといけないのです。
そして、分別心を捨てて仏と同じになるために行なうのが、「三密行」になります。
空海の名言⑨悟りとは?
悟れるものを大覚(だいかく)と号し、
迷えるものを衆生(しゅじょう)と名づく
『声字実相義』(しょうじじっそうぎ)より
| 【現代語訳】 悟って目覚めた人を大覚と呼び、 まだ煩悩(ぼんのう)にとらわれている人を衆生と呼ぶ。 |
仏教における当たり前のことを説いているだけのようですが、煩悩にとらわれず悟ったかどうかが、仏と私たちの違いだという意味です。
しかし、違うといっても、その違いは汚れている水(私たち衆生)ときれいな水(仏)の違い、つまり状態の違いにすぎず、同じ水であることに違いはありません。
では、「悟り」とは何でしょうか?
この言葉が収められている『声字実相義』(しょうじじっそうぎ)のなかには、耳に聴こえる音は大日如来の声で、目に見える現象は大日如来の文字だといういう記述がありますが、その大日如来の声を聴いたり文字を見たりすることが「悟り」だということではないでしょうか。
もっとも、煩悩にまみれている私には、大日如来の声や文字はなかなか伝わってきませんが……(汗)
空海の名言⑩泥沼に咲く美しいレンゲの花のように生きよ
蓮(ハス)を観じて自浄を知り、
菓(このみ)を見て心徳(しんとく)を覚(さと)る
『般若心経秘鍵』(はんにゃしんぎょうひけん)より
| 【現代語訳】 蓮華(レンゲ)の花を見て、 自分の心が清らかであることを知り、 その実を見て、 自分の心に仏性が宿っていることを悟る。 |
レンゲ(蓮華)は、泥池でも美しい花を咲かせます。
そのため、仏教では、煩悩にまみれた世の中を生きる人間のあるべき姿の象徴だとされています。
また、蕾(つぼみ)のなかに実を宿すレンゲは、心のなかに仏性を宿すとされる人間にたとえられます。
つまり、世の中がどんなに汚れていても、レンゲのように美しい花を咲かせる(悟る)ことは可能だと空海は言うのです。
私も、レンゲの花を見たときは、自分が汚れていることを社会や環境のせいにしないように戒(いまし)めたいと思います。
空海の名言⑪空海は永遠に衆生救済を願いつづける
虚空(こくう)尽き、衆生尽き、
涅槃(ねはん)尽きなば、
我が願いも尽きなん
『続性霊集』より
| 【現代語訳】 この世の中が尽きるまで、 生きとし生けるものが尽きるまで、 涅槃=悟りを求める者が尽きるまで、 すべての人びとを救うという私の願いが尽きることはない。 |
832年8月、高野山(こうやさん)で、たくさんの灯明(とうみょう」)と無数の美しい花を献げた「万燈万華法会」(まんどうまんげほうえ)、略して「万燈会」(まんどうえ)が行われました。
この法会には、四恩(しおん:上記「空海の名言①」を参照)に報(むく)い、すべての衆生が無明を払って仏の智慧に目覚めることへの願いが込められました。
この万燈会で空海が誓ったのが、上記の言葉です。
〝世の中や人びと、悟りの世界がすべてなくなってしまえば、衆生を救いたいという私の願いは尽きてしまうけれども、そんなことはないはずだから、私は永遠に願い続ける!〟という空海の強固な意思を、私はひしひしと感じます。
この万燈会の3年後、62歳の空海は高野山で「入定」(にゅうじょう:永遠の瞑想に入ること)しました。
空海は今も、衆生救済を願いながら瞑想を続けていると信じられています。
ちなみに、万燈会は、真言宗の寺院では現在でも続けられています。
私は映像でしか見たことがありませんが、夜空を照らす色とりどりの灯明が幻想的な光景をつくり出し、思わずうっとりしてしまいますよ^^
▼空海は〝生きている〟!? くわしくはこちら↓↓↓

まとめ
空海の名言はいかがだったでしょうか?
あなたの心を揺さぶる言葉に出逢えましたか?
空海の言葉には、私たちを励まし、前向きにする力があります。
その力は、〝私たち人間には仏性が宿っていて、仏=大日如来と一体になることができる〟という空海の強固な信仰から発している——そう私は思います。
ここに紹介したのは、空海の言葉のうちのごくわずか。
もっと空海の言葉に触れてみたいという方は、空海の言葉を紹介した本をひもといてみてはいかがでしょうか。
▼空海の著作について知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海の生涯について知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海について広く知りたい方は、こちら↓↓↓