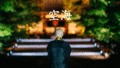「お大師さま」として親しまれ、今なお多くの人びとに慕(した)われている弘法大師・空海。
その偉大な生涯は、835年に高野山で幕を閉じました。
しかし、空海の死については、死ではなく「入定」(にゅうじょう)という深い瞑想に入ったという説と、「病死」だったという説があり、その真相は謎に包まれています。
私は、空海の死因にまつわる入定説と病死説の対決(?)には長らく興味を持ってきました。
そこで、この記事では、空海の最期にまつわる二つの説を深掘りし、なぜ今もなお〝空海は生きている〟と信じられているのか、その背景にある信仰の姿に迫ってみたいと思います^^
空海入定説を検証!最晩年に向けた壮絶な準備
真言宗の開祖として知られる空海は、835年3月21日、高野山奥之院で「入定」しました。
入定とは、悟りを得た僧侶が深い瞑想に入ることを意味します。
この考え方によれば、空海は亡くなったのではなく、今もなお高野山(こうやさん)で私たちを見守りつづけていることになります。
なんと空海は、この835年3月21日を入定の日にすると、あらかじめ決めていたと言われています!(驚)
しかも、「寅の刻」(とらのこく:午前4時頃)という時間まで!!(大驚)
入定の一週間前、空海は弟子たちを集め、「私は3月21日に入定する。悲しまずに、密教を広めつづけなさい」と告げ、多くの遺言を残しました。
この言葉からも、空海が自身の最期をみずからの意思で選び、弟子たちにその後を託したことがうかがえます。
それにしても、自分の最期の日時を自分で決めるなんて、可能なんでしょうか!?
私には無理です(笑)
空海の〝終活〟:入定にいたるまでの軌跡
空海は、831年頃から体調を崩し始めました。
そのため、大僧都(だいそうず)という高い僧位を辞退しています。
みずからの死期を悟った空海は、以下にご紹介するように、最晩年まで真言密教のさらなる発展のために尽力しました。
空海の〝終活〟①高野山への帰還
832年の秋、空海は長らく活動の拠点としていた平安京の東寺(とうじ)を離れ、修行の場である高野山へ戻りました。
そして、弟子たちのために〝終活〟を始めました。
高野山を密教の聖地として、弟子たちが修行を続けるための環境を整えることに力を注いだのです。
空海の〝終活〟②真言密教の基盤強化
空海は834年1月、宮中で行われる年始の儀式に密教の修法を取り入れる「後七日御修法」(ごしちにちみしほ)を行いました。
一方で、真言宗から毎年3名の僧侶を国家公認の僧侶として認めてもらうとともに、高野山の金剛峯寺(こんごうぶじ)が国家公認の寺院=「定額寺」(じょうがくじ)として認められるなど、真言宗の基盤を確固たるものにしていきました。
体調の悪さを押して、真言宗の発展のために尽くす空海は、きっと気迫に満ちた姿だったにちがいなかったんだろうと思います。
空海の〝終活〟③弟子たちへの遺言「御遺告」(ごゆいごう)
入定を予告した3月21日が迫る一週間前の3月15日、空海は弟子や信徒に対して、「御遺告」(ごゆいごう)と呼ばれる25カ条の遺言を示しました。
このなかには、寺院の運営方法や修行の心得、そして後継者となる弟子たちの指名など、空海が築き上げた真言宗を継続・発展させるための重要な指示が記されていました。
このように、空海は体調が悪化するなかでも、真言密教の将来へ向けて、その基盤を固めるために力を尽くしました。
空海は、それこそ文字どおり「全身全霊」で取り組んだのだと思います。
そして、みずから予言したとおり、3月21日午前4時ごろ、入定したと伝えられています。
やることはやり切ったという感じですね。
以上が〝空海入定説〟のあらましです。
▼空海の十大弟子について知りたい方は、こちら↓↓↓

空海の死因は病死?有力視される〝水銀中毒説〟
一方で、空海の死因は「病死」だったとする説があります。
10世紀に空海の弟子の1人である真済(しんぜい)が著したと伝わる『空海僧都伝』(くうかいそうずでん)には、空海の死因が病気だったと記されており、これが病死説の大きな根拠となっています。
この文献には具体的な病名までは記されていませんが、さまざまな状況証拠から、とりわけ有力視されている原因があります。
それは〝水銀中毒〟です!
空海の死因が水銀中毒だったのではないかという疑いは、私にはとても意外でした。
空海の死因が〝水銀中毒〟だと疑われる驚きの理由
なぜ空海の死因は水銀中毒だと疑われるのでしょうか?
その根拠を見ていきましょう。
空海の死因は?①滋養強壮薬「陀羅尼助」(だらにすけ)の存在
空海の存命当時、吉野地方(現在の奈良県)の修験者のあいだでは、「陀羅尼助」(だらにすけ)という薬が流行していました。
「陀羅尼助」とは、滋養強壮薬です。
平安版リゲインやユンケルのようなものだったのでしょうか?
やや気になるところではありますが(笑)、なんとその原料には水銀が含まれていたらしいのです!
空海がこの薬を服用していた可能性は充分に考えられます。
空海の死因は?②仏像制作における水銀の使用
空海は、真言密教の教えを広めるために数多くの仏像を制作しました。
そして、仏像の装飾に使われる金メッキの原料には水銀が不可欠だったのです!
空海は仏像制作を通じて水銀を摂取した可能性があります。
空海の死因は?③晩年の症状と水銀中毒の関連性
晩年の空海は、「よう」と呼ばれる悪性の腫(は)れものや肝臓障害に悩まされていたと伝えられています。
そして、これらの症状は、なんと水銀中毒が引き起こす症状と一致しているのです!
以上3つが、空海の病死説を裏づける有力な根拠となっています。
謎が謎を呼ぶ「入定」と「病死」の狭間
入定という神秘的な最期と、水銀中毒というリアルな病死説——
この2つの説のあいだには、魅力に満ちた空海の人物像があります。
空海は、病に苦しみながらも、衆生救済への強い意思に満ちていました。
そして、生涯をかけて布教に尽力しました。
その想いは、次の句に集約されています——
虚空尽き
涅槃尽き
衆生尽きなば
我が願いも尽きなむ
| 【現代語訳】 この世の中が尽きるまで、 生きとし生けるものが尽きるまで、 涅槃=悟りを求める者が尽きるまで、 すべての人びとを救うという私の願いが尽きることはない。 |
私のような凡人が言えるような言葉では決してないですね(汗)
空海は、このような誓願を立て、多くの人びとを救おうとしたのです。
〝荼毘(だび)に付された〟という記録の真偽
平安時代の歴史書『続日本紀』には、空海の遺体が弟子・実慧(じちえ)によって荼毘(だび)に付されたと記されています。
荼毘とは火葬のことです。
もしもこの記録が事実であれば、空海は入定したのではなく、多くの人びとと同じように亡くなったことになります。
しかし、年月を経るにつれて、空海は病死したのではなく、〝永遠の瞑想に入った〟とする文献が現れるようになります。
真言宗では、空海を「大師」として崇敬し、その入定を死ではなく、深い瞑想に入ったとしたのです。
なぜ今も〝空海は生きている〟と信じられているのか?
空海が〝入定〟してから1200年以上が経ちますが、今もなお少なからぬ人びとが〝空海は生きている〟と信じています。
なぜ〝空海は生きている〟と信じられているのでしょうか?
「即身仏」としての信仰
真言宗では、空海は「即身仏」(そくしんぶつ)だと信じられています。
「即身仏」とは、修行を極め、悟った僧侶が、生きたまま仏になるという真言密教の思想です。
空海が安置されている高野山奥之院の「弘法大師御廟」(こうぼうだいしごびょう)には、今も毎日2回、空海に食事が捧げられています。
▼即身成仏についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

「生身供」(しょうじんぐ)の儀式
空海に食事を捧げる儀式のことを「生身供」(しょうじんぐ)といいます。
この儀式は、空海が入定したとされる835年から1200年以上ものあいだ、一度も途絶えることなく続けられています。
この事実が、空海が今もなお生きつづけているという信仰を支える大きな柱となっています。
▼生身供についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

「同行二人」(どうぎょうににん)の思想
四国八十八ヶ所をめぐる「お遍路」では、巡礼者(お遍路さん)は常に空海がいっしょに歩いてくれていると信じています。
この「同行二人」(どうぎょうににん)という言葉は、空海が私たちを見守り、導いてくれているという信仰を如実に表しています。
まとめ
空海の最期は、入定だったのか、それとも病死だったのか?
真相は謎に包まれたままです。
しかし、入定説と病死説の2つの説は、空海という人物の深い人間性を物語っています。
病に苦しみながらも、人びとを救済しようと尽力した〝人間・空海〟。
一方、入定という形で永遠の命を得て、今も私たちを見守りつづけている〝仏・空海〟。
空海の死因をめぐるこの二面性によって、空海への信仰はより深まり、1200年以上たった今も、多くの人びとの心の拠りどころとなっているのです。
あなたも高野山を訪れて、弘法大師・空海の息吹を感じてみてはいかがでしょうか。
▼空海の生涯についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

▼空海について広く知りたい方は、こちら↓↓↓