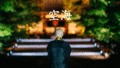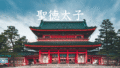聖徳太子(生前の名前は「厩戸王」〈うまやとおう〉「厩戸皇子」〈うまやどのおうじ〉など)は、歴史上の人物のなかでも、ひときわ伝説が多く、私たちのロマンを掻き立てます。
そんな聖徳太子の伝説のなかでも、その才能を語るうえで欠かせないのが、〝10人の話を同時に聞き分けた〟という超人的なエピソードです。
私は小学生だったときに、このエピソードを真に受け、「えっ、ほんと!?」と素直に驚きました。
でも、大人になった今、このエピソードに懐疑的になっている自分がいます。
だって、10人が一斉にしゃべったら、ただうるさいだけじゃないですか?(笑)
それとも、このエピソードは、聖徳太子の何か特別な能力を伝えたいがためのつくり話なのか……?
この記事では、この有名なエピソードの背景にある歴史的文献や、有力な説を紐解きながら、聖徳太子の真の姿に迫ってみたいと思います^^
〝聖徳太子10人聞き分け説〟伝説の始まりは8人?
聖徳太子が10人の話を聞き分けたというエピソードは、歴史書『日本書紀』や説話集『日本現報善悪霊異記』に記されており、一般的にもっとも知られているエピソードです。
しかし、他の文献には、違う人数が書かれているのをご存知でしょうか?
たとえば、現存する聖徳太子の伝記としては最古の『上宮聖徳法王帝説』(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ)や、平安時代の伝記『聖徳太子伝暦』(しょうとくたいしでんりゃく)には、その人数は「8人」と記されています。
このエピソードが元となり、聖徳太子は「厩戸豊聡八耳皇子」(うまやとのとよとやつみみのみこと)という別名で呼ばれたとされています。
一方、同じ『聖徳太子伝暦』には、太子は11歳のときに「36人」の子どもの話を同時に聞き分けたというエピソードが記されています!
いったい、どうしたら36人もの話を聞き分けられるのでしょうか!?
耳が36もあったのでしょうか?
ワケがわかりません(汗)
大人8人、のちに10人。
そして、子ども36人。
文献によって人数は異なりますが、どのエピソードも、聖徳太子がいかに高い能力を持つ人物であったかを強調しているように感じられます。
聖徳太子の偉大さが語り継がれるたびに、エピソードの中身が少しずつ盛られていったのかもしれません。
考えてみれば、話す相手が8人や10人であっても、話の内容を同時にすべて理解し、返答するのは至難の業(わざ)です。
私たちが日常生活で、「ちょっと待って、順番に話して!」と言いたくなるような状況を、聖徳太子は難なくこなしていたわけです。
もしもこのエピソードが本当だったとしたら、聖徳太子は人間の能力を超えた〝超能力〟を持っていたということになるでしょう。
〝聖徳太子10人聞き分け説〟を名前と科学から検証!
〝聖徳太子10人聞き分け説〟を「豊聡耳」(とよとみみ)から検証
〝聖徳太子10人聞き分け説〟は、聖徳太子に与えられた「豊聡耳」(とよとみみ)という呼び名と密接に関係していると考えられます。
この名前は〝豊かで聡(さと)い(賢い)耳を持つ〟という意味で、多くの人の話を聞き分ける能力に由来すると言われています。
しかし、最近では、これとはまるで異なる説が有力になってきました。
実は、古代において「ミミ」という言葉は、「耳」という意味ではなく、男性の尊称として使われていました。
そのため、「豊聡耳」という名前は、「耳がよい」から名づけられたのではなく、男性だから名づけられただけではないかというのです。
もしもこの説が正しければ、エピソードにちなんで名前がつけられたのではなく、後世の人びとが〝名前に「耳」という文字が入っているくらいだから、聖徳太子はきっと耳がよかったにちがいない!〟と推測し、超人的なエピソードを創作したことになります。
〝聖徳太子10人聞き分け説〟を「カクテルパーティー効果」から検証
一方、〝聖徳太子10人聞き分け説〟を科学的な視点から考えてみましょう。
「カクテルパーティーのような騒がしい場所であっても自分の名前や興味関心がある話題は自然と耳に入ってくるという心理効果」(一般社団法人日本経営心理士協会のHP)を「カクテルパーティー効果」といいます。
脳が集中力を使い、聞きたい音だけをフィルタリングする働きですね。
たとえば、男女の交流を目的とした食事会や飲み会である「合コン」で、参加者同士のおしゃべりのなかから気になる異性の声(おしゃべりの内容)を聞き分けた……なんていう経験が、あなたにもあるのではないでしょうか?
私はあります!(笑)
私たちの脳には、もともとこの機能が備わっています。
しかし、それでも、同時に話す10人、ましてや36人もの話を完全に聞き分けることは不可能です。
だとすれば、やはり聖徳太子は本当に超人的な聴力を持っていたのでしょうか?
いや、ひょっとすると、聖徳太子のすごさは別の部分にあったのかもしれません。
それは〝瞬間的な記憶力、理解力、判断力〟です。
つまり、聖徳太子は、順番に人びとの話を聞いたうえで、その内容を瞬時に記憶・理解し、的確な答えを返していったのではないか、ということです。
そうだとすれば、この能力は聴力というよりも、むしろ聖徳太子の並外れた知性と記憶力によるものだったと考えられます。
〝聖徳太子10人聞き分け説〟が暗示する聖徳太子の真の姿とは?
では、なぜ人びとは、聖徳太子の〝聞き分ける力〟を過度に強調して語り継いだのでしょうか?
それは、聖徳太子が為政者として、人びとの声に耳を傾けることを何よりも大切にしていたからだと推察できます。
聖徳太子が定めたとされる「十七条憲法」の第一条には、「和を以(もっ)て貴(とうと)しとなす」と記されています。
〝話し合いを大切にし、争いを起こさないようにせよ〟という教えです。
また、第十七条では、〝独断で物事を判断せず、みんなで議論して決めよ〟と説かれています。
天皇を中心とした中央集権国家を築こうとした時代に、独裁ではなく人びとの意見を尊重しようとした聖徳太子の姿勢は、当時としては画期的でした。
聖徳太子は、自分ひとりの考えではなく、多くの人びとの意見に耳を傾けることで、より良い国づくりができると考えていたのでしょう。
そして、この〝傾聴〟の姿勢こそが、〝聖徳太子10人聞き分け説〟を生み出す最大の要因になった可能性があります。
当時の人びとは、聖徳太子が本当に同時に多くの話を聞き取れたかどうかは別として、聖徳太子がいつでも人びとの声に真摯(しんし)に耳を傾けてくれる偉大な指導者であることを、このエピソードを通じて伝えようとしたのではないでしょうか。
現代においても、私たちの周りにはたくさんの情報や声が溢れています。
そのなかから本当に大切な情報や、心に響く言葉を見つけ出すのは簡単ではありません。
聖徳太子は、実際に10人の話を同時に聞き分けたのではなく、多くの人びとの意見をしっかりと聞き、理解し、最適な答えを導き出す能力に秀でていたのだと、私は思います。
科学技術が発達した現代でも、多くの人の話を一度に聞き分けて理解し、的確な対応をすることは、生身の人間には難しいものです。
そんななかで、伝説として語り継がれる聖徳太子の〝聞く力〟は、私たちが日々のコミュニケーションで忘れてしまいがちな、大切な姿勢を教えてくれていると感じます。
聖徳太子がもしも現代に生きていたとしたら、数多くの情報が飛び交うこの社会で〝聞く力〟を発揮し、どのような政治を行なってくれたでしょうか。
想像するだけでワクワクしますね^^
まとめ
- 〝聖徳太子10人聞き分け説〟は、最初は「8人」だったが、そのうち「10人」、さらには「36人」へと誇張されていった
- 聖徳太子の別名 「豊聡耳」(とよとみみ)」は、〝耳がいい〟という意味の他に、男性の尊称としてつけられた。つまり、聖徳太子の耳がよかったから名づけられたのではなく、 「豊聡耳」(とよとみみ)という名前がついているから〝耳がよかったにちがいない〟と解釈された可能性がある
- 聖徳太子は10人の話を同時に聞き分けられたわけではなく、優れた記憶力、理解力、判断力で人びとの話を素早く整理して答える能力に長けていたと考えられる
- 〝聖徳太子10人聞き分け説〟は、聖徳太子が人びとの意見を尊重する優れた指導者であったことを伝えるためのものだった。その証拠に、聖徳太子が定めた十七条憲法には話し合いの大切さが説かれている
▼聖徳太子が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓