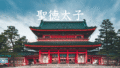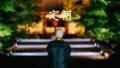聖徳太子(厩戸皇子)は推古天皇のもとで摂政を務め、冠位十二階や十七条憲法の制定、さらには仏教の普及を推進しました。
太子によって飛鳥時代の政治制度や思想の基礎が築かれ、後世にも深い影響を与えた人物と言えるでしょう。
その一方で、彼の晩年の姿や死因については多くの謎が残されています。
結論として、聖徳太子の死因は史料上「不明」 です。
『法隆寺金堂の釈迦三尊像光背銘文』によれば、聖徳太子は622年に亡くなったと記されています。(享年49歳)
ただし、太子の死因については明確な記録が残されていません。
このため、後世の人々は「病によって亡くなった」と解釈したり、「権力争いの渦中で暗殺されたのではないか」と推測したり、さまざまな物語を生み出しました。
確実な結論は出ていないものの、それらの物語をたどることで、当時の社会状況や人々の関心を知ることができます。
聖徳太子の死因は病気説が有力
定説とされているのが「天然痘」(てんねんとう)による病気説です。
天然痘は飛鳥時代から奈良時代にかけて日本各地で猛威を振るった感染症です。
「疱瘡」(ほうそう)とも呼ばれ、高熱と全身の発疹を伴い、重症化すると命を落とす恐ろしい病気で、当時の社会における大きな脅威の一つでした。
大陸との交流が盛んになる中で、天然痘は日本に伝わったとされています。
文化だけでなく病までもが国を越えてやってきたのですね。
現代でいえば、コロナ感染症が広がったときのような脅威だったのではないでしょうか。
聖徳太子が亡くなる直前、身近な家族が相次いで世を去っています。
まず母・穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)が亡くなり、その2ヵ月後には最愛の妻・膳部菩岐々美郎女(かしわでのほききみのいらつめ)が死去。
そして翌日、太子本人も斑鳩宮で崩御しました。
短期間に近親者が立て続けに亡くなったことから、一家全体に感染が広がっていたと考えるのは自然でしょう。
飛鳥時代の日本を大きく変えた聖徳太子も、この恐ろしい病には勝てませんでした。
その姿を思うと、人間の命の儚(はかな)さと歴史の厳しさをひしひしと感じます。
また、病気が人間社会にどれほど大きな影響を与えるかということも、改めて痛感されますね。
聖徳太子の死因には暗殺説もある
蘇我馬子の陰謀による暗殺説
一方、母、妻に続いて後を追うように亡くなっ
たのは不自然とする見方が暗殺説です。
とくに有名なのが蘇我馬子(そがのうまこ)の陰謀による暗殺説です。
蘇我氏は大臣として大きな権力を持ち、推古天皇や聖徳太子とともに政権を担いました。
しかし、両者の政治理念は必ずしも一致していませんでした。
聖徳太子は「天皇を中心とした国家体制」を理想にしたのに対し、蘇我馬子は「蘇我氏の権力拡大」を重視したとされます。
この違いがやがて軋轢(あつれき)を生み、蘇我馬子がみずからの権力基盤を守るため、聖徳太子を排除したのではないかと語られるようになりました。
もちろん、暗殺を裏づける記録はなく、あくまで憶測の域を出ません。
けれども、飛鳥時代が権力抗争に満ちていたことを考えれば、まったく荒唐無稽(こうとうむけい)とも言い切れないのです。
今も昔も政治の世界には権力争いがつきものだとはいえ、その非情さを感じずにはいられませんね。
本来であれば国家を良くしようと力を合わせるべき相手であった蘇我馬子から、逆に邪魔者として排除されたとするなら、聖徳太子の無念さは計り知れなかったのではないかと、私は思います。
そう考えると、あまりにも切なく胸が痛みます。
▼蘇我馬子と聖徳太子の関係をわかりやすく解説しています。こちらをクリック↓↓↓

刀自古郎女の嫉妬による暗殺説
一方、別の暗殺説として、刀自古郎女(とじこのいらつめ)の嫉妬による暗殺説があります。
聖徳太子には4人の妻がいましたが、その中でも一番身分が高かったのが、蘇我馬子の娘・刀自古郎女(とじこのいらつめ)でした。
しかし、聖徳太子が最も愛していたのは膳部菩岐々美郎女(かしわでのほききみのいらつめ)だったと言われています。
そこで、嫉妬に駆られた刀自古郎女が、膳部菩岐々美郎女や聖徳太子本人に手をかけたという話が生まれたのです。
ただし、この説はあくまで伝承や後世の創作に近いもので、信憑性は乏しいと言わざるを得ません。
病気に侵されていたとはいえ、女性が2人もの命を奪ったというのはにわかには信じがたい話です。
もしかして裏で糸を引いている人物がいたのか、それとも後世の人々がドロドロとした愛憎劇として脚色して語ったのか。
この説からは人々の想像や関心の強さが表れているように感じられます。
聖徳太子が死んだ場所から見える彼の思い
さて、それでは聖徳太子は、どこで亡くなったのでしょうか?
『日本書紀』によると、聖徳太子は斑鳩宮(いかるがのみや)で亡くなったという記述があります。
斑鳩宮は都があった飛鳥から北方20㎞ばかりのところにあり、現在の法隆寺に近い場所です。
なぜ聖徳太子が斑鳩宮を居所に選んだのかについては諸説あります。
ひとつは蘇我馬子との権力争いを避けて都から距離を置いたとする説です。
もうひとつは仏教の信仰に専念するために静かな地へ移り住んだという説です。
また、斑鳩は水上交通の要地であり、陸路からもさほど離れていない交通の要衝でした。
そのため、聖徳太子は政治と仏教の両面を営む拠点として斑鳩を選んだのかもしれません。
都での緊張に満ちた暮らしから逃れ、心安らぐ場所を求めていたのでしょうか。
崩御の後、聖徳太子は大阪府太子町にある「叡福寺」(えいふくじ)に埋葬されました。
この地に築かれた墓は「磯長陵」(しながのみささぎ)と呼ばれています。
磯長の地は蘇我氏とゆかりが深い土地であったため、この地が選ばれたと考えられます。
斑鳩宮からは少し離れてはいるものの、当時の高貴な人物の墓所は静寂な環境を重んじて選ばれることが多く、その点で磯長は適していたのでしょう。
注目すべきは、この陵墓に「三骨一廟」(さんこついちびょう)と呼ばれる埋葬形式が用いられたことです。
前年に亡くなった母・穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)、そして最愛の妃・膳部菩岐々美郎女(かしわでのほききみのいらつめ)とともに、聖徳太子がひとつの墓に合葬されました。
当時、身分の高い人物は1人ひとり個別の墓に葬られるのが一般的でした。
そのため三骨一廟は異例であり、家族への強い絆を示すものとも解釈されています。
最期に母や妻と共に葬られたことは、聖徳太子が家族への愛情を生涯通じて大切にしていたことが伝わってきます。
孤独を感じていた聖徳太子が家族の温もりを求めていたとしたら、人間らしい一面もあったのだと安心させられます。
まとめ
ここまで見てきたように、聖徳太子の死因は「天然痘による病死説」がもっとも有力ですが、陰謀による暗殺説や嫉妬による暗殺説といった異説も存在しています。
いずれも決定的な証拠はなく、聖徳太子の最期を完全に解き明かすことはできません。
太子の死因にさまざまな説が語られてきたのは、当時の社会状況や人々の関心を反映したものでしょう。
それだけ聖徳太子が大きな存在であったという証でもあります。
私たちはこの偉人に対して敬意を払い、あれこれ詮索せずに死因は謎のまま受け止めるのがふさわしいのかもしれません。
▼聖徳太子が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓