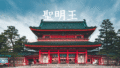日本の歴史における大きな転換点の1つとして、聖徳太子(厩戸王:うまやとおう)が制定したとされる冠位十二階(かんいじゅうにかい)があります。
冠位十二階の制度は603年に導入され、それまでの古い秩序を打ち破り、日本という国が中央集権国家へと舵(かじ)を切るための重要な一歩となりました。
なぜ冠位十二階が制定され、日本という国をどのように変えていったのか、徹底解説していきます^^
冠位十二階とは?これは古代の人事革命だ!
冠位十二階とは、推古天皇を補佐していたとされる聖徳太子が603年(推古天皇11年)に定めた、日本最初の位階制度です。
簡単に言えば、朝廷で働く役人たちのあいだに、上から下まで12段階の明確なランクづけを設けた制度のことです。
役人がかぶる冠(かんむり)の色でランク=位(くらい)を区別したことから「冠位十二階」と名づけられました。
それまでの日本では、「氏姓制度」(しせいせいど/うじかばねせいど)によって、役職や身分が生まれた家柄で決められていました。
そのため、どれほど能力があっても、低い家柄に生まれれば、出世の道は閉ざされていたのです。
能力がある人のなかには、さぞや悔しい思いをしていた人がいたでしょうね。
一方の冠位十二階は、家柄による世襲制を打破し、個人の能力や功績に応じて位階(冠)を授けるという、まさに能力主義にもとづく画期的な制度でした。
これにより、有力な豪族の出身でなくても、優れた人材が政治に携わることができる門戸が開かれたのです。
冠位十二階制定の背景:氏姓制度の限界とは?
冠位十二階が制定される以前の朝廷では、「氏姓制度」が支配的でした。
氏姓制度は、人びとを血縁や地域などに応じて「氏」(うじ)と呼ばれる同族集団に編成し、朝廷がそれぞれの氏に対して「姓」(かばね)と呼ばれる序列を与えるというものでした。
たとえば、有力豪族には「臣」(おみ)や「連」(むらじ)といった姓が与えられました。
なかでも、最有力豪族であった蘇我氏には「大臣」(おおおみ)、大伴(おおとも)氏や物部(もののべ)氏には「大連」(おおむらじ)が与えられ、政権を司りました。
氏姓制度の問題点
氏姓制度には、中央集権的な国家運営を目指すうえで大きな問題がありました。
第1に、世襲による能力低下の問題です。
姓は代々世襲されるため、役職はその一族が独占しがちでした。
これにより、たとえ他の氏族に有能な人物がいても、身分が低ければ登用されず、逆に能力に乏しい人物でも、家柄が高いだけで高い役職に就くことができました。
これは現代の世襲企業にも通じる問題ですね。
第2に、朝廷と役人の関係が希薄だという問題です。
朝廷(天皇)が指名できたのは、あくまで朝廷に仕える「氏」(氏族)だけでした。
そのため、実際に朝廷で働く個々の役人は氏族のなかで選ばれた人物で、朝廷が選抜していたわけではないので、役人と朝廷(天皇)の関係は希薄でした。
何か問題が起こったときは、役人たちは朝廷よりも派遣元の氏族の言うことに従う恐れがあり、朝廷が役人を直接コントロールしにくいという危険性があったのです。
聖徳太子の政治改革への布石
豪族による集団政治の体制に代え、天皇を中心とした律令国家(法令によって運営される国家)を建設するため、聖徳太子は政治改革に着手します。
聖徳太子は大陸の文化や政治制度を学ぶため、600年(推古天皇8年)に隋(ずい)へ遣隋使を派遣しました。
その結果、当時の国際情勢や朝鮮半島(高句麗や百済)の制度を参考にしながら603年に導入したのが冠位十二階だったのです。
当時の朝廷では、最強の氏族である蘇我氏の中心人物である蘇我馬子(そがのうまこ)が推古天皇と協力関係を結んでおり、政局が比較的安定していたことも、新しい制度を導入する後押しとなったと考えられます。
冠位十二階制定の目的:内政と外交の2大戦略とは?
冠位十二階が制定された目的は、主に2つありました。
1つは国内の政治体制の強化。
もう1つは対外的な体裁の確立です。
有能な人材の登用と中央集権体制の強化
もっとも重要な目的は、生まれ(氏姓)にとらわれず、優れた能力を持つ人材を政治に登用し、天皇を中心とする朝廷の機能を強化することでした。
能力主義の導入
冠位十二階は個人に与えられるもので、世襲ではありませんでした。
そのため、身分の低い豪族や一般の出身であっても、能力が高ければ高い冠位を得ることが可能となりました。
冠位が高ければ、生まれが低い家柄でも、高い家柄の人を部下にすることができました。
朝廷と役人の関係強化
役人ひとりひとりを朝廷が直接評価し、ランクづけ(冠位)することで、朝廷と役人との関係が密接になりました。
役人たちは、氏族ではなく朝廷への忠誠心と仕事へのモチベーションを高めることができたのです。
上下関係の明確化
個人の能力に基づいて冠位を授けることで、朝廷の役人たちのあいだに明確な上下関係がつくられ、組織としての統制が取りやすくなりました。
外交的な体裁の確立
冠位十二階制定の目的には、国際的な国家としての体裁を示すという外交的な側面もありました。
当時、中国(隋)や朝鮮半島(高句麗、百済、新羅)など、周辺の主要国ではすでに官人(役人)に階級を与える制度が導入されていました。
日本も独自の、きちんとした階級制度を整えることで、国際社会において国家体制が整った国であることを示す必要がありました。
これにより、外国から使者が来たときに、日本の官僚が地位に応じて適切に応接し、重要な外交相手であることを使者にアピールすることができたのです。
冠位十二階は600年の第1回遣隋使派遣のあとの603年に制定されましたが、これは、使者の身分を明確にする必要性があったためだと考えられます。
ちなみに、第2回遣隋使派遣(607年)では、冠位十二階における5位・大礼(だいらい)の小野妹子(おののいもこ)が遣隋使として選ばれています。
冠位十二階の内容:冠の色で序列が一目瞭然!
冠位十二階は、全部で12の序列で構成されていました。
冠位の序列と儒教の徳目
| 序列 | 徳目 | 階級(冠位) |
| 1位 | 徳 | 大徳(だいとく) |
| 2位 | 小徳(しょうとく) | |
| 3位 | 仁 | 大仁(だいにん) |
| 4位 | 小仁(しょうにん) | |
| 5位 | 礼 | 大礼(だいらい) |
| 6位 | 小礼(しょうらい) | |
| 7位 | 信 | 大信(だいしん) |
| 8位 | 小信(しょうしん) | |
| 9位 | 義 | 大義(だいぎ) |
| 10位 | 小義(しょうぎ) | |
| 11位 | 智 | 大智(だいち) |
| 12位 | 小智(しょうち) |
冠位十二階の序列では、6つの「徳目」をそれぞれ大(だい)と小(しょう)に分けます。
この徳目には、中国の思想である儒教(じゅきょう)の教えが色濃く反映されています。
「徳・仁・礼・信・義・智」のうち、「仁・礼・信・義・智」は儒教で説かれる徳目「五常」(ごじょう)に対応しています。
- 仁:人を思いやる心
- 義:為すべきことをする正義
- 礼:人を思いやる具体的な行動
- 信:誠実で友情に厚いこと
- 智:知識が豊富なこと
これらの徳目の上に最高位の「徳」を置くという構成には、当時の高官たちが儒教の教えを重視していたことが反映されています。
また、「仁・礼・信・義・智」という順番は、古代中国の自然哲学である「五行思想」(ごぎょうしそう)に対応させた日本独自の工夫であったという説が有力です。
ちなみに、「五行思想」というのは、「万物は火・水・木・金・土(七曜の命令)の5種類の元素からなるという説」(ウィキペディア)です。
冠位の色と序列
それぞれの位階は、役人がかぶる冠(かんむり)の色で区別されました。
残念ながら、どの色がどの位階に対応していたかを示す確実な史料は残っていませんが、前述の五行思想における「五行五色説」にもとづく有力な説では以下のように考えられています。
| 大徳 | 濃紫 |
| 小徳 | 薄紫 |
| 大仁 | 濃青 |
| 小仁 | 薄青 |
| 大礼 | 濃赤 |
| 小礼 | 薄赤 |
| 大信 | 濃黄 |
| 小信 | 薄黄 |
| 大義 | 濃白 |
| 小義 | 薄白 |
| 大智 | 濃黒 |
| 小智 | 薄黒 |
これなら、誰が何の位だということがひと目でわかるから、規律が保ちやすくなりますね。
冠位十二階が日本の基礎をつくった!
冠位十二階の導入は、日本の歴史において画期的な取り組みでした。
世襲制が根強かった時代に、生まれ(家柄)ではなく能力によって登用するという理念を実行したことは、豪族の連合国家から天皇を中心とする中央集権国家へ移行するための大きな布石となりました。
そして、有能な人材の登用が進むと、朝廷内の規律を正す必要が生じ、翌年の604年には十七条憲法が制定されました。
十七条憲法には役人たちが仕事をするうえでの心得が記され、冠位十二階とともに天皇の権力を強め、朝廷の機能を強化することを目的としていました。
冠位十二階は、その後も継続され、647年に冠位十三階(七色十三階冠:ななしきじゅうさんかいかん)が制定されるまで40年以上も存続しました。
そして、律令制度(大宝律令など)における位階制度の基礎となり、日本の官僚制度の原型を築いたと言えます。
もっとも、冠位十二階には、最高権力者の蘇我氏が制度の対象外となるなど、不完全な部分がありました。
強固な天皇中心の国家を確立するには、645年の「乙巳(いっし)の変」で蘇我氏が滅亡し、672年の「壬申(じんしん)の乱」によって天武天皇が即位するのを待つ必要がありました。
しかし、そうしたことを差し引いて考えても、能力主義という現代にも通じるあり方を約1400年も前に導入した聖徳太子の英断は、日本の政治史における壮大で果敢なチャレンジだったと、私は思います。
冠位十二階の制度が、日本の国家としての基盤を築いたことは間違いないでしょう。
▼聖徳太子が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓

▼十七条憲法って何?詳しくはこちらをクリック↓↓↓

▼遣隋使に隠された聖徳太子の外交戦略とは?こちらをクリック↓↓↓