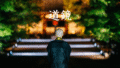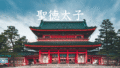あなたは、「聖徳太子は実在しなかった」という衝撃的な説を耳にしたことはありませんか?
かつて1万円札の顔だった聖徳太子が架空の存在だった……
そんな話、にわかには信じられないですよね。
この謎を解き明かすために、この記事では聖徳太子の実在説と非実在説について掘り下げていきたいと思います!
〝聖徳太子実在説〟の核心
まず、多くの人が勘違いしていることから始めましょう。
実は、「聖徳太子」という名前は本名ではありません。
「えーっ!?」とびっくりしましたか?
私も最初は同じ反応でした^^;
実は、「聖徳太子」という名前は、その功績を称える人びとが死後100年ほど経ってから贈った尊称なのです。
本名は「厩戸王」(うまやとおう)「厩戸皇子」(うまやとのみこ)「厩戸豊聡耳皇子」(うまやとのとよとみみのみこ)などとされていますが、はっきりしたことはわかっていません。
厩戸王(574〜622)は、飛鳥時代の皇族で、用明天皇の皇子として生まれました。
そして、政治の中枢にいたことは間違いない事実とされています。
ですから、その当時、「聖徳太子」と呼ばれる人物は実在しなかったとしても、「厩戸王」と呼ばれる実在の人物はいた――
これが〝聖徳太子実在説〟の基本的な考え方です。
ちょっとだけ安心しました(笑)
教科書では、厩戸王、すなわち聖徳太子は、「冠位十二階」や「憲法十七条」の制定、「遣隋使の派遣」など、数々の偉業をなしとげたと学びます。
私なんか、まさにそのとおりに教わりました。
こうした功績があったからこそ、〝聖なる徳を持った皇子(太子)〟という意味をもつ「聖徳太子」として称えられ、その名が後世に伝わってきました。
それなのに、なぜ今、〝聖徳太子の実在〟が疑われるのでしょうか?
その鍵は、聖徳太子(厩戸王)が行なったとされるこれらの偉業が、〝本当に彼1人の力でなしとげられたのか?〟という点にあるようです。
〝聖徳太子非実在説〟の衝撃の内容を徹底解説!
〝聖徳太子非実在説〟は、日本古代政治史が専門で、中部大学名誉教授の大山誠一氏が、1999年に出版した『聖徳太子の誕生』(吉川弘文館)のなかで提唱した説が始まりです。
大山説は、決して厩戸王という人物の存在を否定するものではありません。
しかし、〝私たちが知る聖徳太子像は後の時代に政治的な意図でつくり上げられた〟と主張します。
「そんなことあるのか!?」と思ってしまいますよね(汗)
どういうことなのか、その内容を具体的に見ていきましょう。
〝聖徳太子非実在説〟の核心:〝聖人・聖徳太子〟は捏造!?
大山誠一氏の主張はシンプルかつ大胆です。
上述したように、大山誠一氏は、厩戸王という人物を否定しているわけではありません。
飛鳥時代に、斑鳩宮(いかるがのみや)に住み、法隆寺を建てた有力な〝皇族・厩戸王〟は実在したと認めています。
しかし、私たちが教科書で学んできた〝推古天皇の摂政として数々の偉業をなしとげた聖徳太子〟という人物像は、後世に創作されたものだと断定しているのです。
大山説の根拠は、史料批判です。
大山誠一氏は、聖徳太子に関する史料を検証し、それらがすべて、彼の死後100年以上も経ってから書かれたり、作られたりしたものであると結論づけました。
聖徳太子をめぐる2つの〝捏造〟
大山誠一氏によれば、聖徳太子という人物像は、大きく分けて2段階にわたって〝捏造〟されていったといいます。
1つが、『日本書紀』による聖徳太子像の創作です。
厩戸王の死後、約50年後に起きた皇位継承をめぐる壬申(じんしん)の乱を経て、天武天皇は〝天皇を中心とする律令国家〟の建設を進めます。
このとき、国家の正統性を確立するために、中国の皇帝にも匹敵する理想的な天皇のモデル像が必要とされました。
そこで、天武天皇の皇子である舎人親王(とねりしんのう)が中心となって編纂された『日本書紀』(720年完成)のなかで、厩戸王を「聖徳太子」として英雄化し、彼の事績を誇張・美化して記述した、と大山氏は主張しています。
この創作には、当時の実力者であった藤原不比等(ふじわらのふひと)や、唐から帰国した僧の道慈(どうじ)らが関わったと推察されています。
もう1つの〝捏造〟は、天平年間(729〜749年)に疫病(えきびょう)が流行した際に、時の権力者である光明皇后(こうみょうこうごう)らが、疫病退散を願う聖徳太子信仰を創作したことです。
聖徳太子信仰を広めるために、法隆寺にある仏像や天寿国繍帳(てんじゅこくしゅうちょう)がつくられ、聖徳太子のイメージがさらに神格化されていったというのです。
このように、大山誠一氏は、聖徳太子の人物像が、政治的な意図を持った為政者たちによって段階的につくり上げられたと主張しているのです。
〝捏造の証拠〟とされた3つの史料
大山誠一氏が〝聖徳太子非実在説〟の根拠として重視しているのが、以下の3つの史料です。
日本は憲法十七条を制定する文化水準になかった?
大山誠一氏は、聖徳太子が制定したとされる憲法十七条が、当時の日本の文化水準では書くことができなかったと指摘します。
なぜなら、憲法十七条には中国の古典が多数引用されており、非常に高度な漢文で書かれているからです。
その根拠として、日本の使者が中国の思想をわきまえず、中国の政治秩序を無視した発言をしたという、中国の歴史書『隋書』の記録を挙げています。
このことから大山誠一氏は、当時の日本には中国の古典に学ぶ機運が乏しく、高度な憲法を制定できる文化水準になかったと結論づけています。
▼憲法十七条をわかりやすく、そして詳しく解説!こちらをクリック↓↓↓

『三経義疏』は輸入品?
学校では、聖徳太子は『三経義疏』(さんぎょうぎしょ)を書いたと習います。
私もたしかに、日本史の授業でそう習いました。
『三経義疏』とは、法華経、維摩経(ゆいまきょう)、勝鬘経(しょうまんぎょう)の3つの仏教経典に関する注釈書です。
ところが、大山誠一氏は、そのなかの『勝鬘経義疏』(しょうまんぎょうぎしょ)について、中国の敦煌(とんこう)で出土した写本と7割が同じ文であるという研究結果を引用し、中国から輸入されたものだと主張しました。
つまり、少なくとも『勝鬘経義疏』は聖徳太子自身が書いたものではなく、中国から持ち込まれたものが聖徳太子の著作と見せかけられたというわけです。
▼三経義疏について超わかりやすく解説!こちらをクリック↓↓↓

天寿国繍帳は後世の作?
聖徳太子の死後、妃(きさき)であった橘大郎女(たちばなのおおいらつめ)がその死を偲(しの)び、聖徳太子が往生した天寿国の様子を刺繍(ししゅう)として描かせたのが「天寿国繍帳」(てじゅこくしゅうちょう)です。
大山誠一氏は、その銘文に記された言葉が時代にそぐわないとして、この史料が後世につくられたものだと主張します——
- 「天皇号」の使用:銘文に「天皇」という称号が使われているが、この称号は天武天皇の頃から使われ始めたもので、聖徳太子の時代には存在しなかった
- 「儀鳳暦」(ぎほうれき)の採用:銘文の日付を、聖徳太子の時代に使われていた暦「元嘉暦」(げんかれき)ではなく、持統天皇の時代に採用された唐の暦「儀鳳暦」(ぎほうれき)で計算すると、日付のズレがなくなる
これらを根拠に、大山誠一氏は、天寿国繍帳は聖徳太子の時代よりかなり後の時代につくられたと結論づけるのです。
〝聖徳太子非実在説〟への反論
大山誠一氏の〝聖徳太子非実在説〟は、日本史学界に大きな衝撃を与えました。
しかし、大山誠一氏の主張は、仮説や妄想にしかすぎないという厳しい批判があります。
〝聖徳太子非実在説〟への反論は、次の3つにまとめられます——
『三経義疏』は本当に輸入品か?
大山誠一氏が輸入品と主張した『三経義疏』には、中国人が書く漢文には見られない「倭習」
(わしゅう)という日本の漢文特有の癖が数多く認められるという指摘があります。
これは、聖徳太子が書いたか、少なくとも日本人が書いた可能性を強く示しています。
なぜ厩戸王を聖徳太子に見せかけたのか?
大山誠一氏は、〝なぜ厩戸王を聖徳太子に見せかけたのか?〟というもっとも根幹の問いに十分な答えを出していないと批判されています。
もしも為政者が理想の天皇像を創作したかったのなら、なぜ数ある皇族のなかから、わざわざ厩戸王を選んで英雄化する必要があったのでしょうか?
この問いに対して、そもそも厩戸王が非常に優れた人物で、英雄化するのにふさわしかったからだと考える研究者もいます。
聖徳太子はタブーだった?
大山誠一氏は、聖徳太子が天皇家のルーツとしてさかのぼれるばかりか、仏教界の大恩人でもあるため、ほぼタブー(不可触領域)扱いされてきたと指摘しています。
一方で、〝『日本書紀』を編纂した藤原氏が、ライバルである蘇我氏の血を引く聖徳太子を、そこまで聖人化する必要があったのか?〟という疑問を呈する研究者もいます。
まとめ
私個人としては、大山誠一氏の〝聖徳太子非実在説〟は、とても興味深い視点を提供してくれたと思います。
また、これまで当たり前とされてきた日本史の常識に、正面から疑問を投げかけたその勇気と発想力は、研究者としてすばらしいと思います。
大山誠一氏の主張によって、聖徳太子という人物を、たんなる偉人としてではなく、もっと深く多角的に見直す機会が得られたのではないでしょうか。
しかし、その一方で、大山誠一氏の〝聖徳太子非実在説〟は、限られた史料をもとに論理を飛躍させ、結論を急ぎすぎているように感じられます。
大山誠一氏が指摘した史料の信憑性への疑問は、その後の研究によって批判され、弱点が露呈しました。
こうした〝聖徳太子非実在説〟には客観性に欠けるところがあるので、〝日本史学における新しい学説〟ではなく、〝日本史学における新しい問いかけ〟と捉えるのが適切ではないかと、私は思います。
それにしても、実際のところ、聖徳太子は実在したのでしょうか?
それとも実在しなかったのでしょうか?
この問いに対する最終的な答えは、まだ誰も出せていません。
いつか、その答えが明らかになる日が来るまで、聖徳太子をめぐるロマンあふれる議論を楽しみたいと思います^^
▼聖徳太子が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓