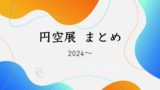円空仏には国宝がない……(涙)
江戸時代初期に、ナタやノミ1つでさまざまな仏を彫り出した仏師・円空(えんくう)。
その数、12万体にもおよぶと言われています!
ひと目見れば「円空仏だっ!」とすぐにわかるような独特の表情とフォルムで、現代人にもファンは多いです。
私もその1人^^
円空仏を集めた展覧会もあちこちで開かれています。
▼円空展に関する情報は、こちら↓↓↓
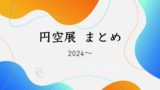
ところが、日本の仏像史を語るうえで決して欠くことができない円空(仏)であるにもかかわらず、国宝に指定された仏像が1体もありません!
円空の仏像は、どこからどう見たってすばらしいし、庶民の信仰を長く支えてきました。
なのに、残念……(涙)
その理由ははっきりとはわかりませんが、国宝級の円空仏は確実に存在します!
ということで、私にとっての国宝級の円空仏を2体ご紹介します^^
国宝級の円空仏①両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)
1つは、岐阜県高山市にある千光寺(せんこうじ)の円空仏寺宝館に所蔵されている「両面宿儺坐像」(りょうめんすくなざぞう)です。
円空展のチラシを飾るのは、決まってこの両面宿儺坐像です。
一度見たら絶対に忘れられない姿だと思いませんか?
私はひと目見て、虜(とりこ)になりました^^
一方で、「リョウメンスクナ」という名前は、最初はまるで覚えられませんでした(汗)
もっとも今の若い人なら、人気マンガ『呪術廻戦』に登場する史上最強で最悪の呪いの王の名前として聞いたことがあるのではないでしょうか。
両面宿儺の名前の初出は『日本書紀』(720年)です。
この『日本書紀』のなかに、〝身体は1つなのに顔は2つ、手足は各4本〟という姿の両面宿儺が飛騨地方にいたことが記されているのです。
円空の両面宿儺坐像の最大の特徴は、『日本書紀』では前後に顔を備えているという記述とは異なり、宿儺の両方の顔を並べて彫っているところです。
円空の自由な発想と解釈が存分に発揮されていると思います。
しかも、慈悲と忿怒(ふんぬ)の表情が同居しているのも大きな特徴です。
ふつう仏像の顔は、如来(にょらい)や菩薩(ぼさつ)が穏やかな慈悲の表情、明王(みょうおう)や天部が怒りに満ちた忿怒(ふんぬ)の表情であることがほとんどですが、円空の両面宿儺坐像は忿怒の表情のなかにも慈悲の表情が見て取れます。
慈悲と忿怒の両方の表情を併せ持つ仏像は、他に見たことがありません。
唯一無二(ゆいいつむに)です。
このように両面宿儺坐像は、円空の高い独創性が如実に表現された1体だと、私は思います。
国宝級の円空仏②十一面千手観世音菩薩立像(じゅういちめんせんじゅかんぜおんぼさつりゅうぞう)
もう1体は、岐阜県高山市の清峯寺(せいほうじ)が所蔵する「十一面千手観世音菩薩立像」(じゅういちめんせんじゅかんぜおんぼさつりゅうぞう)です。
名前が長すぎますね(汗)
ふつうは、たんに「千手観音」と呼ばれています。
円空が、1690年頃、飛騨地方に滞在したとき、檜(ひのき)に一刀彫りしたものだとか。
円空晩年期の作品です。
この千手観音は、聖観世音菩薩像(善財童子)立像、そして、龍頭観世音菩薩(善女龍王)立像といっしょに並べて安置されています。
真ん中が千手観音、左が聖観音、右が龍頭観音という並びです。
千手観音は、表情がとても温和で、静かに柔らかく微笑んでいます。
口元にかすかな微笑を浮かべた「アルカイックスマイル」というやつですね。
日本では、中宮寺や広隆寺の半跏思惟像に見られます。
眼は半眼で、親近感が感じられ、身体は衲衣(のうえ)で覆われています。
そして、背中からは放射状に何本もの手が生えていて、何かを捧げるかのような形をしていたり、人びとの苦しみを救うかのような形をしていたりします。
〝よくぞこれだけの手をナタやノミだけで彫ったな〟と感嘆するような出来映えです。
3体はどれも1メートルを超える大きさです。
千手観音127cm、聖観音160cm、龍頭観音170cm。
この大きさになると、円空仏独特の表情とフォルムの迫力が倍増します!
倍増するのは迫力だけではありません。
千手観音の神々しい美しさも倍増です。
千手観音(と聖観音と龍頭観音)は地元の方が管理されていて、予約をしないと拝観できないそうですが、訪れる人びとのハートを鷲掴み(わしづかみ)にしているようです^^
このように、十一面千手観世音菩薩立像は、その表情においても、そのフォルムにおいても、その美しさにおいても、その大きさにおいても、他の仏像とは一線も二線も画するような特異な存在なのです。
まとめ
私は円空仏が大好きで、他にも国宝級だと思う円空仏はあるのですが、とりわけ円空仏の傑作と言われている2体を指定しました。
円空仏は実際に拝観して初めて、その独特な魅力を味わうことができます。
まだ円空仏を観たことがないという方は、ぜひ1度、会いに行ってみてください!
▼円空の生涯や円空仏の魅力を知りたい方は、こちら↓↓↓

▼円空展についての情報は、こちら↓↓↓