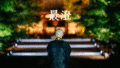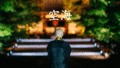【この記事でわかること】
- なぜ平安時代を生きた弘法大師・空海に食事を出すのか
- 高野山で空海に食事を出す「生身供」とはどんな儀式か
- 生身供が行われる時間や、撮影・見学の可否
- 生身供のメニュー
生身供とは?高野山で空海に食事を出す?なぜ?
和歌山県にある高野山(こうやさん)は、弘法大師・空海が平安時代初期に密教の修行の場として開き、現在では真言宗の総本山・金剛峯寺(こんごうぶじ)の境内となっています。
高野山=金剛峯寺の境内という「一山境内地」(いっさんけいだいち)です。
その高野山・金剛峯寺で、空海に食事が出されています。
「生身供」(しょうじんぐ)です。
でも——
「空海って、平安時代の人だから、とっくに亡くなっているでしょ? なのに、なんで食事? どういうこと???」
そう誰しもが思うはずです。
なぜ、すでに亡くなっているはずの弘法大師・空海に食事を出すのでしょうか?
そのワケは……
弘法大師・空海は〝生きている〟からです!
たしかに空海は835年に亡くなっています。
でも、それは〝歴史的には〟です。
〝信仰的には〟亡くなってはおらず、〝入定した〟とされるのです。
「入定」(にゅうじょう)とは、悟りの境地に入った、永遠の瞑想に入った、という意味で、これはつまり、肉体をもったまま仏になる=「即身成仏」(そくしんじょうぶつ)するということです。
なので、弘法大師・空海は亡くなったのではなく、仏として今も〝生きている〟のです。
▼空海の生涯について知りたい方は、こちら↓↓↓

生身供とは高野山の奥の院にいる空海に食事を出す儀式
弘法大師・空海が入定しているのは、高野山・金剛峯寺の境内のいちばん奥にある「奥之院」(おくのいん)というエリアの、さらにいちばん奥にある「弘法大師御廟」(こうぼうだいしごびょう)です。
ここで、今なお〝生きている〟弘法大師・空海に食事を出す儀式=生身供は行われます。
生身供は、弘法大師・空海の入定後から現在まで、1200年ものあいだ続けられています。
高野山では1年のあいだに数多くの儀式や行事が行われますが、生身供のように1200年も続いている儀式は他にないのではないでしょうか。
生身供の時間は?様子は?見学できる?
生身供が行われる時間は、朝6時と10時半の2回です。
毎日行われます。
上の動画を観ていただければわかりますが、とても厳かな儀式です。
身が引き締まりますよ^^
弘法大師・空海への食事は、奥の院の御廟橋(ごびょうばし)手前にある御供所(ごくうしょ)で調理されます。
そして、「嘗試地蔵」(あじみじぞう)で弘法大師・空海への食事を〝味見〟してもらいます。
「嘗試地蔵」というのは、空海の食事の世話をしていた愛慢(あいまん)、愛語(あいご)という2人の弟子が、御廟橋(ごびょうばし)の脇に「御厨明神」(みくりやみょうじん)として祀られたのが元となっているようです。
味見専門のお地蔵さんって、珍しいですね^^
〝味見〟の際には、地蔵菩薩の真言を唱えます。
続いて、白木の箱に納められた弘法大師・空海への食事を、2人の僧侶が担ぎ、案内人の「維那」(ゆいな:役割の名前)を先頭に御廟へ進んでいきます。
その後、弘法大師・空海への食事は、御廟の拝殿にあたる燈籠堂(とうろうどう)へお供えされます。
そして、読経のあと、維那と食事を担いだ2人の僧侶はふたたび御供所へと戻ってきます。
その間、約30分。
撮影は御廟橋から先は禁止ですが、見学することはできます。
ただし、御廟のなかに入ることはできません。
御廟のなかに入ることができるのは維那だけです。
一般人が中の様子を窺い知ることはできないのです。
御廟のなかがどうなっているのか興味がそそられますが、神聖な空間なので、そこは仕方がありませんね。
生身供のメニューとは?
高野山で弘法大師・空海に食事が出されるというだけでも興味深いですが、どのようなメニューなのか気になりますよね?
どうやら、朝6時に届ける朝食は、ご飯と味噌汁、野菜のおかず2品、ほうじ茶。
10時半に届ける昼食は、ご飯と味噌汁、おかず3品。
基本は精進料理ですが、たまにパスタやシチュー、カレーライス、オムライスといった洋食が出ることも。
メロンなどのデザートがついたり、午後には抹茶や緑茶、コーヒーなどの飲み物が供されたりするそうです。
また、正月にはおせち料理が出されます。
弘法大師・空海のための食事ですから、きっとどの料理もとてもおいしいんでしょうね。
ちょっとでいいから実物を見てみたいものです!
▼生身供でパスタが供される理由と意味について考えてみました↓↓↓

まとめ
- 高野山で弘法大師・空海に食事が運ばれるのは、空海が〝生きている〟から
- 高野山で〝生きている〟弘法大師・空海に食事を届ける儀式が「生身供」
- 生身供が行われる時間は朝6時と10時半
- 御廟橋から先は撮影禁止だが、見学は可能
- 生身供のメニューは基本的に精進料理だが、洋食が出ることも
▼空海についてさらに知りたい方は、こちら↓↓↓