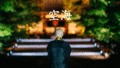運慶にまつわる主な展示会やご開帳、講演会など、これまでの情報をまとめています。
並び順は、新しい情報から古い情報へ下っていく「降順」です。
運慶展:2025年
運慶 祈りの空間—興福寺北円堂
場所:東京国立博物館
期間:2025年9月9日〜11月30日
ふだんは見ることができない興福寺北円堂の内部を再現し、運慶作品が7体展示されます。

▼『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』に行ってきました♪レビューはこちら↓↓↓

運慶展:2024年
運慶——女人の作善と鎌倉幕府
場所:神奈川県立金沢文庫
期間:2024年11月29日〜2025年2月2日
「運慶——女人の作善と鎌倉幕府」展は、下記「鎌倉の伝運慶仏」展と「運慶展 運慶と三浦一族の信仰」展との連携展示として開催されました。
運慶の仏像制作が、源頼朝(みなもとのよりとも)の妻・北条政子や、2代将軍・頼家(よりいえ)と3代将軍・実朝(さねとも)の養育係を務めた大弐局(だいにのつぼね)など、鎌倉幕府の女性たちと密接に結びついていたことを示す展示でした。
たとえば、北条政子が安産祈願をした曹源寺の十二神将立像。
このなかで巳神(ししん)だけがひときわ大きいのですが、これは北条政子が巳の刻(みのこく:午前9時〜11時ごろ)に生まれた実朝の加護を求めたからではないかと考えられています。
また、寿福寺の薬師如来坐像。
この仏像はもともと鶴岡八幡宮のなかにある寺に安置されていたものですが、北条政子が実朝の病気の快癒を願って制作を依頼したもので、運慶工房による作品の可能性が高いそうです。
さらに、称名寺光明院の大威徳明王像。
この仏像は、大弐局がやはり実朝の病気の快癒を願って制作を依頼しました。
運慶仏といえば、東大寺の金剛力士像に代表されるように力強くてマッチョなイメージですが、そうしたイメージとはまた違う運慶仏を鑑賞することができる貴重な運慶展だったようです。
それにしても、実朝の加護を願って仏像制作を依頼したのに、その実朝の病気が快癒することを願ってまた仏像制作を依頼するとは皮肉なものですね。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶展 運慶と三浦一族の信仰
場所:横須賀美術館
期間:2024年10月26日〜12月22日
「三浦一族」とは、平安時代から戦国時代にかけて三浦半島を本拠地とした武士の一族で、鎌倉幕府の創建で大きな役割を果たしました。
そのため、三浦半島には三浦一族に関わる寺院が多く、仏像も数多くつくられました。
三浦一族のうちの1人で、鎌倉幕府の侍所初代別当を務め、2022年のNHK大河ドラマで広く知られるようになった「鎌倉殿の13人」(13人の合議制)の1人でもあった和田義盛(わだよしもり:1147〜1213)が運慶に依頼してつくらせた阿弥陀三尊像、不動明王像、毘沙門天像(以上、浄楽寺)は、そうした仏像の代表です。
「運慶展 運慶と三浦一族の信仰」展では、上記の運慶仏5体の他にも、和田義盛が所持していたと言われる天養院の薬師如来像、南宋からもたらされ、滝見観音の別名をもつ清雲寺の観音菩薩坐像など、全部で9体の運慶仏が展示されました。
当時の三浦一族の権力と財力が窺い知れますね。
なお、「運慶展 運慶と三浦一族の信仰」展は、開幕からわずか20日で観覧者が1万人を突破し、総計で27000人以上の観覧者数となりました。
なお、この「運慶展 運慶と三浦一族の信仰」展は、下記「鎌倉の伝運慶仏」展と、上記「運慶——女人の作善と鎌倉幕府」展との連携展示です。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

鎌倉の伝運慶仏
場所:鎌倉国宝館
期間:2024年10月19日〜12月1日
「鎌倉旧国宝展」と同時開催された特集展示です。
鎌倉幕府ができてから、幕府とのつながりをより深めた運慶は、執権・北条家からの信頼のもと、鎌倉で活発な制作活動を行ないました。
そのため、鎌倉周辺には、運慶が制作したと伝わる仏像が数多く存在します。
そうした仏像のなかから、主に下記の仏像が展示されました。
| 地蔵菩薩立像 | 寿福寺 |
| 地蔵菩薩坐像 | 浄智寺 |
| 弁才天坐像 | 鶴岡八幡宮 |
| 初江王坐像 | 円応寺 |
| 俱生神坐像 | 円応寺 |
| 鬼卒立像 | 円応寺 |
なお、この「鎌倉の伝運慶仏」展は、上記「運慶展 運慶と三浦一族の信仰」展と「運慶——女人の作善と鎌倉幕府」展との連携展示です。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶展:2023年
2023年は、運慶が亡くなってからちょうど800年に当たり、遠忌(おんき)に関連した展示や講演が行なわれました。
運慶の晩年と死をめぐって
場所:半蔵門ミュージアム
期間:2023年12月9日
運慶研究の第一人者で、半蔵門ミュージアム館長の山本勉氏による講演でした。
講演のタイトルは「運慶の晩年と死をめぐって」で、山本勉氏は、運慶の晩年を、京都、奈良、鎌倉という運慶の活動拠点を通して解説しました。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶作の仏像 秋の特別開帳
場所:浄楽寺
期間:2023年10月19日
例年、浄楽寺の「十夜法要の日」に催されているご開帳で、当日限定の御朱印や六佛焼香巡りもあります。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

『運慶 六田知弘写真集』
著者:六田知弘(むだともひろ)
出版社:求龍堂
刊行日:2023年10月3日
『運慶 六田知弘写真集』は、仏教に関する写真集が多い写真家・六田知弘氏による、運慶800年遠忌を記念した写真集です。
運慶の作品、あるいは運慶工房が制作したと考えられる作品に、運慶の父・康慶や、運慶の息子・康弁による作品を加えた97点が掲載されています。
黒背景を基調とし、仏像の特定部分を拡大した写真は、今まで見たことがないようなインパクトが強いカッコイイ作風で、一度見たら是体に忘れられない仕上がりになっていて必見です^^
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶八百年大遠忌 お戻り開帳
場所:浄楽寺
期間:2023年3月3日〜5日
同寺の阿弥陀三尊像、不動明王像、毘沙門天像のご開帳は例年3月3日だけですが、800年遠忌を記念して、ご開帳が3日間に延長されました。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶展:2022年
運慶800年遠忌記念 特別展「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」
場所:神奈川県立金沢文庫
期間:10月7日〜11月27日
1223年に没した運慶の800年遠忌を記念し、横須賀美術館と共同開催した展示会です。
観音菩薩立像・地蔵菩薩立像(満願寺)、不動明王立像・毘沙門天立像(浄楽寺)、不動三尊像(常福寺)、大威徳明王像(運慶作、光明院)など、国や横須賀市に重要文化財に指定された仏像等が展示されました。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶 鎌倉幕府の三浦一族
場所:横須賀美術館
期間:2022年7月6日〜9月4日
上記でご紹介した神奈川県立金沢文庫と共同開催した展示会です。
運慶および運慶工房が制作したと思われる仏像を中心に、同時代の仏像や書跡など約50点の文化財が展示されました。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶展:2018年
運慶 鎌倉幕府と霊験伝説
場所:神奈川県立金沢文庫
期間:2018年1月13日〜3月11日
運慶と鎌倉幕府の関係や、霊験あらたかな仏として運慶仏が信仰されていたことを関連作品を通して紹介する展示会だったようです。
会場では、梵天立像、大威徳明王像、大日如来坐像、阿弥陀如来立像、頬焼阿弥陀縁起絵巻などの重要文化財や最新の研究成果が紹介されました。
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶展:2017年
2017年は、東京国立博物館で開催された運慶展に尽きます!
興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」

場所:東京国立博物館
期間:2017年9月26日〜11月26日
この記事を書いている2025年現在でも、史上最大の運慶展だと言えます。
運慶の父・康慶や息子・湛慶、康弁ら親子3代の作品を展示し、運慶の作風の変遷をたどることができる運慶展でした。
私も行きましたが、ふだんは1方向からしか見られない仏像を、ぐるっと360度あらゆる角度から見ることができるのが楽しかったです^^
あまりに集中して見すぎて、また、えらく混んでいて、やたら疲れてしまったことを覚えています(苦笑)
ちなみに、入場者数は、60万人以上だったそうです(驚)
展示は3章構成で、出品作品は下記のとおりでした——
なお、表中で★印がついている作品は国宝です。
第1章 運慶を生んだ系譜——康慶から運慶へ
| 仏像名 | 作者 | 場所 |
| 阿弥陀如来および両脇侍坐像 | 長岳寺 | |
| 毘沙門天立像 | 奈良・中川寺十輪院伝来 | 東京国立博物館 |
| 地蔵菩薩坐像 | 康慶 | 瑞林寺 |
| 大日如来坐像★ | 運慶 | 円成寺 |
|
運慶願経(法華経巻第八)
|
||
| 仏頭 | 運慶 | 興福寺 |
| 四天王像 | 康慶 | 興福寺 |
| 法相六祖坐像★ | 康慶 | 興福寺 |
第2章 運慶の彫刻——その独創性
| 仏像名 | 作者 | 場所 |
| 毘沙門天立像★ | 運慶 | 願成就院 |
| 五輪塔形銘札★ | 願成就院 | |
| 阿弥陀如来坐像および両脇侍立像 | 運慶 | 浄楽寺 |
| 不動明王立像 | 運慶 | 浄楽寺 |
| 毘沙門天立像 | 運慶 | 浄楽寺 |
| 月輪形銘札(毘沙門天立像納入品) | 浄楽寺 | |
| 地蔵菩薩坐像 | 運慶 | 六波羅蜜寺 |
| 大日如来坐像 | 真如苑真澄寺 | |
| 大日如来坐像 | 光得寺 | |
| 八大童子立像★ | 運慶 | 金剛峯寺 |
| 聖観音菩薩立像 | 運慶・湛慶 | 瀧山寺 |
| 無着菩薩立像・世親菩薩立像★ | 運慶 | 興福寺 |
| 四天王立像★ | 興福寺 | |
| 法眼運慶置文(尊勝寺領近江国香庄文書のうち) | 運慶 | 早稲田大学図書館 |
| 宝篋印陀羅尼経(金剛力士立像納入品)★ | 東大寺 | |
| 大威徳明王坐像 | 運慶 | 光明院 |
第3章 運慶風の展開——運慶の息子と周辺の仏師
| 観音菩薩立像・勢至菩薩立像 | 清水寺 | |
| 多聞天立像 | 東福寺 | |
| 重源上人坐像★ | 東大寺 | |
| 観音菩薩立像・地蔵菩薩立像 | 満願寺 | |
| 四天王立像 | 海住山寺 | |
| 毘沙門天立像・吉祥天立像・善膩師童子立像 | 湛慶 | 雪蹊寺 |
| 神鹿 | 高山寺 | |
| 子犬 | 高山寺 | |
| 善妙神立像 | 湛慶 | 高山寺 |
| 千手観音菩薩坐像光背三十三身像のうち迦楼羅・夜叉・執金剛神★ | 湛慶 | 妙法院 |
| 天燈鬼立像・龍燈鬼立像★ | 康弁(龍燈鬼) | 興福寺 |
| 十二神将立像のうち辰神・巳神・未神・申神・戌神 京都・浄瑠璃寺伝来 | 東京国立博物館 | |
| 十二神将立像のうち子神・丑神・寅神・卯神・午神・酉神・亥神 京都・浄瑠璃寺伝来 | 静嘉堂文庫美術館 |
▼運慶作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓