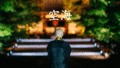2025年9月9日から11月30日まで東京国立博物館で特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』が開催されますが、この運慶展について俳優の高橋一生(たかはしいっせい)さんが熱く語りました!
媒体は、エンタメ特化型情報メディアの「SPICE」(スパイス)。
「高橋一生『場所を体感するのに、知識は必要ない』 特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』インタビュー」という記事です。
運慶展を楽しむための1つの視点を提供してくれていて、初心者の方にもとても役立つ内容となっていますよ^^
▼『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』をくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

▼『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』に行ってきました♪レビューはこちら↓↓↓

高橋一生さんと運慶の関係は?
それにしても、なぜ特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』のことを高橋一生さんが語るのだろう……?
あなたも、そう疑問に思いませんでしたか?
でも、疑問はすぐに氷解。
特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』の広報大使&音声ナビゲーターを高橋一生さんが務めるからです!
はじめは意外や意外と私は思いました。
でも、「美術展ナビ」というサイトのインタビュー記事(2025/06/24)を見ると、高橋一生さんは大の仏像好きのようです。
仏像を観るときは、「仏師のバックグラウンドを重ねながら鑑賞したり、その仏像が誕生した時代に思いをはせたり」しているそうです。
そして、特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』には、「運慶一門が開いた祈りの場がどんなものだったのか、タイムスリップするように体感できることに今からワクワクしています」と、期待感MAXな心境を語っています。
〈それにしても高橋一生さんは、なぜ仏像に関心を持つようになったのだろう?〉
私はそう思いましたが、「美術展ナビ」の記事では、こう語っていました——
おそらく10代後半、祖母が亡くなり、日常的に手を合わせる習慣ができてからだと思います。1日のうちに少しでもそういう時間があることによって心が落ち着きますし、現代の仏師の方の手によるものですが、家に仏像も飾っています。仏像好きで知られるみうらじゅんさんがよく「仏像はウルトラマンの世界観と共通する」とおっしゃっていますけれど(笑)、それもある意味わかるというか、大きな存在と向き合うこと自体が好きなんだと思います。畏敬の念を抱いた瞬間に、そこは祈りの空間になるともいえる。「いただきます」「ごちそうさま」と手を合わせるシンプルなことにも繋がっていますし、おそらく皆さんも知らず知らずのうちになさっていると思いますよ。
やはり高橋一生さんには、仏像に関心を抱く出発点となるような原体験があったんですね。
こうした思いを持っている高橋一生さんなら、特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』の広報大使&音声ガイドに抜擢されても当然です。
では、本題に戻りますが、その高橋一生さんは、「高橋一生『場所を体感するのに、知識は必要ない』 特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』インタビュー」の記事のなかで何を語ったのでしょうか?
以下に、私なりにご紹介してみますね^^
高橋一生、「古都のさらに古都」奈良への深まる愛着
高橋一生さんは昨年(2024年)、法隆寺での仕事をきっかけに奈良に強い縁を感じるようになったそうです。
そして、奈良を「古都のさらに古都」だと思い、飛鳥時代に古神道を大切にしながらも仏教などの外来文化を、決して排他的になることなく受け入れた日本人の特有の感覚に感銘を受けたとのこと。
高橋一生さんは、この「受け入れることでより醸成される」日本文化のあり方を高く評価しています。
なかなか鋭い感性ですね。
高橋一生、運慶仏の魅力と寺外公開が拓く新たな鑑賞空間を語る
高橋一生さんは、〝運慶仏のどこに魅力を感じるか?〟というインタビューアーの質問に対して、運慶とその一派の彫刻が、それ以前の天平彫刻と比べて写実的で力強いと語ります。
運慶の作品が人間の肉体性を重視し、「人間の先に仏がある」という感覚を大切にしている点に魅力を感じているようですね。
たしかに運慶以前の仏像は、人間とは別次元の世界にいる存在のように彫られていたので、高橋一生さんが指摘するような視点を持てば、運慶仏は魅力的に映るだろうなと、私も思いました。
一方で高橋一生さんは、ふだんは現地でしか拝観することができない仏像が、美術館や博物館で「寺外公開」されることの意義を語っています。
とりわけ、ふだんは見ることができない仏像の背後や、光背がない状態で観られることはとても珍しく、さまざまな角度から運慶仏を鑑賞できる貴重な機会であると述べています。
高橋一生さんは、仏像と向き合うと「じっと見られている感覚」を覚え、圧倒的な存在感を感じるそうですが、この運慶展がそのような特別な空間になることへの期待を語っています。
いやあ、特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』の開催が待ち切れなくなってきますね^^
高橋一生が語る、アトラクションとしての仏像空間とは?
高橋一生さんは、お寺で仏像を鑑賞するときは、ただ仏像を見るだけでなく、空間全体が緻密にデザインされていることを強く感じる、と語ります。
その例として法隆寺を挙げ、仏像と対峙する位置や訪問者の感覚までもが計算されていて、特殊な感覚を覚えるそうです。
私は法隆寺には昭和53年に小学校の修学旅行で行っただけなので覚えていないですが、他の寺院に行ったとき、たしかに高橋一生さんが言うように、〈この配置は計算されているなぁ〉と感じることがあります。
そして、高橋一生さんは仏像鑑賞を、当時の人びとが悟りへの境地を体感するための「一種のアトラクション」だととらえ、今回の展示は、それを現代で体験する良い機会であると評価しています。
いやあ、斬新な発想ですね。
高橋一生さんは、ある仏像を見たときに、生きている人間でもないのに〝何かが宿っている〟かのような感覚を覚えたことがあるそうです。
仏像には救済や願いが込められているため、その立体自体が「大きな領域」をつくり出しているように感じられるのではないかと分析しています。
私が思うに、このように感じられるということは、その仏像をつくった仏師、ここでは運慶の想いや魂と共鳴したということなのではないでしょうか。
私もそんな感覚を経験してみたいものです。
高橋一生が語る、運慶仏の体感的仏像鑑賞論
特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』では、音声ナビゲーターを務める高橋一生さん。
鑑賞者の方の邪魔にならないように、なるべく寄り添い、「静かに一緒に見ているような感覚になれる」ようなトーンの音声ガイドになるように努めるとのこと。
なぜなら、映画やドラマを観る前に原作を読む必要がないように、仏像や美術作品も直感的に体験することがもっとも重要で、作品の前に立ち、そこで生まれる感覚や感情、言葉にならない「すごい!」という感覚こそが、鑑賞の醍醐味であると、高橋一生さんは考えているからです。
特に運慶の仏像作品には、知識がなくても鑑賞者を惹きつける説得力があるので、感じること自体を楽しんでほしいと語っています。
そのため、その邪魔をしないような音声ガイドを心がけるのだそうです。
高橋一生さん、よく考えていらっしゃいますね。
まとめ
高橋一生さんの言葉からは、たんなる作品の鑑賞にとどまらず、仏像とその空間、そして自分自身の内面との対話を通じて、歴史や文化、さらには現代社会における精神的な豊かさを追求する姿勢が強く感じられます。
そうした高橋一生さんに倣(なら)いつつ、特別展『運慶 祈りの空間ー興福寺北円堂』が新たな感動や発見を体験するための機会になるといいですね^^
▼過去の運慶展を知りたい方は、こちら↓↓↓

▼運慶の作品についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓