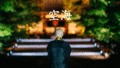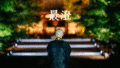歴史の教科書や、お寺を訪れた際に「弘法大師」や「空海」という名前を目にして、「この2人って同じ人なの?」「なぜ名前が違うんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
何を隠そう、私もその1人でした^^;
弘法大師も空海も同じ1人の人物を指していますが、実はこの2つの名前の使い分けにこそ、空海という人物の深い魅力と、空海が今もなお私たちに親しまれつづけている理由が隠されているのです。
この記事では、弘法大師と空海という名前のそれぞれに人びとが込めた想いと意味を、弘法大師・空海の生涯をたどりながら探ってみたいと思います^^
空海から弘法大師へ:時と信仰が育んだ2つの顔
「空海」とは求道者の名
まず、「空海」という名前は、彼が生きていたときに名乗っていた法名(ほうみょう)です。
讃岐国(さぬきのくに:現在の香川県)で生まれた空海は、幼名を真魚(まお)といい、裕福な家庭で育ちました。
私のなかでは、「まお」という名前の音の響きが、空海のイメージにそぐわない感じがします。
どうでもいいことですが……(汗)
真魚は大学で儒学を学びますが、やがて仏教の道に魅せられ、山林での厳しい修行を経て、22歳頃に「空海」と名を改めます。
この「空海」という名には、仏教の深い思想が込められているようです。
「空」は、〝すべてのものは常に変化し、決まった形がない〟という仏教の根本的な教えを表しています。
「海」は、〝仏教の真理がどこまでも広がる智慧の海〟を意味します。
つまり、「空海」とは、仏教の真理を探求し、世に広めつづける1人の求道者の名だったのです。
雄大な名前ですね。
まさに名前のとおりの生き方を空海はしたのだと私は思います。
「弘法大師」とは偉大な功績への称賛の名
一方、「弘法大師」という名前は、空海が亡くなったあと、その偉大な功績を称えて、朝廷から贈られた特別な称号=諡号(しごう)になります。
空海が亡くなったのは835年ですが、この諡号が贈られたのは、それからおよそ90年後の921年のことでした。
「弘法」とは〝仏教の教えを広める〟という意味で、「大師」は〝偉大な僧侶〟に与えられる尊称です。
つまり、「弘法大師」という名前には〝仏教を日本中に広めた偉大な僧〟という意味が込められており、空海が亡きあとも人びとに尊敬され、その功績が語り継がれていた証拠なのです。
このように、「空海」は彼自身が名乗っていた求道者としての名前であり、「弘法大師」は空海の功績を讃えて贈った称号という違いがあるのです。
空海と弘法大師という2つの名前は、1人の人間が時を経て人びとの信仰のなかで特別な存在へと変化していったことを如実に物語っているのです。
これまで何気なく「弘法大師・空海」などと使ってきましたが、このような意味の違いがあったんですね!
留学から開山へ:空海が歩んだ求道の旅
空海は、仏教を極めるため、31歳のときに遣唐使の一員として唐へ渡りました。
その地で空海は、密教の正統な後継者である恵果阿闍梨(けいかあじゃり)と運命的な出会いを果たします。
恵果は、一目見て空海の才能を見抜き、ふつうなら伝授するのに数十年かかる密教の教えを、わずか半年ですべて伝授しました。
すぐに空海の才能を見抜いた恵果もすごいですが、半年で密教のすべてを身につけた空海はほんとうにすごいですね!
空海は、恵果から「遍照金剛」(へんじょうこんごう)という灌頂名(かんじょうみょう)を与えられ、密教の第八祖となります。
「遍照金剛」とは〝この世の一切を遍(あまね)く照らす者〟という意味です。
密教の最高仏である大日如来をも意味します。
そして、空海は、膨大な経典や仏画、密教法具を携えて帰国し、日本に真言密教を確立しました。
帰国後、空海は嵯峨天皇から京都の東寺(とうじ)を賜り、都での布教の拠点としました。
同時に、厳しい修行にふさわしい場所として、現在の和歌山県の高野山(こうやさん)に、もう1つの拠点をつくります。
こうして空海は、真言宗の教えを広めていきました。
バイタリティーあふれる空海の姿が目に浮かびます。
なお、高野山は、空海が入定(にゅうじょう:肉体を持ったまま深い瞑想に入り、仏となること)の地とした場所となりました。
▼空海の生涯についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

仏教だけじゃない!弘法大師・空海が残した偉業と伝説
空海が弘法大師として人びとから深く親しまれている理由は、仏教の教えを広めただけにとどまりません。
弘法大師・空海の偉業は、教育、文化、土木事業など、多岐にわたります。
教育者としての顔
弘法大師・空海は、身分に関係なく誰もが学べる日本初の庶民のための学校「綜藝種智院」(しゅげいしゅちいん)を設立しました。
仏教だけでなく、さまざまな学問を教えたことから、現代の総合大学の先駆けだと言えます。
書道の大家としての顔
弘法大師・空海は、日本の書道の歴史を語るうえで欠かせない「三筆」(さんぴつ)の1人に数えられています。
「三筆」とは、弘法大師・空海、嵯峨天皇(さがてんのう)、橘逸勢(たちばなのはやなり)の3人です。
弘法大師・空海の書は力強く流麗で、「弘法にも筆の誤り」「弘法筆を選ばず」ということわざが生まれるほど、書道に大きな影響を与えました。
土木技術者としての顔
弘法大師・空海は、僧侶でありながら、土木技術者としても卓越した才能を発揮しました。
とりわけ、香川県の満濃池(まんのういけ)の修復工事を短期間で成功させ、人びとの暮らしを救った功績は、今も語り継がれています。
▼空海が修復した満濃池についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

これらの偉業からわかるのは、弘法大師・空海は人びとの生活に寄り添い、社会に大いに貢献したということです。
弘法大師・空海の行動の1つ1つが、仏教の教えを広めるだけでなく、人びとの苦しみを和らげ、より良い社会を築く土台となっていったのです。
だから人びとは、弘法大師・空海をただの僧侶ではなく、救いの存在として深く敬うようになっていったのでした。
弘法大師・空海は今も生きている?現代に伝わる信仰
弘法大師・空海は、多くの人びとに深く親しまれています。
その大きな理由の1つとして、弘法大師・空海が〝今も生きている〟と信じられていることが挙げられるでしょう。
真言宗では、空海は亡くなったのではなく、高野山の奥の院で永遠の瞑想に入っている=「入定」(にゅうじょう)していると信じられています。
そのため、高野山の奥の院にある「弘法大師御廟」(こうぼうだいしごびょう)では、今も毎日欠かさず朝と昼に食事が供えられています。
この儀式は「生身供」(しょうじんぐ)と呼ばれますが、弘法大師・空海が今も世の中の平和を願い、修行を続けていると信じる人びとの想いの表れなのです。
▼空海に食事を供する生身供についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

また、四国八十八ヵ所めぐり、通称「お遍路」では、遍路者たちは「同行二人」(どうぎょうににん)という言葉を胸に、弘法大師・空海が常に自分といっしょに歩んでくれていると感じながら旅をします。
四国の人びとが遍路者を温かくもてなす「お接待」という文化も、「遍路者は弘法大師の分身」という信仰から生まれたものです。
このように、「弘法大師」という名前には、数々の伝説や信仰が重なっています。
弘法大師・空海は、よく「お大師さま」と呼ばれますが、この呼び方には、たんなる歴史上の人物を超え、今も私たちを見守ってくれているという親しみが込められているのです。
まとめ
弘法大師と空海は、時と信仰の移り変わりに応じて使い分けられた、1人の偉大な人物の2つの顔でした。
その生涯や偉業、そして現代にまで続く信仰を知ることで、私たちは弘法大師・空海の人物像をより深く理解し、なぜ今もなお数多くの人びとに愛され、親しまれているのかを垣間見ることができるでしょう。
▼空海について広く知りたい方は、こちら↓↓↓