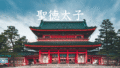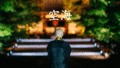奈良時代、日本の歴史に大きな影響を与えた行基(ぎょうき)と鑑真(がんじん)。
行基と鑑真は、それぞれまるで異なる背景と立場で日本仏教の発展に貢献しました。
行基は民衆に寄り添い、一方の鑑真は仏教界の基盤を築くために海を渡りました。
同じ仏の道を歩みながらも、その生涯や功績は明らかに異なります。
今回は、そんな二人の人生をたどり、行基と鑑真の決定的な違いについて、徹底比較していきます^^
行基と鑑真はどっちが先?
歴史を紐解くうえで、まず気になるのは、〝どちらが先に活躍したのか?〟という点ですよね。
先に結論を言うと、行基が鑑真よりも先に生まれ、先に亡くなっています。
行基は668年生まれで、749年に亡くなりました。
行基の主な功績は、奈良時代初期の民衆への布教や社会事業、そして東大寺の大仏建立への協力です。
一方、鑑真は688年頃の生まれで、763年に亡くなりました。
鑑真が日本へやってきたのは、行基が亡くなったあとの753年です。
つまり、行基が亡くなった約4年後に、鑑真はようやく日本にたどり着いたことになります。
2人の生きた期間がまるで重なっていないのは少し意外でした。
行基と鑑真の人生を時間に即して見ると、行基が日本の社会基盤を整え、民衆に仏教の広がりをもたらしたあとに、鑑真が日本仏教の制度を確立するために来日した、という流れになります。
二人の功績は直接的な協力関係にはありませんが、この時間の流れを考えると、行基が民衆に仏教を根づかせた土壌の上に、鑑真がより厳格な仏教の秩序を築き上げた、と捉えることができます。
生きた時期は重なっていなくても、その功績には連続性があったのですね。
行基:民衆に寄り添った社会事業家
行基は、奈良時代に活躍した(朝鮮半島を起源とする渡来系)日本人の僧です。
行基は、仏教がまだ貴族や皇族のためのものであった時代に、その常識を打ち破った人物です。
朝廷から正式な僧の資格を得ずに、寺院の外に出て民衆に布教活動を行い、社会事業を進めたことで知られています。
行基の活動は、まるで現代のボランティア活動の先どりだと言えるでしょう。
橋や道、水路、港といったインフラを整備し、貧しい人びとのための救護施設「布施屋」(ふせや)を建設するなど、人びとの暮らしを直接的に豊かにする事業に尽力しました。
農民たちが田畑を耕し、収穫物を京へ運ぶための道や、平城京建設で働く人々を支援する施設を造るなど、まさに〝人びとのための仏教〟を体現していたのです。
しかし、この行基の活動は、「僧尼令」(そうにりょう)という法令に違反するとされ、弾圧されてしまいます。
当時の仏教は国を守るためのものであり、民衆への布教は国の税収を減らす〝不都合な事態〟とみなされていたのです。
この不条理な弾圧にもかかわらず、行基は決して挫(くじ)けませんでした。
国からの弾圧を無視して、民衆からの絶大な支持を背景に活動を続けます。
すごい精神力ですね。
長いものには巻かれろ式の人間とは正反対です。
やはり並の僧侶ではありません(汗)
困難に直面しても、自分の信念を貫き通す行基の姿勢は、現代を生きる私たちも見習うべき点かもしれません。
そして、運命の転機が訪れます。
度重なる飢饉(ききん)や天災で混乱していた国を仏教の力で安定させようと考えた聖武天皇は、東大寺の大仏建立を計画します。
しかし、大仏を造るには莫大(ばくだい)な人手が必要でした。
ここで白羽の矢が立ったのが、民衆からの絶大な支持を得ていた行基でした。
かつて自分を弾圧した朝廷からの依頼にもかかわらず、行基は快くこれに応じ、各地を回って大仏建立の協力を募(つの)りました。
自分を弾圧した朝廷からの要請を受けるなんて、やっぱり行基は並の僧侶とは大違いです!
〝仏の教えによって民衆を救う〟という立場に徹していたから、そんなこと取るに足りないことだったのかもしれませんね。
「行くぞ!大仏と民のために!」
そう行基は呼びかけ、数多くの人びとが大仏造立に力を貸したと言われています。
その功績が認められ、行基は日本人で初めて「大僧正」という僧侶の最高位を与えられました。
弾圧された身から、国の最高位に上り詰めるなんて、人生の大逆転劇!
行基の功績は、今なお日本各地に伝説として語り継がれています。
鑑真:命を賭して戒律を伝えた求道者
一方の鑑真は、招かれて唐からやってきた高僧でした。
そして、日本の仏教界に〝秩序〟をもたらします。
当時の日本には、正式な僧侶になるための「授戒」という儀式が行われていませんでした。
つまり、「私は僧侶である!」と宣言すれば、誰でも僧侶になれるという〝無秩序〟な状態だったのです。
これでは仏教の教えが正しく伝わらないと考えた日本の仏教界は、遣唐使を通じて、唐の国にいた鑑真に日本へ来てもらえるよう懇願します。
鑑真は、唐の皇帝からも才能豊かで博識高い僧侶として認められており、日本へ行くことを止められていました。
しかし、鑑真は、日本の僧侶たちの必死の願いを聞き入れ、危険を冒して日本へ渡ることを決意します。
日本への道のりは、想像を絶するほど困難でした。
嵐による船の難破、仲間からの裏切り、投獄など、なんと5回も渡海に失敗します。
鑑真は失明という悲劇に見舞われますが、それでも渡海を諦めませんでした。
6度目の挑戦で、ようやく日本の地に降り立ったときには、来日を決意してからすでに約20年もの歳月が流れていました。
仏教の教えを伝えるという使命のために、すべてを投げ打って困難に立ち向かった鑑真の姿は、まさに求道者そのものです。
失明してもなお、その志を曲げなかった鑑真の強い精神力には、ただただ脱帽です。
日本に到着後、鑑真は奈良の東大寺に「戒壇」という授戒の場を設け、日本の僧侶たちに正しい戒律を授けました。
聖武天皇も鑑真から授戒を受け、日本の仏教界に正式なルールが確立されました。
もしも鑑真が来日していなかったら、日本の仏教は混乱したままだったかもしれません。
つまり、鑑真は、日本仏教の基盤を築き、その後の発展の土台を築いたのです。
鑑真の功績はそれだけにとどまりません。
鑑真は、食文化や建築技術といった大陸の進んだ文化も日本にもたらしました。
私たち現代人がふだん食している味噌や豆腐をはじめ、漢方の知識は、鑑真が日本へ来なければ、日本に存在していなかったかもしれないのです。
鑑真って、日本の文化全体に深い影響を与えていたんですね。
鑑真さまさまです^^
行基と鑑真の違い:方向性と影響力
行基と鑑真には、いくつかの点で違いがあります。
その違いを表としてまとめると、以下のようになります――
| 項目 | 行基 | 鑑真 |
| 国籍 | 朝鮮からの渡来系日本人 | 唐人(中国から来た人) |
| 貢献内容 | 日本国内のインフラ制度を整え、社会事業に貢献 | 日本の仏教の制度を整え、大陸のものをもたらした |
| 生きた時代 | 668年〜749年(奈良の大仏完成前に亡くなる) | 688年頃〜763年(行基の死後に来日) |
| 僧侶としての立場 | 家柄は高くない。国に弾圧されるも、後に大僧正となる | 唐の皇帝にも一目置かれたエリート。日本の朝廷から来日を懇願される |
行基が貢献したのは、仏教を広く民衆のものにした点です。
行基の社会事業は、仏教が一部の特権階級のためのものでなく、すべての人びとを救うものであるという考えを定着させました。
これにより、日本の社会全体に仏教が根づくきっかけが生まれたのです。
一方、鑑真が貢献したのは、仏教を〝正しいもの〟にした点です。
鑑真がもたらした戒律は、日本の仏教界に規律と資格制度を確立させ、後世の仏教の健全な発展を可能にしました。
もしも鑑真が来日していなかったら、日本の仏教はルールのない無秩序な状態のままだったかもしれません。
では、行基と鑑真が行なったことは、どちらが重要なのでしょうか?
これは〝愚問〟(ぐもん)です。
なぜなら、評価の基準を「仏教を広める」か「仏教のルールを整える」かのどちらに置くかで変わってくるからです。
というよりも、行基と鑑真の行なったことは、どちらも重要です!
行基と鑑真という二人の偉人の存在が、日本仏教をより深く、そして豊かなものに成長させたことは間違いないからです。
二人がそれぞれ違う方向性で力を尽くし、異なった影響力を与えたからこそ、今日の日本仏教があると言えるのではないでしょうか。
行基と鑑真の覚え方
最後に、行基と鑑真の違いをテストや勉強で効率よく覚えるため、役立つ覚え方をご紹介します^^
行基の覚え方:「行くぞ!大仏と民のために!」
行基は民衆に仏教を広め、東大寺の大仏造立にも協力しました。
行基の行動的な側面と功績を合わせて覚えることで、頭に残りやすくなります。
行基が率先して人びとのために行動した様子が目に浮かぶようで、覚えやすいですね^^
鑑真の覚え方:「カン(鑑真)ペキな戒律!」
鑑真は、日本に戒律をもたらしました。
だから、鑑真を「カンペキな戒律」(=仏教のルール)を伝えた人と覚えれば、行基と区別しやすくなります。
また、鑑真の壮絶な来日の物語も、語呂合わせにはピッタリです。
「ガン(鑑真)ばって6回目で成功!」というのはいかがでしょうか。
鑑真の不屈の精神を象徴する語呂合わせですね。
これらの覚え方を活用し、二人の偉人の功績と違いをしっかりと頭に入れ、歴史の勉強に役立ててください^^
まとめ
- 行基は、民衆に仏教を広め、橋や道といった社会事業に尽力した
- 行基は、当初は朝廷に弾圧されたものの、東大寺の大仏建立に協力した功績が認められ、日本人で初めて最高位の僧「大僧正」となった
- 鑑真は、日本の仏教界を立て直すため、失明しながらも、6度目の渡海で来日を果たした
- 鑑真は、日本に正式な僧となるための戒律を伝え、日本仏教の基盤を築いた