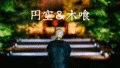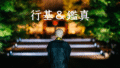「聖徳太子の地球儀」は、飛鳥時代に聖徳太子がつくったオーパーツなのか?――
この記事にアクセスされたあなたは、そんな疑問への〝答え〟を求めているにちがいありません。
先に〝答え〟を言ってしまうと、「いいえ」です。
「聖徳太子の地球儀」が飛鳥時代に聖徳太子によってつくられた可能性はきわめて低いと言わざるをえません。
のっけからロマンがしぼんでしまいそうなことを言ってしまいましたね……(汗)
では、なぜそう言えるのか?
徹底解説していきます。
「聖徳太子の地球儀」がオーパーツだと言われるワケは?
聖徳太子(574-622)といえば、冠位十二階や十七条憲法を制定した日本史の重要人物です。
どんなに日本史が苦手な人でも、聖徳太子の名前を知らない人はいないと思います。
ただし、「聖徳太子」という名称は死後に与えられたので、今では、生前の「厩戸皇子」(うまやどのみこ)「厩戸王」(うまやどのおう)という名称で呼ばれることが多くなってきました。
聖徳太子が超人的な能力を持っていたという伝説は多く、一度に10人の話を聞き分けたというエピソードはあまりにも有名です。
そんな聖徳太子ゆかりの宝物として、聖徳太子創建の寺として知られる兵庫県太子町の斑鳩寺(いかるがでら)に伝わるのが、いわゆる「聖徳太子の地球儀」です。
正式には「地中石」(ちちゅうせき)」と呼ばれるこの球体は、直径約10センチのソフトボールくらいの大きさで、表面にはデコボコとした突起とくぼみがあり、それが大陸と海を形どっているように見えます。
そのため、古くから地球儀ではないかと推測されてきました。
「聖徳太子の地球儀」がミステリーとして語られる最初の理由は、聖徳太子が生きていた7世紀の日本には、地球が丸いという概念そのものが広まっていなかったと考えられるからです。
それどころか、「聖徳太子の地球儀」には、15世紀に発見されたアメリカ大陸や、1820年代に発見された南極大陸まで描かれているのです!
常識的に考えれば、聖徳太子の時代に、こうしたことを知るのは不可能です。
そのため、「聖徳太子の地球儀」は、時代にそぐわない技術や知識が使われた「オーパーツ」(Out of Place Artifacts)として関心の的となってきました。
これまで、ロマンをかき立てられる人が多勢いたにちがいありませんね。
「聖徳太子の地球儀」の正体を科学と歴史の視点から解明!
実は、「聖徳太子の地球儀」の正体を探るため、科学的な調査が行われたことがあります。
その結果、「聖徳太子の地球儀」の材質は石ではなく、漆喰(しっくい)であることが判明しました。
漆喰とは、石灰を主成分とし、壁材などにも使われる建築素材です。
さらに詳しく分析すると、その漆喰には海藻糊(かいそうのり)が混ぜられていることがわかりました。
海藻糊を混ぜる技法は、日本の戦国時代以降、特に江戸時代になってから広く用いられるようになったものです。
つまり、「聖徳太子の地球儀」は、聖徳太子が生きていた飛鳥時代の作である可能性がきわめて低いことがわかりました。
また、「聖徳太子の地球儀」の南極大陸に相当する部分には、「墨瓦臘泥加」(メガラニカ)という文字が墨で書かれていることが明らかになりました。
「メガラニカ」とは、16世紀に世界一周航海を成し遂げた探検家マゼランにちなんで名前がつけられた想像上の南方大陸のことです。
古代ギリシアから存在すると信じられてきましたが、世界地図に描かれるようになったのは大航海時代のあとになります。
日本に初めて西洋の正確な世界地図が伝わったのは、17世紀初頭のことです。
この地図に「メガラニカ」は描かれています。
こうした歴史的事実を考えても、「聖徳太子の地球儀」が飛鳥時代につくられたものではないことがわかります。
「聖徳太子の地球儀」はいつ誰がつくったのか?
では、「聖徳太子の地球儀」は、いつ誰がつくったのでしょうか?
斑鳩寺に伝わる宝物目録『常什物帳』(じょうじもつちょう)には、江戸時代の安政年間(1854-1860)に「地中石」として記載されているので、少なくともその頃には存在していたと考えられます。
さらに、「聖徳太子の地球儀」に描かれた地形は、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』(わかんさんさいずえ:1712年)に掲載されている「山海輿地全図」(さんかいよちぜんず)ととてもよく似ていることが指摘されています。
『和漢三才図会』は、日本の医師であった寺島良安(てらしま・りょうあん)が編纂したもので、西洋の知識も多く取り入れられていました。
このことから、「聖徳太子の地球儀」は寺島良安、もしくは彼が編纂した地図を参考にした何者かによって、江戸時代中期につくられたという説がもっとも有力視されています。
それでも謎は残る!「聖徳太子の地球儀」に描かれた〝謎の大陸〟の正体とは?
科学的な調査と歴史的背景から、「聖徳太子の地球儀」は聖徳太子がつくったものではなく、江戸時代につくられたものだと考えられます。
しかし、それでもなお、オーパーツ説がささやかれる大きな理由が1つ残されています。
それは、「聖徳太子の地球儀」上の太平洋の真ん中に〝謎の大陸〟が描かれていることです。
これを「ムー大陸」ではないかと考える人がいます。
「ムー大陸」とは、1万2000年以上前に太平洋に存在したとされる伝説の古代大陸です。
この伝説は20世紀初頭に提唱されたもので、『和漢三才図会』が編纂された江戸時代に知る人は誰もいなかったはずです。
なぜ、江戸時代につくられた地球儀に、200年以上もあとの時代に提唱される伝説の大陸が描かれているのでしょうか?
この不可解な点こそが、「聖徳太子の地球儀」をオーパーツではないかと信じさせている最大の謎なのです。
この謎については、ムー大陸の存在を信じる人びとのロマンを掻き立てる一方で、その正体を合理的に考察する見解も存在します。
それは、この〝謎の大陸〟が、フィリピンやインドネシア、ミクロネシアなどの島々をデフォルメして表現したものではないかという説です。
漆喰で立体的な球体をつくるにあたっては、大陸の凹凸は全体にバランスよく配置されている方が作業しやすいという側面があります。
「聖徳太子の地球儀」では、日本列島やその南にある島々が本来の位置からずれていたり、大きく表現されていたりすることが確認されています。
そのため、太平洋の真ん中にある〝謎の大陸〟が、まるでムー大陸のように見えているというのです。
とはいえ、この謎に満ちたデコボコを前にしたとき、合理的・科学的な判断をするか、あるいは、オーパーツ説を素直に信じるか、それとも、まだ誰も知らないことを知ることができる聖徳太子の超人的な知覚能力を夢想するか、その〝答え〟はきっと見る人によって異なるのだと思います。
「聖徳太子の地球儀」には江戸時代の知恵とロマンが詰まっている
「聖徳太子の地球儀」は、材質や歴史的背景から見ても、聖徳太子がつくったものではないと言えます。
一方で、「聖徳太子の地球儀」は別の見方ができるでしょう。
江戸時代に日本人がどれだけ西洋の知識に興味を持ち、それを自分たちの手で表現しようとしたのか――
「聖徳太子の地球儀」は、そうした先人の努力を示す貴重な遺物だと思うのです。
「〝謎の大陸〟は本当にムー大陸ではないのか?」――謎はかすかに残りますが、その最大のミステリーがあるからこそ、「聖徳太子の地球儀」は今も多くの人びとを惹きつけているのかもしれません。
「聖徳太子の地球儀」は、たんなる古美術品ではなく、聖徳太子の超人伝説と、遠い時代の人びとの知的好奇心とロマンが詰まった、まさにタイムカプセルのような存在なのではないでしょうか。
▼聖徳太子が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子の死因は病気?暗殺?詳しくはこちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子実在説vs.非実在説を徹底解説!詳しくはこちらをクリック↓↓↓

▼聖徳太子が10人の話を聞き分けられたって本当?真偽が気になる方はこちらをクリック↓↓↓