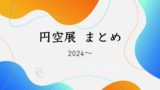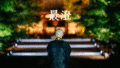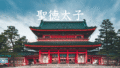鋭いノミ跡が力強い仏像をつくった円空(えんくう)と、丸みを帯びた優しげな仏像をつくった木喰(もくじき)。
まるで対照的な仏像を残した2人の僧は、江戸時代を代表する「作仏聖」(さぶつひじり)あるいは「造仏聖」(ぞうぶつひじり)として並び称されています。
円空と木喰の仏像は、時代を超えて今も多くの人びとを魅了しつづけています。
この記事では、円空と木喰の生涯と作品の違いを比較し、その魅力の核心に迫ってみたいと思います^^
円空と木喰:生涯と活動の違い
円空は1632年、美濃国(現在の岐阜県)で生まれました。
一方の木喰は1718年、甲斐国(現在の山梨県)で生まれました。
生まれた年は86年、活躍した時期はほぼ100年違います。
でも、それぞれの仏像が庶民に受け入れられたという点で、円空と木喰は共通しています。
円空:悟りを求めて旅を続ける修験者
円空は20代のころ、修験者として厳しい修行を積み、白山信仰に出会いました。
白山信仰は山そのものをご神体とする山岳信仰で、円空が多くの仏像を残した寺は、白山信仰と深い関わりがありました。
円空は寺を持たず、各地を放浪しながら仏像を彫る遊行僧(ゆぎょうそう)=「作仏聖」(さぶつひじり)や「造仏聖」(ぞうぶつひじり)と呼ばれる仏師として活躍しました。
幕府からは差別される対象でしたが、一般庶民にとってはありがたい存在として受け入れられ、たくさんの交流エピソードが残っています。
円空は32歳で初めて記録に残る仏像を彫り、生涯に12万体の造仏を発願しました。
59歳で10万体を達成したとの遺文があり、現在までに5400体以上の円空仏が確認されています。
64歳で母が眠る地で即身仏となって入定したとされています。
▼円空の生涯についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

木喰:遅咲きながら、ひたすら造像に励んだ生涯
一方、木喰は、61歳という高齢になってから本格的に造像を始めました。
これまでは北海道に渡った時からとされていましたが、最近の研究でそれ以前に制作された像が青森で発見されるなど、定説を覆すような新事実が出てきています。
93歳で亡くなるまでの32年間で2000体の造像を発願し、そのうち約720体が現存しています。
木喰もまた、円空と同じように各地を巡りながら仏像を彫る旅を続けました。
自分自身を象(かたど)った「自身像」を15体も残しており、ふっくらとした顔つきと微笑みをたたえた表情が特徴的です。
円空と木喰の作品の違い:鋭いノミ跡とやさしい微笑み
円空と木喰の仏像の作風はどちらも特徴的で、明確な違いが見られます。
円空仏:素材のいのちを活かした力強い造形
円空の仏像は、鋭いノミ跡をそのまま残した力強い造形が特徴です。
円空は、素材が持つそのままの状態の「生成り」(きなり)を大切にし、木の筋目や節、曲がりといった自然な形を最大限に活かして彫り上げました。
ノコギリを使わず、鉈(なた)やノミで断ち割るように彫っていったと考えられています。
たとえば、栃木県日光市の清瀧寺にある不動三尊像は、朽(く)ちた木をそのまま火焔光背(かえんこうはい)として利用しており、円空ならではの発想がよく表現されています。
また、三重県の明福寺の薬師如来と阿弥陀如来の両面仏は、一つの木に二つの仏を彫り込む珍しい像となっています。
円空は、仏教を知らない人びとに対し、自然に逆らわない生き方の尊さを説いており、その思想が仏像の姿として表現されていると私は思います。
▼円空仏の特徴について知りたい方は、こちら↓↓↓

木喰仏:庶民に寄り添う微笑み
木喰の仏像は、円空仏とは対照的に、丸みを帯びた優しげな表情が特徴です。
民芸運動を推進した柳宗悦(やなぎ・むねよし)は、慈悲深い微笑みをたたえている木喰仏を「微笑仏」(びしょうぶつ)と呼びました。
木喰仏はとても丁寧に作り込まれており、ふっくらとした顔つきで、見る人の心を安らかにするような優しい表情をしています。
また、木喰仏は庶民の暮らしに溶け込んでいました。
たとえば、新潟県長岡市の金毘羅堂(こんぴらどう)に伝わる木喰自身像は、子どもたちのソリになって頭がすり減ってしまったそうです(笑)
また、「ご利益があるにちがいない」と、木喰仏の頭を削って煎(せん)じて飲んだというエピソードもあり、木喰仏が人びとにいかに深く愛されていたかがわかります。
円空仏と木喰仏の共通点は庶民に愛されたこと!
ここまで、円空と木喰の生涯と作品の違いを見てきました。
一方、円空仏と木喰仏には共通点もあります。
私が思うに、最大の共通点は、円空仏も木喰仏も〝人びとの暮らしに寄り添い、祈りを形にした存在〟であることです。
現代の仏像が美術品として厳重に管理されているのとは対照的に、円空仏と木喰仏は、どちらも人びとの生活のなかに当たり前のように存在していました。
木喰仏は、すでにご紹介したように、ワルガキたちがソリにしたり、村人が頭を削って飲んでしまったりしました。
一方の円空仏は、そこまでの扱われ方はされなかったようですが(笑)、山奥の人気のない祠(ほこら)のなかに、ホコリをかぶってひっそりと祀(まつ)られたりしていました。
こう聞くと、円空仏も木喰仏も、なにやらぞんざいに扱われていたように思えますが、これはそれほどまでに庶民と分かちがたく結びついていたことの証(あかし)だと私は思うのです。
円空仏の持つ力強い生命力は、自然と共生し、そのあるがままを受け入れる日本の精神性を体現しているように思われます。
また、円空自身の悟りや修行の跡が色濃く反映されているようにも思えます。
一方、木喰仏の優しい微笑みは、人生の苦難を乗り越え、安らかさを求める人びとの心に、静かに寄り添ってきたように思われます。
また、人びととの交流や、彼らが抱える喜怒哀楽を写し取ったかのようにも思えます。
円空仏にも木喰仏にも、見る者の心に語りかけてくる強い力が感じられます。
それは、円空も木喰も名声や富のためではなく、ただひたすらに人びとの救済を願って仏を彫ったからに違いないからだと思います。
円空と木喰が現代に遺したものは、たんなる美術品ではなく、日本人が昔から大切にしてきた素朴な信仰心そのもののような気がします。
円空と木喰の仏像に触れることで、私たちは忘れかけていた心の安らぎや、自然への畏敬の念を思い出すことができるのではないでしょうか。
まとめ
江戸時代に活躍した2人の作仏聖、円空と木喰は、対照的な作風の仏像を制作しました。
▼円空(1632-1695)
- 鋭いノミ跡が特徴の力強い仏像を制作
- 遊行僧として各地を放浪し、生涯に12万体の造仏を発願
- 素材の自然な形を活かした作風が特徴
▼木喰(1718-1810)
- 丸みを帯びた優しげな「微笑仏」を制作
- 61歳から本格的に造仏を始め、93歳で亡くなるまでに約2000体の造仏を発願
- 庶民の生活に寄り添い、愛された仏像を数多く制作
2人の仏像は、作風こそ異なりますが、どちらも名声や富のためではなく、人びとの救済を願って彫られたものであり、人びとの暮らしに深く根ざした「祈りの形」としての魅力を持っています。
▼2024年以降に開催された円空展のまとめは、こちら↓↓↓