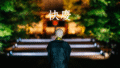平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した「天才仏師」こと運慶。
その名はよく知られていても、いったい運慶がどんな作品を残したかをよく知る方は少ないのではないでしょうか。
このページでは、運慶の作品を一覧にし、どの場所に安置されていて、何が国宝で、運慶作品にはどのような特徴があるかをご紹介します♪
運慶作品を一覧でご紹介!
運慶は生涯にわたり、数多くの仏像を彫りました。
その数、運慶作品だと推定される仏像を含め、80体以上!
デビュー作の大日如来坐像は1176年に完成しているので、亡くなる1223年までの47年のあいだに、年間1、2体は仏像をつくっていた計算になります。
すごいバイタリティーです!
そんな運慶作品のうち、運慶作だと確定、あるいは運慶作の可能性が高い仏像31体を一覧にしました!
運慶作品一覧全31体
| 栃木 | 光得寺 | 大日如来坐像(重要文化財) |
| 東京 | 真如苑 | 大日如来坐像(重要文化財) |
| 神奈川 | 浄楽寺 | 阿弥陀三尊像(重要文化財):3体(阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩) |
| 神奈川 | 浄楽寺 | 不動明王立像(重要文化財) |
| 神奈川 | 浄楽寺 | 毘沙門天立像(重要文化財) |
| 神奈川 | 称名寺光明院 | 大威徳明王像(重要文化財) |
| 静岡 | 願成就院 | 阿弥陀如来坐像(国宝) |
| 静岡 | 願成就院 | 不動明王立像(国宝) |
| 静岡 | 願成就院 | 二童子立像(国宝):2体(矜羯羅童子、制吒迦童子) |
| 静岡 | 願成就院 | 毘沙門天立像(国宝) |
| 愛知 | 瀧山寺 | 聖観音菩薩(重要文化財) |
| 愛知 | 瀧山寺 | 梵天・帝釈天立像(重要文化財) |
| 京都 | 六波羅蜜寺 | 地蔵菩薩坐像(重要文化財) |
| 奈良 | 円成寺 | 大日如来坐像(国宝) |
| 奈良 | 東大寺 | 南大門 金剛力士立像(国宝):2体(阿形、吽形) |
| 奈良 | 東大寺 | 俊乗堂 俊乗上人(俊乗房重源)坐像(国宝) |
| 奈良 | 興福寺 | 北円堂 弥勒如来坐像(国宝) |
| 奈良 | 興福寺 | 北円堂 無著菩薩・世親菩薩立像(国宝) 2体 |
| 奈良 | 興福寺 | 木造仏頭(重要文化財) |
| 和歌山 | 金剛峯寺 | 八大童子立像(国宝)*1 |
*1:8体のうちの6体が運慶作品(恵光童子、恵喜童子、烏俱婆伽童子、清浄比丘童子、矜羯羅童子、制多伽童子)
なお、最近の調査と研究により、興福寺北円堂の四天王像(持国天、増長天、広目天、多聞天)4体(国宝)を加えて、35体とする見方もあります。
運慶作品31体はどんな仏像?わかりやすく解説
運慶作品31体は、実際にはどのような仏像で、どんな成り立ちや特徴があるのでしょうか?
運慶は主に鎌倉幕府の要人をはじめ、東国武士のために仏像を制作しました。
仏像の種類は、大日如来や阿弥陀如来、観音菩薩、不動明王、金剛力士像など、さまざま。
仏像の大きさも、30cmくらいの小ぶりなものから8m超えの巨大なものまで、いろいろです。
また、上記運慶作品31体を制作順に並べ替えると次のようになります——
| 円成寺 | 大日如来坐像 |
| 願成就院 | 阿弥陀如来坐像、不動明王立像、矜羯羅童子立像、制吒迦童子立像、毘沙門天立像 |
| 浄楽寺 | 阿弥陀如来坐像、観音菩薩立像、勢至菩薩立像、不動明王立像、毘沙門天立像 |
| 真如苑 | 大日如来坐像 |
| 光得寺 | 大日如来坐像 |
| 金剛峯寺 | 八大童子立像(うち6体) |
| 六波羅蜜寺 | 地蔵菩薩坐像 |
| 瀧山寺 | 聖観音菩薩立像、梵天立像、帝釈天立像 |
| 東大寺 | 金剛力士立像(阿形、吽形) |
| 東大寺 | 重源上人坐像 |
| 興福寺 | 弥勒如来坐像、無著菩薩立像、世親菩薩立像、木造仏頭 |
| 称名寺光明院 | 大威徳明王像 |
このうち、とりわけ有名なのが、運慶のデビュー作である円成寺の大日如来坐像。
そして、東大寺南大門の金剛力士立像(阿形、吽形)。
さらに、興福寺の無著菩薩立像と世親菩薩立像です。
〝死ぬまでに一度は観ておきたい仏像〟と言っても過言ではありません。
興味がある方は、下記リンク先ページでくわしくご紹介しているので、ぜひごらんください^^

運慶作品の可能性が中程度以下の仏像一覧
運慶の作品の可能性が中程度以下の仏像も一覧にしてみましょう!
| 東京 | 五島美術館 | 愛染明王像 |
| 神奈川 | 満願寺 | 観世音菩薩像 |
| 神奈川 | 満願寺 | 地蔵菩薩像 |
| 神奈川 | 円応寺 | 閻魔大王像 |
| 神奈川 | 教恩寺 | 阿弥陀如来像 |
| 神奈川 | 教恩寺 | 観音菩薩像 |
| 神奈川 | 教恩寺 | 勢至菩薩像 |
| 神奈川 | 杉本寺 | 十一面観音像 |
| 神奈川 | 杉本寺 | 地蔵菩薩像 |
| 神奈川 | 杉本寺 | 仁王像 |
| 神奈川 | 補陀洛寺 | 日光菩薩像 |
| 神奈川 | 補陀洛寺 | 月光菩薩像 |
| 神奈川 | 光触寺 | 阿弥陀如来像 |
| 神奈川 | 東光禅寺 | 薬師如来像 |
| 長野 | 仏法紹隆寺 | 不動明王像 |
| 静岡 | 蓮台寺 | 大日如来像 |
| 愛知 | 瀧山寺 | 鬼面 |
| 愛知 | 瀧山寺 | 三門 仁王像 |
| 愛知 | 金蓮寺 | 阿弥陀如来坐像 |
| 岐阜 | 円鏡寺 | 金剛力士像(阿形、吽形) |
| 岐阜 | 横蔵寺 | 金剛力士像 |
| 滋賀 | 知善院 | 十一面観音坐像 |
| 京都 | 蓮華王院(三十三間堂) | 千手観音立像 |
| 京都 | 高山寺 | 石水院 子犬像 |
| 京都 | 鹿王院 | 釈迦如来像 |
| 京都 | 鹿王院 | 十大弟子像 |
| 京都 | 相国寺 | 釈迦如来像 |
| 京都 | 相国寺 | 迦葉像 |
| 京都 | 相国寺 | 阿難像 |
| 京都 | 戒光寺 | 釈迦如来立像 |
| 京都 | 泉涌寺 | 三尊仏(阿弥陀・釈迦・弥鞠) |
| 京都 | 西明寺 | 釈迦如来像 |
| 京都 | 多禰寺 | 金剛力士像 |
| 京都 | 圓光寺 | 千手観音像 |
| 京都 | 金戒光明寺 | 三重の塔 文殊菩薩像と脇士像 |
| 奈良 | 東大寺 | 八幡宮 僧形八幡神像 |
| 奈良 | 興福寺 | 国宝館 仏頭(元西金堂本尊) |
| 奈良 | 室生寺 | 金堂 十二神将像 |
| 奈良 | 弘仁寺 | 明星堂 大日如来坐像 |
| 和歌山 | 金剛峯寺 | 指徳童子立像(八大童子) |
| 和歌山 | 金剛峯寺 | 阿耨達童子立像(八大童子) |
| 和歌山 | 三宝院 | 弘法大師像 |
| 高知 | 雪渓寺 | 薬師如来像 |
運慶作品はどの場所にある?
上記の運慶作品の一覧を見ておわかりのように、運慶作品だと確定した作品と、その可能性が高い作品が分布している場所は、栃木県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、奈良県、和歌山県になります。
なかでも、奈良県に集中しているのが特徴です。
これは、運慶の活動拠点が奈良であったこと、また、1180年の平氏による南都焼き討ちによって焼亡した東大寺と興福寺の再興に運慶が関わったことが最大の理由でしょう。
さらに、運慶作品だと伝えられる仏像を含めると、その場所は長野県、岐阜県、滋賀県、高知県にも広がります。
運慶作品が、当時としては、いかにいろいろな場所に広まったかがよくわかりますね。
ところで、鎌倉や京都、東京へ観光に行った際に運慶作品を見たいという方もいるでしょう。
鎌倉であれば、近隣の神奈川県横須賀市にある浄楽寺へ行ってみてください。
ここには、阿弥陀三尊像(阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩)、不動明王立像、毘沙門天立像という5体の運慶作品が安置されています。
運慶の作品のなかでも初期のものですが、とても状態がよいようです。
次に、京都であれば、京都市内の六波羅蜜寺に運慶作品があります。
地蔵菩薩坐像です。
六波羅蜜寺のホームページによれば、「一名〝夢見地蔵〟といわれ眉目秀麗な面相や変化のある法衣のひだのまとめ方は実に優れている」とのこと。
また、運慶の作品ではなく、湛慶の作品になりますが、ここ六波羅蜜寺には、運慶坐像と湛慶坐像があります。
最後に東京ですが、東京都千代田区にある「半蔵門ミュージアム」で運慶作品と推定されている大日如来坐像を見ることができます。
入館は無料!
これはなんとしてでも見に行かねばソンですよ♪
運慶作品のうち国宝はどれ?
上記の運慶作品のうち、国宝だけを一覧にしてみます。
| 静岡 | 願成就院 | 阿弥陀如来坐像 |
| 静岡 | 願成就院 | 不動明王立像 |
| 静岡 | 願成就院 | 二童子立像 |
| 静岡 | 願成就院 | 毘沙門天立像 |
| 奈良 | 円成寺 | 大日如来坐像 |
| 奈良 | 東大寺 | 南大門 金剛力士立像 |
| 奈良 | 東大寺 | 俊乗堂 俊乗上人(俊乗房重源)坐像 |
| 奈良 | 興福寺 | 北円堂 弥勒仏坐像 |
| 奈良 | 興福寺 | 北円堂 無著菩薩・世親菩薩立像 |
| 和歌山 | 金剛峯寺 | 八大童子立像 |
運慶作品がこれだけ国宝に指定されているということは、運慶がいかに常に高い水準の作品を生み出しつづけていたかを如実に物語っています。
運慶は、ときに「天才仏師」と呼ばれることがありますが、まさにこの国宝指定作品の数が、その呼称の妥当性を裏づけていると言えるのではないでしょうか。

運慶作品の特徴は?
運慶が活躍する前の平安時代後期までは、仏像は身体が細身で、穏やかな表情をしていました。
これに対して、運慶の作品の特徴として挙げられるのは、力強さと圧倒的な存在感です。
まるで仏像作品が本当に生きているかと錯覚するかのような生き生きとした表情や動きが見られます。
運慶の作品の多くは、屈強な男性の風貌を持ち、身体の肉づきがよく、堂々とした体つきで重量感があり、自由な動きを感じる姿勢をしていて、力強いエネルギーに満ちています。
また、眼に水晶を入れて「玉眼」(ぎょくがん)とした仏像作品も多く見られます。
玉眼は、光が当たると眼球が動くように見えるので、まるで生きているかのような存在感があるのです。
運慶は、このような技法を取り入れることで、仏を人びとにとってグッと身近な存在にしたのだと思います。
もちろん、運慶は、こうしたオリジナリティが高い作品の特徴を1人で生み出したわけではありません。
先人の仏師たちから続いてきた作風を受け継ぎながらも、勢力を伸ばしてきた武士たちの要望に応える形で、運慶独自の作風を生み出していきました。
そして、運慶の作品の特徴は、後世の仏師や彫刻師たちに大きな影響を与えていったのです。
▼運慶が属した慶派について知りたい方は、こちら↓↓↓

運慶とは?
最後に、運慶の生涯について簡単にご紹介しておきましょう。
運慶は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した、日本史上もっとも有名な仏師(ぶっし)です。
生まれた年は、1150年前後(推測)で、亡くなった年は1223年です。
運慶が生きた時代はちょうど政権の中心が貴族から武士へと移る過渡期で、穏やかに鎮座ましました貴族好みの仏像に代わって、今にも動き出しそうな躍動感ある武士好みの仏像を数多くつくりました。
デビューは20代半ば。
デビュー作は大日如来坐像(円成寺)です。
30代には、北条時政の願いで仏像を彫るなど、鎌倉幕府や東国武士たちとの結びつきを強くします。
40代には、東大寺大仏殿の仏像を彫るなど、仏師として揺るぎない地位を確立しました。
50代が名実ともにピークの時期で、最高の僧位である法印(ほういん)を授与。
その一方で、日本史の教科書には必ず載っている東大寺南大門の金剛力士立像を制作しています。
60代でも活躍が衰えることはなく、鎌倉幕府関係者の願いで多数の仏像を制作。
70代前半で、この世を去りました。
▼運慶の生涯についてもっと知りたい!という方は、こちらをクリック↓↓↓

まとめ
- 運慶作品は、80体以上制作されたと推定
- 運慶作品がある場所は奈良県に集中
- 運慶作品の特徴は力強さや写実的なリアリティ
▼過去の運慶展について知りたい方は、こちら↓↓↓

▼運慶展(2025年)に行ってきました♪レビューはこちら↓↓↓