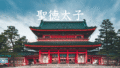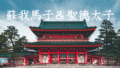「和を以(もっ)て貴(とうと)しとなす」
この有名なフレーズは、聖徳太子(厩戸王:うまやとおう)が604年に制定したとされる十七条憲法第一条の冒頭の一文です。
〝和をもっとも大切な規範とせよ〟という意味ですが、それはたんなる道徳の教えではありませんでした。
実は、この日本最古の「憲法」(現代の憲法とはまるで違い、社訓のようなもの)は、当時の日本が直面していた国際的な大ピンチと、内政の腐敗という二つの危機を乗り越えるための、革新的な〝政治改革マニュアル〟だったのです。
この記事では、そうした十七条憲法が生まれた背景から、制定の真の目的、そして現代まで続く〝後世の創作論争〟について、深く掘り下げて解説していきます。
また、十七条憲法の書き下し文と現代語訳もご紹介します。
さあ、1400年の時をさかのぼり、聖徳太子の壮大な国家建設計画の全貌を見ていきましょう!
十七条憲法制定の背景と経緯
聖徳太子が十七条憲法を制定した背景には、国際的な危機感と国内の政治改革の必要性がありました。
隋の皇帝・文帝からの非難
5世紀後半から6世紀にかけて、日本は中国の宋(そう)に朝貢(ちょうこう)していましたが、中国での戦乱により国交が途絶えていました。
しかし、6世紀末に隋(ずい)が中国を統一すると、600年(推古天皇8年)に聖徳太子は約1世紀ぶりに朝貢を再開します。
この際、日本の政治体制について説明を受けた隋の皇帝・文帝(ぶんてい)から、「それは間違っている」と非難される出来事がありました。
この先進国からの厳しい評価は、聖徳太子に大きな危機感を与えたとされています。
聖徳太子は、夜も眠れないほどショックだったかもしれません(汗)
ちなみに、この出来事は、隋の正史である『隋書』には記載されていますが、『日本書紀』には記載されていません。
豪族連合からの脱却と意識改革
当時の日本(ヤマト朝廷)は、有力な豪族の協力体制によって政治が行われていました。
朝廷で働く役人は、朝廷に直接雇用されておらず、豪族の命令で派遣されている、今で言うところの〝派遣社員〟のような状態でした。
このため、役人にとっての忠誠の対象は、朝廷ではなく、派遣元の豪族でした。
しかし、この体制だと、
- 朝廷(天皇)に対する役人の忠誠心が低い
- 役人の上下関係が能力ではなく派遣元の豪族の力関係で決まり、役人同士が派遣元の豪族のことでいがみ合い、一致団結できない
……という問題がありました。
国のことより自分の雇用主のほうが大事というのは、国の役人としてはたしかにマズいですね(汗)
そこで聖徳太子は、隋に軽視されないよう、豪族の協力体制から、天皇を中心とする律令国家体制への改革を急ぎました。
そのために聖徳太子がまず603年(推古天皇11年)に制定したのが、冠位十二階です。
これにより、役人を家柄ではなく才能で登用する道を開きました。
そして、この改革をさらに進めるために、また、役人たちの意識を〝豪族への忠誠〟から〝天皇と国家への奉仕〟へと変革するために604年(推古天皇12年)に制定したのが、十七条憲法だったのです。
こうした一連の改革によって、国内体制は確立され、対等な外交を目指すための土台作りが進んでいったのです。
▼冠位十二階についてわかりやすく解説しています!こちらをクリック↓↓↓

十七条憲法制定の目的
十七条憲法は、604年(推古天皇12年)に聖徳太子が制定したとされる日本最初の成文法です。
これは、国民に向けた法律ではなく、ましてや、国民が国家権力を統制するための近現代の憲法ともまるで違います。
十七条憲法は、豪族や役人(官僚、貴族)に対して道徳的な規範や心得を示したもので、現代の会社の〝社訓〟のような性格を持つものでした。
そうした十七条憲法を制定した主な目的は、次の3つに集約されます——
天皇中心の国家体制の確立
当時、力をつけた豪族のなかには、自分勝手な政治を行う者がいました。
そこで、第三条で「天皇の命令に従うこと」と定め、豪族の勢力を抑え、天皇を国の頂点に据えた政治が行えるようにしました。
この点に、聖徳太子が描いた〝天皇を中心に据えた国づくり〟の理念が明確に表れています。
役人の意識改革と組織の統一
急務だったのは、朝廷で働く役人たちのあいだに存在した、豪族間の利害対立と、マウントの取り合いを解消することでした。
そこで聖徳太子は、十七条憲法第一条の「和を以(もっ)て貴(とうと)しとなす」(人びとが争わず、調和を大切にすること)を政治の基本とし、役人同士がいがみ合うことなく、協力して天皇のために仕事に励むことを求めました。
また、第一条では議論の重要性、第十七条では独断の排除が説かれ、豪族出身者による勝手なふるまいを戒(いまし)め、公平で偏(かたよ)りのない話し合いを重んじる姿勢を求めました。
これにより、豪族同士の利害が対立しやすかった時代において、十七条憲法は政治に統一的な方向性を与え、組織全体をまとめ、天皇の理想を実現するための共通の指針となりました。
外交上の地位向上と大国化
先進国であった中国(隋)と対等な外交を行うためには、国家としての体制が整っている〝まともな国〟だと認めてもらう必要がありました。
〝国の基本となる決まり〟があるかどうかが、そのポイントの1つでした。
聖徳太子は、仏教や儒教などの教えを参考に〝国をまとめるための基本となる決まり〟として十七条憲法をつくり、日本が隋に引けをとらない統一された国家であることを示そうとしました。
これは、国としての体裁を整え、国際社会で認められるための布石でもあったのです。
国の骨格をつくり、人びとの意識を変えようとした(とされる)聖徳太子の努力は並大抵のものではなかったのでしょうね。
▼遣隋使に隠された聖徳太子の外交戦略とは?こちらをクリック↓↓↓

聖徳太子の十七条憲法は本当に本人の作?
十七条憲法は聖徳太子が604年(推古天皇12年)に制定したとされ、日本最古の成文法として学校の教科書にも載っています。
しかし、十七条憲法が本当に聖徳太子によってつくられたのかどうかについては、以前から論争があります。
十七条憲法の創作説が生まれる根拠
十七条憲法が後世の創作ではないかとする説の主な根拠は、条文中の言葉遣いや内容の不自然さにあります。
1つ目は、国司(こくし)という言葉が使われていることです。
十七条憲法の条文には、地方官の名称として「国司」という言葉が含まれています。
しかし、国司が設置されたのは、十七条憲法が制定されたとされる時代よりもずっと後の時代です。
この点から、「厩戸王の時代に国司という言葉が使われるはずがない」として、少なくとも一部は後世に創作されたという説が生まれました。
2つ目は、『日本書紀』編纂時に創作もしくは潤色(うわべや表現をつくろう)されたとする推定です。
十七条憲法が『日本書紀』の編纂者によって創作または文章が潤色されたとする見解が、江戸時代に示されました。
近代に入ると、歴史学者の津田左右吉(そうきち)氏らも、内容が推古朝当時の国制と合わないとして、『日本書紀』が編纂された720年頃に作成されたと推定しました。
3つ目は、漢文に〝日本的特徴〟があるとする見方です。
この見方によると、漢文の書き方が7世紀のものとは考えられず、『日本書紀』推古紀の文章と共通の誤字や誤記が見られることから、全体が『日本書紀』編纂時に創作された、もしくは、少なくとも文章が大きく潤色されたと推定されています。
創作説への反論
一方で、十七条憲法は聖徳太子の時代につくられたと認める反論も根強くあります。
その根拠の1つは、推古朝の政治方針と適合することです。
創作説に反論する学者のなかには、国司のような官制的な役割が律令制以前の推古朝当時にもある程度存在していても不自然ではないとする見解を持つ者がいます。
もう1つの根拠は、十七条憲法の内容が時代に適合しているということです。
十七条憲法に示されている仏教(第二条)や礼(第四条)を重んじる姿勢が当時の推古朝の政治方針に沿っていることから、後世の潤色が入っている可能性は否定できないものの、基本的には推古朝当時のものと認めてよいとする見解があります。
この見解では、十七条憲法の目的が、当時の豪族連合体制から天皇中心の国家体制を目指すという、聖徳太子の政治改革の方向性に合致していることを重視しています。
十七条憲法創作説のゆくえは?
十七条憲法のすべての条文が後世の創作であるという決定的な証拠はなく、現在でも創作か否かは大きな争点となっています。
聖徳太子人気によって、他の人の功績が聖徳太子のお手柄とされた可能性が指摘されている一方で、教科書では604年制定とされており、十七条憲法については今なお論争は続いています。
いったい歴史的事実はどうだったのでしょうか?
今後の論争のゆくえが気になりますね^^
十七条憲法の内容:書き下し文と現代語訳
書き下し文は、淨教寺(じょうきょうじ)のサイトから引用させていただきました。
第一条
一にいわく、和(やわらぎ)を以って貴しとなし、忤(さから)うことなきを宗(むね)となす。人みな党(たむら)あり。また達(さと)れるもの少なし。ここを以ってあるいは君・父に順(したが)わず、たちまち隣・里に違(たが)う。しかれども上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなはち事(こと)の理(ことわり)自(おのずから)に通(とお)る。何事か成らざらん。
和(うちとけ、なごみあうこと)をもっとも大切な規範としなさい。そして、お互いに背き逆らうことのないよう心がけなさい。なぜなら、人は誰でも自分の仲間で徒党を組みがちで、この世に物事の道理をわきまえた理想的な人格者(賢人)は少ないものだからです。そのために、私たちはついリーダーや親の命令に従わなかったり、身近な人や隣近所と争いを起こしたりしてしまうのです。しかし、もしも上の者と下の者(上司と部下)がにこやかに仲むつまじくなり、自分の利害といった執(とら)われの心を離れて問題を話し合えるならば、おのずから筋道(道理)が通り、事実と真理が一致します。そうすれば、どんな難しいことでも成就し、実現できないことは何もないでしょう。和の精神と開かれた議論こそがすべてを成功に導く鍵なのです。
第二条
二にいわく、篤(あつ)く三宝を敬え。三宝とは佛・法・僧なり。すなわち、四生(よつのうまれ)に終帰(ついのよりどころ)・万国(よろずのくに)の極宗(きわめのむね)なり。何れの世・何れの人かこの法(みのり)を貴ばざらん。人はなはだ悪(あ)しきものすくなし。よく教えらるれば従う。それ三宝に帰(よ)りまつらずば、何をもってか枉(まが)れるを直(ただ)さん。
心から三宝(さんぽう)を篤(あつ)く敬いなさい。三宝とは、仏(悟りを開いた覚者)、その真理の教え(法)、そしてその教えを実践する人びとの集い(僧)のことを指します。これこそが、すべての生きとし生けるものの最終的なよりどころであり、あらゆる国の究極の規範(仰ぐべき教え)なのです。どのような時代であれ、どのような人であれ、この尊い教えを敬わずにいられるでしょうか。心底からの極悪人はまれであり、よく教え諭(さと)せば必ず真理に従うものです。もしもこの三宝をよりどころとしないならば、他に何によって我執(がしゅう)にとらわれた、よこしまな曲がった心や行いを正すことができるでしょうか。
第三条
三にいわく、詔(みことのり)を承(うけたまわ)りてはかならず謹(つつし)め。君をばすなわち天(あめ)とす。臣(やつこらま)をばすなわち地(つち)とす。天は覆い地は載せて、四(よつ)の時順(したが)い行はれて、万(よろず)の気(しるし)、通うことを得(う)。地、天を覆はんとするときは、すなわち壊(やぶ)るることを致さまくのみ。ここをもって、君のたまうときは臣承る、上(かみ)行うときは下(しも)靡(なび)く。故(それ)詔を承りてはかならず慎(つつし)め、謹(つつし)まずはおのずからに敗(やぶ)れなん。
天皇の詔(みことのり)を受けたら、必ず謹(つつし)んで従いなさい。たとえるなら、君主は天であり、臣下(官僚)は地です。天がすべてを覆い、地がすべてを載せることによって、四季は順序正しく巡り、あらゆる生き物の生気が通い、活動することができるのです。もしも地が天を覆い隠そうとするようなことがあれば、この世界の秩序は必ず破壊されてしまうでしょう。このように、君主が命じたことには臣下は必ず承諾し、上の者が行うことには下の者は従うべきなのです。ですから、天皇の命令を受けたならば、必ず謹んで受け入れなさい。もし従わなければ、結局は自らが破滅したり、事が失敗したりすることになるでしょう。
第四条
四にいわく、群卿(まちきみたち)・百寮(もものつかさ)、礼(いや)びをもって本(もと)とせよ。それ民(おおみたから)を治(おさ)むるの本、かならず礼びにあり。上(かみ)礼びなきときは下(しも)斉(ととの)はらず、下礼びなきときはもってかならず罪(つみ)あり。ここをもって、群臣(まちきみたち)礼びあるときは位(くらい)の次(ついで)乱(みだ)れず、百姓(おおみたから)礼びあるときは国家(あめのした)おのづからに治まる。
すべての官僚は、まず礼節を物事の基本としなさい。国民を治めるうえでもっとも肝心なことは、まさにこの礼儀作法にあるからです。上に立つ者が礼節を欠けば、下の者の秩序は乱れ、民衆から礼節が失われれば、必ずや罪を犯す者が現れます。そのため、官僚たちが礼節を守り行えば、身分の順序は乱れることなく、国民一人ひとりに礼節が根づけば、国はおのずと平和に治まるものなのです。
第五条
五にいわく、餐(あじわいのむさぼり)を絶ち、欲(たからのほしみ)を棄てて明らかに訴訟(うったえ)を弁(わきま)へよ。それ百姓の訴えは、一日に千事あり。一日すら尚しかり、いわんや歳を累(かさ)ねておや。このごろ訴えを治むる者、利を得るを常とし、賄(まいない)を見てはことわりをもうすを聴く。すなわち財あるものの訴えは、石をもって水に投ぐるがごとし。乏(とぼ)しきものの訴えは、水をもって石に投ぐるに似たり。ここをもって、貧しき民はすなわちよるところを知らず。臣道(しんどう)またここに闕(か)く。
公の職務に携わる者は、飲食や物欲への貪(むさぼ)りを断ち、金銭的な私欲を捨て、国民の訴えを公正かつ明白に裁決しなさい。国民の訴訟は日に千件にも及ぶほど多く、一日でさえこの有様ですから、年月が重なればその件数の多さは想像に難くありません。ところが近頃、訴訟を取り扱う役人の中には、私的な利益を得ることを常態化し、賄賂を受け取ってからでなければ言い分を聞かない者がいます。その結果、財力のある者の訴えは「石を水に投じるように」あっさりと聞き入れられますが、貧しい人びとの訴えは「水を石に投げるように」まったく取り合ってもらえません。これでは、弱い立場の国民は救済の術(すべ)を失い、為政者たる官吏としての正しい道も欠けてしまうでしょう。
第六条
六にいわく、悪を懲(こ)らし善を勧むるは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり。ここをもって、人の善を匿(かく)すことなく、悪を見てはかならず匡(ただ)せ。それ諂(へつら)い詐(あざむ)く者は、国家を覆(くつがえ)す利器なり。人民を絶つ鋒剣(ほうけん)なり。また佞(かだ)み媚(こ)ぶる者は、上に対しては好みて下の過ちを説き、下にいては逢(あ)いては上の失を誹謗(そし)る。それ、これらの人は、まな君に忠なく、民に仁なし。これ大乱の本なり。
悪事を正し、善行を奨励することは、古来からの変わらぬ良き規範です。それゆえ、他人の善い行いを決して隠さず、悪を見たら必ず正しなさい。おもねり、人を欺(あざむ)く者は、国を転覆させる鋭利な刃物であり、国民の生活を断ち切る鋭い剣のような存在です。特に、口先だけで媚(こ)びへつらう人間は、目上の者に対しては下の人間の過失を好んで告げ口し、逆に目下の者には上の者の失態を非難します。このような者は、君主への忠誠心も、国民への思いやり(仁愛)も持ち合わせていません。これこそが、社会全体を大きく混乱させる最大の原因となるのです。
第七条
七にいわく、人おのおの任あり。掌(つかさど)ること、濫(みだ)れざるべし。それ賢哲、官に任ずるときは、頌(ほ)むる声すなわち起こり、かん者(かんじゃ)、官を有(たも)つときは、禍乱(からん)すなわち繁(しげ)し。世に、生まれながら知る人少なし。よく念(おも)いて聖となる。事、大少となく、人を得てかならず治(おさ)まる。時、急緩(きゅうかん)となく、賢に遇いておのずから寛なり。これによりて、国家永久にして、社稷(しゃしょく)危(あや)うからず、故に、古(いにしえ)の聖王(せいおう)、官のために人を求む。人のために官を求めず。
人はそれぞれ、果たすべき固有の役割を持っています。誰もが、自分の職務の範囲を守り、権限を乱用してはなりません。賢明な人物が公職に就けば、たちまち称賛の声が上がり、政治は安定します。しかし、よこしまな心を持つ者が登用されれば、災いと混乱がすぐに頻発するでしょう。生まれながらにして物事をすべて悟っている者は、この世には少ないものです。深く考え、努力を重ねて初めて真の指導者となるのです。仕事は大小にかかわらず、適任者を得て初めて円滑に運びます。世の中の動きが激しくても、あるいは緩やかであっても、賢明な人材がいれば、おのずと国にはゆとりと豊かさが生まれます。これによって、国家は永く存続し、国民は危険にさらされることはありません。古代の聖なる王がしたように、職務のためにふさわしい人物を探しなさい。決して、特定の人物のために不必要なポストを設けてはならないのです。
第八条
八にいわく、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早く朝(まか)りて晏(おそ)く退(まか)でよ。公事(こうじ)?(いとま)なし。終日(ひねもす)にも尽くしがたし。ここをもって、遅く朝(まか)るときは急なることに逮(およ)ばず。早く退(まか)るときはかならず事尽くさず。
すべての公職に就く者は、朝は早く出勤し、夕方は遅くまで残りなさい。公の仕事というものは、決して油断できるものではなく、たとえ丸一日かけてもすべてを終えるのは難しいものです。ですから、朝遅れて出勤すれば、緊急の案件に対応できず、また、定時前に早く退勤してしまえば、必ずや処理しきれない仕事を残すことになるでしょう。
第九条
九にいわく、信はこれ義の本(もと)なり。事ごとに信あるべし。それ善悪成敗はかならず信にあり。群臣(ぐんしん)ともに信あるときは、何事か成らざらん。群臣信なきときは、万事ことごとくに敗れん。
誠実さ(信)こそが、人が歩むべき正しい道の根本です。したがって、公務であれ私事であれ、何事にも真心を尽くしなさい。なぜなら、物事の善悪、そして事業の成功と失敗を決めるのは、まさに誠実さの有無にかかっているからです。公の職務に就く者すべてが誠実であれば、どのような困難な事業も必ずや成し遂げられるでしょう。しかし、もし誠実さが欠けていたならば、あらゆる計画、あらゆる事業が、ことごとく失敗に終わってしまうのです。
第十条
十にいわく、こころの忿(いか)りを絶ち、おもての瞋(いか)りを棄(す)てて、人の違(たが)うことを怒(いか)らざれ。人みな心あり。心おのおの執(と)るところあり。かれ是(ぜ)とすれば、われは非(ひ)とする。われ是とすれば、かれ非とす。われはかならずしも聖(ひじり)にあらず。かれかならずしも愚にあらず。ともにこれ凡夫(ぼんぶ)のみ。是非の理、?(たれ)かよく定むべけんや。あいともに賢愚なること、鐶(みみがね)の端(はし)なきがごとし。ここをもって、かの人は瞋るといえども、かえってわが失を恐れよ。われひとり得たりといえども、衆に従いて同じく挙(おこな)え。
心の中の怒りを絶ち、顔に出る激しい怒りを捨てなさい。そして、人が自分と異なる意見を述べても、決して激しく怒ってはなりません。なぜなら、人にはそれぞれ異なる心があり、その心には誰もが譲れないこだわりを持っているからです。ある人が「正しい」と思うことを自分が「間違っている」と否定し、自分が「正しい」と思うことを他人が「間違い」だと否定する。しかし、私が必ずしも聖人ではなく、相手が愚か者だと決まっているわけではありません。私たちは、どちらも欠点を持つ「凡夫」(ぼんぷ)にすぎないのです。絶対的な正しさや道理を、一体誰が判断できるというのでしょうか?お互いに賢明な面もあれば愚かな面もあることは、端のない金属の輪(鐶:かん)のように、区切りがないものなのです。ですから、もし他人があなたに怒りを向けたとしても、むしろ自分の側に過失がなかったかを振り返り、反省しなさい。また、自分一人だけが「これが真理だ」と確信していても、多くの人々の意見を尊重し、それに同調して行動しなさい。
第十一条
十一にいわく、功過(こうか)を明らかに察(み)て、賞罰はかならず当てよ。このごろ賞は功においてせず、罰は罪においてせず。事を執る群卿(ぐんけい)、賞罰を明らかにすべし。
功績と過失を明確に見極め、功労には必ず賞を、罪科には必ず罰を与えるようにしなさい。近頃の組織では、功績がない者に賞を与えたり、罪がないのに罰を科したりする不当な事例が見受けられます。政務を担うすべての官吏は、この賞罰の基準を正しく、かつ明白に実行しなければならないのです。
第十二条
十二にいわく、国司(くにのつかさ)・国造(くにのみやつこ)、百姓(ひゃくせい)に斂(おさ)めとることなかれ。国に二君なし。民に両主なし。卒土(そつど)の兆民(ちょうみん)は王をもって主となす。所任(しょにん)の官司(かんじ)はみなこれ王民なり。何ぞあえて公と、百姓に賦斂(おさめと)らん。
地方を治める役人たちは、決して民衆から勝手に財物や労力を徴収してはなりません。国に二人の君主はおらず、民衆に二人の主人はいないからです。この国すべての民は、ただ天皇(王)一人のみに仕える臣民です。そして、地方の政務を任されている官吏たちも、みな天皇の家臣にすぎません。それなのに、どうして公的な税や労役とは別に、私利のために民衆から取り立てを行うことが許されるでしょうか。
第十三条
十三にいわく、もろもろの官に任ぜる者、同じく職掌(しょくしょう)を知れ。あるいは病し、あるいは使(つかい)して、事を闕(おこた)ることあらん。しかれども知ることを得る日には、和(あまな)うことむかしより識(し)れるがごとくにせよ。それ与(あずか)り聞かずということをもって、公務をな妨(さまた)げそ。
すべての公職にある者は、互いの職務内容を広く熟知するようにしなさい。病気や、やむを得ない出張などで、担当者が一時的に職務を欠くことがあります。そのような事態になっても、後にその任務に就いた者は、同僚と緊密に連携し、あたかも以前から関わっていた者のように、滞りなく業務を継続しなければなりません。「自分は聞いていない」「担当外だ」などと言い訳をし、公的な業務を停滞させるようなことは、決して許されないのです。
第十四条
十四にいわく、群臣百寮(ぐんしんひゃくりょう)、嫉妬(しっと)あることなかれ。われすでに人を嫉(うらや)むときは、人またわれを嫉む。嫉妬の患(うれ)え、その極(きわまり)を知らず。このゆえに、智おのれに勝るときは悦(よろこ)ばず、才おのれに優(まさ)るときは嫉妬(ねた)む。ここをもって五百歳にしていまし今賢(こんけん)に遇うとも、千載にしてひとりの聖(ひじり)を待つこと難し。それ賢聖(けんせい)を得ずば、何をもってか国を治めん。
すべての公職者は、人を嫉妬してはなりません。なぜなら、あなたが人を妬めば、必ずや他人もまたあなたを妬み、この嫉妬がもたらす災いには際限がないからです。その結果、人は自分より優れた知恵を持つことを喜びとせず、自分より優秀な才能を持つ者を妬んでしまうのです。このような精神状態では、五百年経っても目の前に現れた賢人の価値を認められず、千年待っても聖人を迎え入れることはできないでしょう。賢者や聖人という有能な人材がいなくて、一体どうやってこの国を治めることができるでしょうか。
第十五条
十五にいわく、私(わたくし)を背きて公に向くは、これ臣の道なり。およそ人、私(わたくし)あるときはかならず恨(うら)みあり。憾(うら)みあるときはかならず同(ととのお)らず。同(ととのお)らざるときは私をもって公を妨(さまた)ぐ。憾み起こるときは制に違(たが)い、法を害(やぶ)る。ゆえに初めの章に云う、上下和諧(じょうげわかい)せよ、と。それまたこの情(こころ)か。
個人的な感情や利益(私心)を捨て、公の利益を目指すことこそが、貴族・官吏の道であり、公僕としての務めです。およそ人に私心があるとき、必ず他者に対して恨みの感情が生まれます。恨みが生まれると、人々は協力し合うことができなくなります。協力体制が崩れれば、その私心によって公の業務が妨害されることになるのです。さらに、恨みが深刻化すれば、組織の制度に違反し、国の法律を侵すことにもなりかねません。だからこそ、十七条憲法の第一条で「上下の者が仲良くし、執われの心を離れて話し合いなさい」と説いたのです。これは、私心を捨てて和を重んじるという、この公務員倫理の根本を説くものなのです。
第十六条
十六にいわく、民(たみ)を使うに時をもってするは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり。ゆえに、冬の月に間(いとま)あらば、もって民を使うべし。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり。民を使うべからず。それ農(なりわい)せずば、何をか食らわん。桑(くわと)らずば何をか服(き)ん。
国民を公的な仕事に動員する際は、必ず農事の時期を考慮しなさい。これは古来より受け継がれてきた、善き統治の原則です。それゆえ、冬の間に農閑期(ひま)があれば、その時を見計らって国民を使役しなさい。しかし、春から秋にかけては、農耕や養蚕といった、生活の根幹をなす仕事の最盛期です。この時期に国民を使役することは厳に慎まなければなりません。一体、農耕をしなければ、国民は何を食べて生きていくのでしょうか。養蚕をしなければ、何を着て身を覆うというのでしょうか。国家の基本は、国民の衣食住の確保にあります。
第十七条
十七にいわく、それ事はひとり断(さだ)むべからず。かならず衆(しゅう)とともに論(あげつら)うべし。少事(しょうじ)はこれ軽(かろ)し。かならずしも衆とすべからず。ただ大事(だいじ)を論(あげつら)うに逮(およ)びては、もしは失(しつ)あらんことを疑う。ゆえに衆と相(あい)弁(わきま)うるときは、辞(こと)すなわち理(り)を得ん。
物事を決定する際、重大な案件は独断で行ってはなりません。必ず、関係者全員と徹底的に議論しなさい。些細な事柄であれば、柔軟に対応し、必ずしも全員の意見を聞く必要はありません。しかし、重要な決定を下す場合は、判断に誤りがあるかもしれないという疑いを常に持ちなさい。それゆえに、みんなで是非を検証し合うことで、道理に適った最善の結論を導き出すことができるのです。
▼聖徳太子が5分でわかる!こちらをクリック↓↓↓