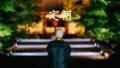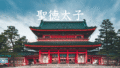日本史の中で「三大悪人」と呼ばれる人物がいます。
足利尊氏、平将門、そして奈良時代の僧侶・道鏡です。
とりわけ道鏡は「天皇の寵愛を受けて皇位を狙った悪僧」と語られることが多く、日本史の中でも強い悪いイメージを持たれてきました。
しかし本当に道鏡は「悪僧」だったのでしょうか。
単なる野心家という見方だけでなく、「実は国を安定させようとした人物」という再評価も進んでいます。
本記事では、道鏡の生涯や天皇との関係、そして歴史的評価の変遷について詳しく見ていきましょう。
道鏡はどんな人?本当に悪僧だった?
道鏡は、現在の大阪府東部・河内国に生まれました。
出自は弓を製作する弓削(ゆげ)氏という一族です。
若き日の道鏡は葛城山(かつらぎさん)に籠(こ)もって修行し、古代インドの言語である梵語(ぼんご:サンスクリット語)に通じた学僧で、修験道的な祈祷(きとう)や加持(かじ)などにも習熟していたと伝えられています。
その後、東大寺初代別当・良弁僧正(ろうべんそうじょう)のもとで修行を積み、やがて宮廷に仕えるようになりました。
そこで天皇の病を癒す「禅師」(ぜんじ)として仕えたことが、道鏡の運命を大きく変えることになります。
道鏡は特別に高い身分の出自ではありませんし、努力家で真面目な僧という印象を受けます。
世間で言われるような「悪僧」のイメージは感じられません。
ただ、そのひたむきな努力が、周囲の人々の目には野心家として映ったのかもしれません。
道鏡を寵愛しすぎの孝謙天皇
孝謙(こうけん)天皇は、聖武(しょうむ)天皇と光明皇后(こうみょうこうごう)の娘として生まれ、日本史上6人目の女性天皇となりました。
即位後、母・光明皇后の看病を理由に淳仁(じゅんにん)天皇に譲位し、自らは上皇(じょうこう)となります。
光明皇后の死後、孝謙上皇は病に倒れますが、このとき看病にあたったのが道鏡でした。
道鏡の祈祷によって病が回復したことで、孝謙上皇は道鏡に強い信頼を寄せるようになります。
緊張感と孤独の中で心身ともに疲弊していた孝謙上皇が病を癒され、精神的な支えとなった道鏡を寵愛したのは、必然的なことだったのかもしれません。
その後、道鏡はわずか数年のうちに「大臣禅師」「太政大臣禅師」、そして「法王」という日本仏教界の頂点に立つ地位へと異例の昇進を遂げます。
天皇の厚い信任なしには考えられない昇進です。
孝謙上皇と道鏡の関係を危惧したのが藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)でした。
藤原仲麻呂は淳仁天皇を擁立し、実質的に政治の実権を握っていました。
しかし孝謙上皇が復権し、道鏡を重用するにつれ、その地位は揺らぎます。
764年、藤原仲麻呂はついに挙兵し「藤原仲麻呂の乱」を起こしました。
しかし反乱は失敗して藤原仲麻呂は戦死し、淳仁天皇も廃位され淡路島へ流されてしまいます。
この結果、孝謙上皇は再び称徳(しょうとく)天皇として重祚(ちょうそ)し、道鏡は絶対的な後ろ盾を得ました。
称徳天皇は「仏教による国家統治」を理想に掲げ、道鏡を最高位の僧として信任します。
弟の弓削浄人(ゆげのきよひと)らも高位に取り立てられ、一族の勢力は拡大しました。
宗教と政治を一体化させる体制は、理想を掲げる一方で、既存の貴族層との緊張を高める要因ともなりました。
かつての協力者が一転して敵になってしまう不安定な世の中であったことがよくわかります。
称徳天皇が仏教の力を国家の拠り所としたのは、自然な流れだったのかもしれません。
道鏡事件(宇佐八幡宮神託事件)が日本史に与えた影響とは?
769年、皇位継承をめぐる大事件「宇佐八幡宮神託事件」、いわゆる「道鏡事件」が起こります。
この事件によって、道鏡は「皇位を狙った悪僧」というイメージが決定的になります。
九州の宇佐八幡宮から「道鏡を皇位に就ければ天下は安泰になる」という神託(神のお告げ)があったと奏上されます。
称徳天皇は真偽を確かめるため、和気清麻呂を勅使(ちょくし)として宇佐に派遣しました。
しかし、和気清麻呂が持ち帰った神託は「皇位は必ず皇族が継ぐべきであり、無道の者は排すべし」というもので、これは道鏡の即位を明確に否定する内容でした。
和気清麻呂が真実を隠さず奏上すると、称徳天皇と道鏡は激怒します。
和気清麻呂は名前を「別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)」と改めさせられる屈辱を受け、大隅国(現在の鹿児島県)に流罪となりました。
さらに道鏡は暗殺を試みますが、雷雨に阻まれて未遂に終わったと言われています。
最終的に称徳天皇は、強引に道鏡を天皇に立てることはせず、事態を鎮静化させました。
翌770年に称徳天皇が崩御すると、白壁王(しらかげおう)が光仁(こうにん)天皇として即位し、道鏡の皇位継承の道は完全に閉ざされました。
道鏡が自ら仕組んだ事件だとするならば、「悪僧」としての評価もうなづけます。
和気清麻呂への処分や暗殺未遂といった出来事も、悪僧のイメージを補強するには最適な筋書きです。
もしも本当に道鏡が天皇の座に就いていたならば、日本の歴史はどうなっていたでしょうか?
仏教が国家の中心に据えられ、現在とはまったく異なる「仏教国家」となっていたかもしれませんね。
道鏡事件は、日本史に大きな影響を与えました。
この事件を通じて、天皇は必ず皇族から選ばれるという原則が確立されました。
また、政治と宗教を切り離そうとする意識が強まり、後世の政教分離の思想にもつながっていきます。
すなわち道鏡事件は、日本の国家体制や宗教観に長期的な影響を及ぼす分岐点となったのです。
「皇位継承」や「政教分離」の原則が今日まで受け継がれていることを考えると、道鏡事件が後世に与えた影響の大きさには改めて驚かされますね。
道鏡の死因と評価の変化
770年、称徳天皇の崩御によって後ろ盾を失った道鏡は失脚し、下野国(しもつけのくに:現在の栃木県)薬師寺別当に左遷されました。
772年、死因は記録に残されていませんが、道鏡はこの地で亡くなりました。
道鏡の死は庶民と同じ扱いで記録され、貴族的な格式は与えられませんでした。
ただし極刑には処されず、僧籍も保持されたままであった点は、皇位簒奪を企(たくら)んだとされる者としては異例の軽い処分といえるでしょう。
一時は国家を動かすほどの権力を握った道鏡が、最終的には地方に送られ静かにその生涯を閉じたことは、不幸な結末ともいえます。
けれども、死刑などの過酷な処分を免れたことを考えれば、むしろ幸いだったのかもしれません。
天皇との関係や道鏡事件は、道鏡に「皇位を狙った悪僧」というイメージを定着させました。
しかし史実を冷静に見ると、その評価には疑問も残ります。
称徳天皇は確かに道鏡を厚く信任しましたが、最終的に道鏡に皇位を譲るつもりはなかったと考えられます。
実際に「後継者は自ら定める」との詔(みことのり)を出し、強引に即位させる姿勢は見せませんでした。
加えて、道鏡の失脚後の処遇も死刑や流刑ではなく、薬師寺別当として地方に下げられるにとどまりました。
これは完全な反逆者とはみなされなかったと推測されます。
また、道鏡が大規模な粛清(しゅくせい)や弾圧を行なった記録はありませんし、むしろ仏教を通じて国家を安定させようとした可能性もあります。
既存の貴族勢力にとって目ざわりな存在だったがゆえに「悪僧」として描かれたとも考えられます。
近年では、道鏡を「単なる野心家」と見るよりも、「時代の波に翻弄された人物」「仏教によって国家を安定させようとした指導者」として再評価する見方も出ています。
つまり、道鏡は一方的に「悪僧」と決めつけられる人物ではなく、奈良時代という激動の時代を象徴する存在として理解すべきでしょう。
当時の世の中は不安定であったため、人々の不満や怒りの矛先をそらすために「悪者」が必要だったのかもしれません。
いずれにせよ、人々は昔からスキャンダルを好み、一度悪いイメージがついてしまうと、それを覆すのは非常に難しいものです。
道鏡も「悪僧」というイメージが先行して誤解されてきた人物であると思われます。
歴史は常に一面的ではなく、さまざまな解釈が存在します。
多くの点が不明であり、また時代ごとに評価は大きく変わります。
だからこそ、私たちは先入観やイメージにとらわれず、柔軟に歴史を評価していく姿勢が求められるのではないでしょうか。