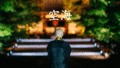最澄と空海は、どちらも平安時代、しかも同時期を生きた僧侶です。
最澄と空海の2人には、次のような共通点があります——
- 遣唐使として同じ船団で中国へ渡り、日本に戻ってからは朝廷の保護を受け、日本仏教の基礎を築いた
- 最澄は比叡山、空海は高野山、というように山中に拠点を築いた
- 死後、朝廷から、最澄は「伝教大師」、空海は「弘法大師」という諡(おくりな)を授かった
しかし一方で、最澄と空海には違いもあります。
その違いについて、ご紹介していきます^^
最澄と空海の違い①:身分
最澄と空海は、面識こそなかったものの、同じ時期に遣唐使団の一員として唐へ渡りました。
しかし、その身分はまるで異なっていました。
最澄は「還学生」(げんがくしょう)でした。
「還学生」とは、遣唐使に同行して往復する学問僧で、留学期間は短期ですが、国が学費を負担し、通訳もつく特別な身分でした。
これは、最澄が桓武天皇から信任を得ていたからでした。
一方の空海は「留学生」(るがくしょう)でした。
「留学生」とは、留学期間は最低でも10年以上で、学費は自費。
通訳はつきませんでした。
最澄と空海のあいだに、最初これだけの差があったというのは驚きです!
ちなみに、空海は唐で師事した恵果の遺言に従い、20年の留学予定を2年で切り上げて帰国しました。
そのため、すぐに都に入ることは許されず、4年間、九州の太宰府(だざいふ)に留め置かれました。
きっと空海は早く都に戻りたくて、うずうずしていたでしょうね。
最澄と空海の違い②:唐で学んだ仏教
唐(中国)にいるあいだ、最澄は、法華経を中心とした天台教学や禅の教え、そして密教などを学びました。
一方の空海は、密教のみを学んでいます。
最澄も空海も密教を学んだ点で共通していますが、1年後の帰国が決まっていた最澄は、当時の中国で広まりつつあった密教の重要性を認識しつつも、その密教を本格的に学ぶにはいたりませんでした。
最澄としては、不完全燃焼だったことでしょう。
これに対し、空海は、わずか3ヵ月で、密教の最高位である「阿闍梨」(あじゃり)を授かるほどに密教を体得し、密教の真髄を受け継ぐ後継者となり、帰国後、真言宗を開きました。
この違いが、帰国後、最澄が空海の弟子になるという決断をもたらすことになったのです。
▼最澄と空海の関係についてくわしく知りたい方は、こちら↓↓↓

最澄と空海の違い③:天台宗と真言宗
最澄と空海がそれぞれ中国で学んだ仏教の違いは、そのまま2人が開いた宗派の違いとなって表れました。
最澄が唐から持ち帰ったのは天台宗の教えで、空海が持ち帰ったのは真言密教の教えです。
両者のあいだには明確な違いがあります。
最澄の天台宗の教え
天台宗というのは、当時の中国における有力な宗派で、インドからもたらされたさまざまな仏教思想=仏教経典を一定の基準のもとに階層的に秩序づけ、理解しようとするのが特徴でした。
多様な仏教経典のあいだには本来、上下関係はないのですが、天台宗なりの整理のしかたによって、『法華経』(ほけきょう)が最上位であるとされました。
その『法華経』の教えは、「一切衆生悉有仏性」(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)という言葉に集約されるように、すべての生きとし生けるものは生まれながらにして仏となる可能性=仏性をそなえていると説きます。
つまり、誰でも仏になれるチャンスがあるということです。
仏になるためには修行が必要ですが、天台宗はそれまでの多様な仏教のあり方を含み込んでいたので、修行の種類は多様でした。
止観(しかん:集中と瞑想)、坐禅、密教の修法、念仏(常行三昧)、千日回峰行など、さまざまな修行が採り入れられていたのです。
空海の真言宗の教え
空海が開いた真言宗は、天台宗のように多様な仏教思想の集合ではなく、インド大乗仏教の最終段階で現れた「密教」という独自の仏教思想に基づいていました。
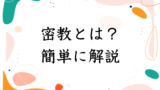
空海は、自身が開いた真言宗は、仏教の最終発展形として、あらゆる仏教の頂点に立つものと考えました。
そのため、真言宗がもっとも重視する経典は、天台宗がもっとも重視する『法華経』ではなく、『大日経』(だいにちきょう)と『金剛頂経』(こんごうちょうきょう)でした。
真言宗において『法華経』も重視されたものの、『大日経』と『金剛頂経』にくらべれば下位に位置づけられたのです。
その密教の最終目標は、生きたまま仏の境地にいたる「即身成仏」(そくしんじょうぶつ)です。
そのための修行として、真言宗では「三密加持」(さんみつかじ)の行が基本となります。
「三密」とは、身密(しんみつ:手で印を結ぶ)、口密(くみつ:真言を唱える)、意密(いみつ:宇宙の真理を心に思い描く)のことです。
要は、〝仏になりきる〟のです。
天台宗では修行によって一歩一歩、仏の境地に近づくのですが、真言宗ではいきなり仏になりきる修行を行なうところが、天台宗と真言宗の最大の違いだと言えるでしょう。
同じ時期に開かれた天台宗と真言宗とで、これほどの違いがあったとは正直驚きました!
最澄と空海の違い④:奈良仏教(南都六宗)との関係
当時の日本で主流だった仏教=奈良仏教(南都六宗)との関係でも、最澄と空海は違います。
最澄は奈良仏教に対して敵対的。
一方の空海は調和的でした。
最澄は、自身が中国から持ち帰った天台宗の教えが奈良仏教と異なると主張します。
つまり、奈良仏教は〝限られた者しか仏になれない〟という教えでしたが、最澄は〝すべての者が仏になれる〟と説きました。
そこで、旧来の戒壇院とは別に、比叡山に天台宗独自の大乗戒壇院(だいじょうかいだんいん)を設立しようとしました。
これに反発した奈良仏教側は、最澄を厳しく批判。
最澄と奈良仏教は対立し、長年にわたって論争しつづけました。
一方の空海は、10代のころ奈良仏教の有力寺院である大安寺(だいあんじ)で学び、また、同寺の重要職務である別当に就いていたこともあるなど、奈良仏教とは密接な関係がありました。
僧侶たちの上奏文(じょうそうぶん:天皇へ提出する書類)を代筆するなど、個人的な関係もあったようです。
そうした調和的な関係を築いていた結果、東大寺のなかに真言宗専門の戒壇院の設立を許されました。
最澄よりも空海のほうが世渡り上手だったのかもしれませんね。
最澄と空海の違い⑤比較表
| 最澄 | 空海 | |
| 生没年 | 767〜822 | 774〜835 |
| 出身地 | 近江国(滋賀県) | 讃岐国(香川県) |
| 留学時の身分 | 還学生 | 留学生 |
| 唐での師 | 智顗(ちぎ) | 恵果 |
| 開いた宗派 | 天台宗 | 真言宗 |
| 拠点となった寺院 | 比叡山延暦寺 | 高野山金剛峯寺、教王護国寺 |
| 学んだ仏教 | 法華経、禅、密教、戒律 | 真言密教 |
| 教えの特徴 | 顕密一致 | 即身成仏 |
| 南都仏教との関係 | 対立的 | 協調的 |
まとめ
-
唐へ渡ったときの身分は、最澄は「還学生」、空海は「留学生」
-
唐では、最澄は天台教学を中心に禅、密教などを学んだ一方、空海は密教のみを学んだ
-
修行によって徐々に仏に近づく天台宗に対し、真言宗は最初から〝仏になりきる〟修行に徹する
-
奈良仏教(南都六宗)に対して、最澄は敵対的、空海は調和的
▼最澄と空海についてさらに広く知りたい方は、こちら↓↓↓