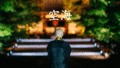今回ご紹介するのは、奈良時代に大きな権勢を誇りながらも、最後は非業の死を遂げたと言われる謎多き僧、玄昉(げんぼう)です。
私はこれまで、「玄昉って、吉備真備(きびのまきび)といっしょに遣唐使として中国へ渡って、政治に関わって失脚した人でしょ?」くらいの教科書的な知識しか持ち合わせていませんでした。
ところが今回、玄昉の生涯と死後にまつわる恐ろしい伝説を知り、正直驚きました!
いったい玄昉の身に何が起きたのか?
その生涯をたどりながら、謎に迫っていきたいと思います^^
玄昉って、どんな人?
玄昉(?~746年)は、奈良時代に活躍した僧で、俗姓は阿刀(あとう)氏(安斗氏)です。
のちの歴史に名を残す玄昉のキャリアは、唐への留学から始まりました。
717年、玄昉は遣唐使の一員として、また学問僧として唐へ渡ります。
このとき、同じ遣唐使として唐へ渡ったのが、のちに玄昉と政治の表舞台でタッグを組むことになる吉備真備(きびのまきび)でした。
玄昉は唐で法相宗(ほっそうしゅう)を学び、なんと18年もの長きにわたって異国の地で研鑽を積みました。
その才能は、当時の唐の皇帝である玄宗に認められるほどでした。
玄昉は三品(当時の中国で3番目に高い位)に準ずる位と、位の高い者にしか許されない紫色の袈裟(けさ)を賜(たまわ)りました。
これは、並大抵のことではありません!
玄昉が超優秀だったことを物語っています。
異国で最高の評価を得た玄昉は、一切経5000巻と数々の仏像とともに、735年に帰国しました。
帰国後の玄昉は、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いでした。
玄昉は僧侶の最高位である僧正に任じられ、内裏(だいり)で仏教の儀式を行う「内道場」へ入ります。
そして、聖武天皇の母である藤原宮子の病を祈祷によって回復させたことで、天皇からの信頼を不動のものとしました。
この功績により、玄昉は政治に深く関わるようになり、吉備真備とともに橘諸兄(たちばなのもろえ)政権の中心人物として権勢をふるうことになります。
玄昉の進言は、聖武天皇による東大寺建立の発願にも大きな影響を与えたと言われています。
また、玄昉は、日本仏教において、すでに日本に伝えられていた法相宗の教義をさらに深め、新しい知識をもたらした功労者でもありました。
玄昉の華々(はなばな)しい活躍は、まさに唐での厳しい修行の成果であり、帰国後の日本の仏教界、ひいては政治にまで大きな影響を与えることになりました。
玄昉と吉備真備との関係は?
玄昉の生涯を語るうえで欠かせないのが、吉備真備の存在です。
玄昉と吉備真備の二人は同じ遣唐使として唐へ渡り、帰国後も共に橘諸兄政権を支え、権勢を二分するパートナーでした。
政治のトップに僧侶と知識人が並び立つというのは、当時としては異例でした。
玄昉と吉備真備が政治の中心にいたことで、時の朝廷では学問や仏教が重んじられたことでしょう。
しかし、その隆盛は、藤原氏との対立をもたらします。
玄昉と吉備真備を排除しようと、藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ)が九州で兵を挙げたのです。
「藤原広嗣の乱」です。
「藤原広嗣の乱」は最終的に失敗に終わり、藤原広嗣は処刑されますが、玄昉と吉備真備の政敵は藤原広嗣だけではありませんでした。
その後、急速に力をつけてきたのが、藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)です。
藤原仲麻呂の台頭により、橘諸兄政権は力を失い、玄昉と吉備真備もその影響を受けます。
興味深いのは、藤原仲麻呂政権下で、玄昉と吉備真備が同じ九州へ左遷されたことです。
玄昉は筑紫(つくし)の観世音寺(かんぜおんじ)の別当になり、吉備真備も九州へ送られました。
これは、藤原広嗣の怨霊を鎮めるために、あえて藤原広嗣に縁があった地である九州へ、玄昉と吉備真備を送ったという説もあります。
もしもこの説が本当なら、玄昉と吉備真備は権力争いの犠牲になっただけでなく、怨霊の標的役まで担わされたということになります!
私は、当時の政治の怖さを感じてしまいました(震)
玄昉はなぜ左遷された?
玄昉へのねたみや反感が原因?
玄昉が左遷された直接的な原因は、橘諸兄政権が衰退し、藤原仲麻呂が政権を握ったことにあります。
しかし、それだけではなかったようです。
玄昉は、その人格に対して周囲からの批判が強かったとされています。
当時の史書である『続日本紀』(しょくにほんぎ)には、玄昉の死が「藤原広嗣が霊の為に害せらる」と記されており、玄昉が藤原広嗣の怨霊による復讐のために死んだのだと人びとのあいだでささやかれていたことがうかがえます。
さらに、後世の書物になると、玄昉に関するスキャンダラスな噂が次々と登場します。
『元亨釈書』(げんこうしゃくしょ)には「藤室と通ず」(藤原氏の妻と関係を持った)とあり、これは聖武天皇の母、藤原宮子(ふじわらのみやこ)のことだろうと言われています。
『今昔物語集』や『源平盛衰記』では、玄昉が光明皇后と密通し、それを藤原広嗣が見とがめたことが乱の原因であったとまで書かれています。
もっとも、これらの話は信憑性に乏しく、玄昉が権勢を誇ったためにねたまれた可能性が高いとされています。
しかし、こうした噂が広まった背景には、玄昉が権力の中枢にいたことへの周囲のねたみや反感が根強くあったことが想像できます。
玄昉は死に方も悲劇的だった?
玄昉にとって左遷以上に悲劇的だったと伝わるのは、その死に方です。
左遷された翌年の746年、玄昉は観世音寺の落慶法要の導師を務めていました。
そのとき、空に雷鳴がとどろき、黒雲の中から現れた赤い衣の男が玄昉をつかんで空へと連れ去り、身体をバラバラにして地上に投げ落としたというのです!
この赤い衣の男こそ、怨霊となった藤原広嗣でした。
玄昉の胴体は観世音寺に、そして首は遠く奈良の都にまで飛来し、興福寺の近くに落ちたと言われています。
この首が落ちた場所に供養のために建てられたのが、東大寺南大門から南へ約1kmのところに今も残る「頭塔」(ずとう)です。
もちろん、上記の話は伝説です。
しかし、これらの伝説は、玄昉の功績の華やかさとは対照的に、なんとも悲惨で奇怪です。
興福寺南円堂に安置されている「法相六祖坐像」のうちの1体である玄昉像(康慶作)は、眉間にしわを寄せ、泣きながら許しを請うように両手を組んでいる姿で表現されています。
この玄昉像を、伝説を知ったうえで見ると、玄昉の悲劇性がひしひしと胸に迫ってくるのではないでしょうか。
玄昉は権力の頂点を極めたものの、最後は怨霊の仕業(しわざ)と噂される死を迎えました。
これは、玄昉がどれほど人びとからねたまれ、そして、いかにその死が悲劇的であったかを物語っています。
本当のところはどうかわかりませんが、玄昉という人物が、当時の人びとの心に強烈な印象を残したことは間違いありません。
その一方で、玄昉は、並外れた才能を持ち、天皇から絶対的に信頼される僧侶でした。
陰と陽。
そのギャップがむしろ、玄昉の存在感をグッと高めているのかもしれませんね。